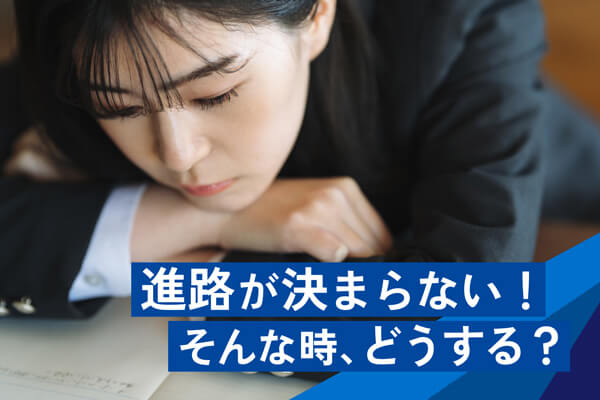慣用句に弱い受験生が増えている!? 背景に読書習慣の減少、読みやすい内容の物語の増加
お気に入りに登録
 しつこいほどに活字離れが叫ばれ続けている昨今。そんな中、言葉の乱れや語彙力の低下も課題となっている。そこで、「子どもの語彙力が低い」と悩む小6女子の保護者に、中学受験のスペシャリストである平山入試研究所の小泉浩明氏が答える。
しつこいほどに活字離れが叫ばれ続けている昨今。そんな中、言葉の乱れや語彙力の低下も課題となっている。そこで、「子どもの語彙力が低い」と悩む小6女子の保護者に、中学受験のスペシャリストである平山入試研究所の小泉浩明氏が答える。
***
【質問】
一般的に知られているような言葉に対する知識が乏しいです。大人のように経験を積んでいればそう難しくないと思いますが。なるべく多くの本を読むしかないのでしょうか?(小6女子の母親)
【答え】
ことわざや四字熟語、そして慣用句に関する知識が乏しいと感じていらっしゃるのでしょう。これはお子さまだけの問題ではなく、特に慣用句の不足が受験生一般に目立つように思います。これには2つの要因が考えられます。まずは、読書の習慣の減少、あるいは本の多様化により読みやすい内容の物語が増加し、子どもたちがそちらのほうを好んで読んでいるということです。それらはいわゆるファンタジーものなど、読みやすいが難しい言葉はあまり身につかないような本です。もうひとつは、そのような子どもたちの状況に反して入試問題は難しく、本文に出てくる熟語や慣用句のレベルは相変わらず高いということです。
豊かな語彙を持ちそれらを自由に使いこなせるようになるまでには、長い鍛練の時間が必要です。低学年のうちから読書や辞書を使う習慣を身につける。そして、5、6年生になったら、不足している語彙を確認するためにも、単語集を演習することで入試の頻出語彙をまとめる。この一連の学習が、語彙力強化のための最も効果的な勉強法だと考えます。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 漢字・指示語・熟語・ことわざ・慣用句など、国語のすべてが苦手で困っています[中学受験]
- 【自由研究テーマ 中学生】え戸時代のくらしについて調べる
- 泣き虫なのは気弱だからではない?自己表現ができれば泣き虫も卒業できる!
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- 【自由研究テーマ 中学生】新聞紙が野菜のせん度を守る効果を調べる
- 人一倍敏感で傷つきやすい「敏感っ子(HSC)」をどう育てる? 5人の敏感っ子を育てたママに聞いた3つのポイント
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 【自由研究】日本人ノーベル賞受賞者の研究を調べる <中学生>
- 言い換えるだけ!定期テスト前に中高生のやる気を引き出す声かけ5選













![漢字・指示語・熟語・ことわざ・慣用句など、国語のすべてが苦手で困っています[中学受験]](/juken/201308/img/KJ_20130812_01.jpg)
![「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201003/20100309-1.jpg)