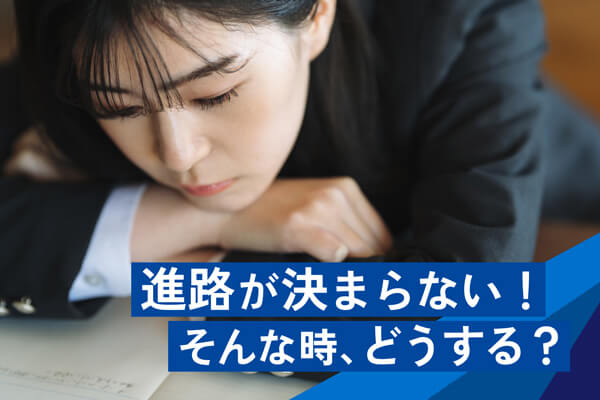図形問題克服のカギは、“解法の道具”と“手順の俯瞰(ふかん)”
お気に入りに登録
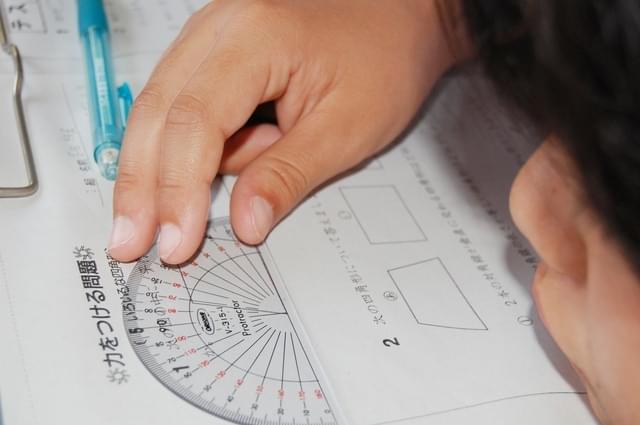 算数問題、特に図形の問題を苦手とする子どもは少なくない。神経質・強気なタイプの小6女子を持つ母親からの相談に、平山入試研究所の小泉浩明氏が図形問題克服の秘訣を指導する。
算数問題、特に図形の問題を苦手とする子どもは少なくない。神経質・強気なタイプの小6女子を持つ母親からの相談に、平山入試研究所の小泉浩明氏が図形問題克服の秘訣を指導する。
***
【質問】
図形がとにかく苦手です。補助線をひいて考える問題でも、見当違いのところにひいて、長く考えていることが多いです。たくさんの問題をやって慣れようとしていますが、なかなか解けません。(小6女子の母親)
【小泉氏からのアドバイス】
算数が得意な子と、不得意な子の違いを考えてみます。得意な子は“解法の道具”を十分に持っています。解法の道具とは、公式や計算方法、「補助線をひく」などの解き方、「二等辺三角形の底角は等しい」などといった性質を指します。これらを図形問題の条件や求めるものによって使い分けるのです。解法の道具を十分に持たない子どもは、なかなか正解にたどり着けません。
もう一つ大事なことがあります。算数や数学を解くためには、解法の手順を「俯瞰(ふかん)」つまり「全体を上から見ること」が必要です。最初から最後までの道筋ではなく、次とその次くらいまでの手順を考えていく程度で構いません。その手順が正しいかどうかは、正解が出るまでわからないので、当然、試行錯誤の連続になります。しかし、問題数をこなしていれば、「おそらくこれでよいのではないか」という勘も働くようになり、ある程度は自信を持って問題を解くことができるのです。
さて、お子さまのケースですが、解法の道具を十分に持っていないか、あるいは解法の手順を俯瞰していないかのいずれか、あるいは両方だと思います。前者に関しては、数多くの問題を解いて解法の道具に慣れ親しむことで解決できます。そして、後者に関しては次の手順だけでなくその次の手順までも合わせて考えるクセをつけるとよいでしょう。いずれにしても、問題演習をこなすことで身に付けていく力だと思います。
出典:算数の図形の問題で、補助線を見当違いのところにひいて、長く考えていることが多い[中学受験] -ベネッセ教育情報サイト
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- 【一人お風呂の始め方】お風呂はいつから一人で入る? 異性の親と一緒に入るのはいつまで?
- 数学を苦手にしない!高校生が数学の実力を鍛えることができる勉強法とは?
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 赤ちゃんが飛行機に乗れるのはいつから? 下調べと事前準備で快適な安全な移動を
- 【PR】コンタクトデビューはいつから?低年齢化で子どもが使っても大丈夫?
- クラス替え 仲のよい友達とクラスが分かれて元気がない我が子…何と声をかける?
- 小学校入学準備「幼児期から始める! 小1プロブレム対策」
- 数学の定期テスト対策で、成績上位者の70%は「演習」を行い、成績下位者の44%は「暗記と見直し」を行っている













![「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201003/20100309-1.jpg)