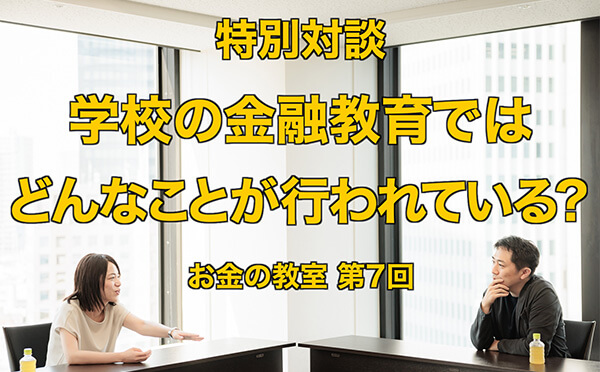学校では今 【第13回】「プレイフル」な学び ~楽しいことの中に学びはあふれている-小泉和義-
お気に入りに登録

「プレイフル」という言葉は、聞きなれない言葉かもしれません。適切な日本語に翻訳するのは難しいのですが、「何かに夢中になったり、ドキドキワクワクしたりするなど、前向きな気持ちでいっぱいになっている状態のこと」を指します。今回は、「プレイフル」と「学び」との関わりについてお話しします。
学校の勉強は楽しい?
子どもたちは、一つのことに熱中したり、好奇心を持って物事に取り組んだりする経験をたくさんしていると思います。たとえば、友達とサッカーを楽しんだり、1人でゲームに集中したりしている時などがそれに当てはまります。そうした経験をしているとき、子どもたちの気持ちはとても前向きです。
さて、学校の授業は子どもにとって楽しく、夢中になれる時間なのでしょうか。恐らく、多くの子どもにとって、答えは「ノー」でしょう。勉強は、どうしても「つまらないもの」「つらいもの」というイメージが先行します。学校から宿題が出れば、仕方なく取り組まなければならないし、学校の授業が仮につまらなくてもその時間はずっと教室で耐えなければなりません。義務的にしなければならないことには、だれだって前向きにはなれません。もちろん、つらいことをやり遂げることも重要ですが、授業のほとんどがつらく、つまらない時間だとするなら、子どもの学ぶ意欲は高まらないと思います。したがって、「プレイフル」な感情や感覚は、学びにはとても大切なのです。
3つの学びの情景
先日、チャイルドリサーチネット(幅広い分野の研究者とともに、子ども研究を行うインターネットを中心にした研究機関)の国際会議があり、その中で、プレイフルな学びに関する議論をしました。
会議の中では、幼児期の議論が中心でしたが、その中で、同志社女子大の上田信行教授が提案された考え方は、小学校以降の学びに有効な内容だったので紹介します。
「学び」には、三つの情景があり、一つは「知識伝達型の学び」です。知識や技能を系統的に効率よく習得するための伝統的な教授型の学習スタイルです。
二つ目は、「構成主義的な学び」です。仲間とともに協働して取り組んだり、対話したりして新しい気付きや発見を促す学びです。現在学校現場では、このような学習形態を積極的に取り入れようとしています。この方法だと、子ども自身が主体的に学びに関わる場面が増えるため、「プレイフル」な感覚を得やすいのではないかと思います。
そして三つ目は、「恋愛型学び」です。周囲を喜ばせようとして行うパフォーマンスのように、自分ではなく特定の対象に向けた情熱によって深められる学びです。「どうすれば相手を喜ばせることができるだろうか」と考える過程の中に、多くの学びが含まれています。
学びとは、本来「自分自身のため」に向けられたものと考えがちですが、「だれかのため」と視点を変えてみると、新しい発見があるかもしれません。たとえば、家で「料理を作る」ことは「だれかのため」でもあります。お子さんに料理を手伝ってもらう際に「お父さんに『おいしい』と思ってもらえる料理にするために、どう工夫しようか」と一緒に考えることが、「プレイフル」な学びにつながっていくのだと思います。
「楽しいことの中に、学びはたくさんあふれている」と考えると、学びにも前向きになれます。学校の勉強も楽しく取り組めるのが一番よいですが、もしそれが難しければ、日常の生活の中で「プレイフル」になれる学びを探してみてはどうでしょうか。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 子育てに取り入れたい『プレイフルシンキング』で、子どもの「やってみたい!」「知りたい」が生まれる
- 合格前に予約もアリ!今知っておきたい、受験生のひとり暮らしの「部屋探し」事情 《ガイドブック無料プレゼント中》【PR】
- 2025年版「子ども用GPS端末」のおすすめ9選!安くて人気なのは?キッズスマホとの違いは
- 学校の金融教育では、どんなことが行われている?【親子で学ぶお金の教室第7回】
- 入学準備で一番大切なことは?[教えて!親野先生]
- 「知らない人について行っちゃダメ」の危険な落とし穴 子どもを犯罪から守るために伝えるべき「最も重要でわかりやすい」ポイント【専門家監修】
- 学校では今 【第10回】表現することを通して、考える力を高める‐小泉和義‐
- ミシンで作る入園、入学アイテム別名入れのポイント
- 子どもの水難事故はなぜ減らない? 身近に潜む危険とは