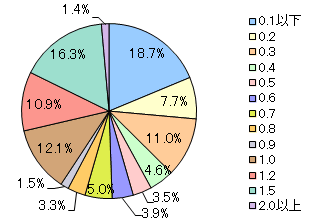「通級」教室が年々増加 一般の学校で特別支援教育
お気に入りに登録
一般の学校の普通学級に在籍する障害のある子どもが、一部の時間に別教室や特別支援学校で授業を受けることを「通級」といいます。この通級による指導を受けている子どもたちの数は年々増加していますが、2011(平成23)年度には全国で初めて6万5,000人を超えたことが文部科学省の調査でわかりました。2011(平成23)年度は全国の公立小・中学校の約1割で通級による指導が行われています。
通級は、もともと言語障害や弱視など比較的に障害が軽い子どもたちのために「自立支援」など普通学級ではできない障害のある子ども向けの教育をするためのもので、1993(平成5)年度に制度化されました。その後、2007(平成19)年度にそれまでの「特殊教育」が「特別支援教育」に切り替わるのに先駆け、2006(平成18)年度からは高機能自閉症などの発達障害も通級による指導の対象に加わりました。
文科省の調査によると、全国の公立小・中学校で通級による指導を受けている子どもの数は、2005(平成17)年度は3万8,738人でしたが、07(同19)年度は4万5,240人、09(同21)年度は5万4,021人と増加し、11(同23)年度は6万5,360人となりました。
同時に通級指導教室を設置する学校の数も増加しており、2011(平成23)年度は全国の公立小・中学校などで通級指導教室(障害別を除く)を設置しているのは3,061校に上り、公立小・中学校全体の9.6%に当たっています。通級指導教室を設置している学校は、過去3年間で25.5%も増加した計算になります。
通級は制度化以来、その指導を受ける子どもたちの数が増加していましたが、最近になって急増している主な理由は、発達障害のある子どもが通級指導を受けるようになったことです。通級指導を受けている子どもの障害で最も多いのは言語障害の3万1,607人ですが、過去7年間程度あまり変動していません。それに対して自閉症は1万342人(前年度比1,194名増)、学習障害(LD)は7,813人(同1,158名増)、注意欠陥多動性障害(ADHD)は7,026人(同1,228名増)で、年々増加を続けています。
また、視覚・聴覚障害や言語障害などのある子どもたちは、特別支援学校などに置かれた通級指導教室に通うケースが多いのに対して、LD とADHDの場合は、自校に設置されている通級指導教室で指導を受けることが多いのが特徴です。通級指導のための時間数を見ると、週1時間が47.2%、週2時間が30.9%で、この二つが全体の78.1%を占めています。通級指導に当たる教員は、特別支援学級担任、通級指導担当教員など特別支援教育の知識を持つ者が当たることが求められています。
なお、発達障害のある子どもに対して、通常の授業の一部を別教室で行うことがありますが、これは「取り出し指導」と呼ばれるもので、通級指導とは別のものです。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- Shift│第13回 「デザイン・エンジニアリング」が新しい課題解決型授業を生みだす -子どもたちに伝えたい「失敗は成功への過程に過ぎない」- [5/6]
- 子どもがなりたい職業 人気ランキング 小学生は「野球選手」「ケーキ屋さん・パティシエ」
- Shift│第13回 「デザイン・エンジニアリング」が新しい課題解決型授業を生みだす -子どもたちに伝えたい「失敗は成功への過程に過ぎない」- [4/6]
- 子どもの発音が気になったら……今すぐマネしたいお口の筋力アップ方法
- Shift│第13回 「デザイン・エンジニアリング」が新しい課題解決型授業を生みだす -子どもたちに伝えたい「失敗は成功への過程に過ぎない」- [6/6]
- 言うことを聞かない子どもが2週間で変わる!?親がとるべき戦略とは?
- Shift│第13回 「デザイン・エンジニアリング」が新しい課題解決型授業を生みだす -子どもたちに伝えたい「失敗は成功への過程に過ぎない」- [1/6]
- 小学校入学式の日程や流れ、持ち物、服装、写真撮影は?まるっとガイド!【体験談あり】
- 教育フォーカス│変わる学校教育、その変化の潮流と課題を読み解く~「第6回学習指導基本調査」より~│[第2回]アクティブ・ラーニングは高校の学び改革のチャンスだ —探究学習・課題解決型学習の資産をどのように生かすか—