「自信」は、自分を信じて行動することで、育まれる!ボーク重子さんに聞く!これからの子どもを幸せにする「非認知能力」の育み方 ~Lesson14 最終回 自信
- 育児・子育て
ライフコーチのボーク重子さんに、子どもの「非認知能力」の育み方についてお伺いしてきたこの連載も、今回で最終回です。最終回のテーマは、「自信」。
非認知能力を育んでいくことで、自分や他者、社会に対しても責任ある意思決定ができるようになり、そうした行動の結果として得られる、ポジティブな感情のひとつが「自信」です。
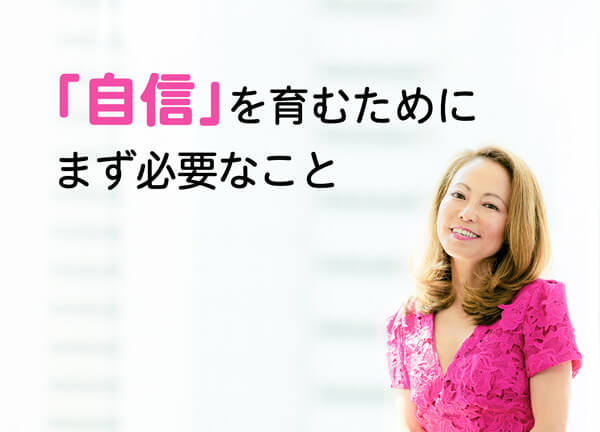
【保護者のかたのお悩み】
Q.子どもが学校で積極的に発言しません。子どもに聞くと、「自信がないからみんなの前で言いたくない」と言います。どうすれば自信をつけることができますか?
親は子どものよい聞き役に
聞く時の鉄則は「否定しない」
ボークさん:発信って多かれ少なかれ勇気が要りますよね。だからまずは学校に「安心して発信できる環境があるか?」が問われるかと思います。
子どもがみんなの前で言いたくない理由は、「間違えたくない」と思っているからでしょう。それは子どもの問題ではなく、学校が「発信することが大切」と子どもとの向き合い方を変える必要のある点ではないかと思うのです。
もっと柔軟に、子どもたちが思っていることを自由に表現できる場所で学校はあるべきだと思います。そのためには、相手の違いを受け入れ、自分も正解だけれど、相手も正解。そう思える環境を学校の中に作っていく必要があります。
誰かひとりの考えだけが正解ではなくて、いろいろな考えがあり、その中で、議論しながら最もいい答えをともに導き出していく。これがこれからの学校生活の中で育んでいきたい共感力・協働力・社会性という非認知能力だと思います。
先生方がまた、自分の答えだけが正解だと思わないことも大切だと思います。
先生の答えだけが正解だとすると、学校で何かをやろうとした時にも、先生が「こうしなさい」と言ったことを、いつも子どもが正解だと思ってしまうからです。
「違う考え方もあるのではないか」「こうやったほうがいいかもしれない」といったアイデアは、考える余地があるからこそ、生まれます。それは家庭の中でも同じことです。
「協働力」の回でもお話しましたが、親はトップダウンをやめて、子どもに言うことを聞かせるのではなく、親が、子どものよい聞き役に徹することです。
娘が通っていたボーヴォワール校でも、先生方はとても熱心に、それが仕事だと言わんばかりに子どもたちの話に耳を傾けていました。
親が子どもの話を聞く時にはまた、子どもを「否定しない」ことが大切です。否定されることで、「次も間違っていたらどうしよう」と子どもは思い、自由に発言することができなくなってしまいます。
おうちのかたはぜひ、「へえ、面白そうだね!」「なるほど!」「教えてくれてありがとう!」といった相槌をうち、まるごと子どものことを肯定してあげてください。そうすることで、子どもが安心して自分の意見を言えるようになります。
子どもの「自信」を育てるために
親は失敗を見守って
「自信」とは、ありとあらゆる非認知能力を含んだ最終的な副産物であり、突き詰めれば「自分を信じる力」ではないでしょうか。
連載の最初にもお話しましたが、自己肯定感を土台として、対自分、対社会、対他者に対して行動した結果、達成感とともに得られるポジティブな感情が「自信」です。
自信があると、人は行動ができるようになります。人生は、誰かが作ってくれるものではなく、自分の行動が決めていくものです。行動しなければ、自分の選択肢を広げていくことはできません。そして行動していった結果が、「自分」という実績になっていくのではないでしょうか。
もちろん、「行動すれば必ずうまくいく」というわけではありません。うまくいかないこともたくさんあるでしょう。それでも、できると自分を信じなければ何も始まりませんし、いろいろな失敗をしてこそ、そこから学び、前に進むことができます。失敗とは言い換えれば「素晴らしい問題解決の機会」なのです。
だから失敗しても大丈夫。立て直せるという自分自身への信頼と、小さなことでもやるといったことをまずはやってみる。その体験の積み重ねが大切です。
親は子どもに完璧を求めずに、大らかな気持ちで挑戦や失敗を見守ってあげてください。子どもの自信を育てるためには、親は子どもに失敗させる勇気をもたせなくてはいけないでしょう。失敗しなければ学べないことはたくさんあります。
親は子どもが多くの失敗を経験できる機会を奪わず、応援するのが務めではないでしょうか。

自信がなくて踏み出せない時には
ステップバックすることも大切
何かをやろうと思った時に、「自信がなくて」その一歩が踏み出せないという時には、ステップバックして、「できそうなことからやってみる」ということもまた大切です。たとえベイビーステップだったとしても、その体験を積み重ねることで、自分自身の問題解決能力に対する信頼の度合いが上がっていきます。
どうやって問題を解決するか。それはこれまで自分が行動してきたことによって、自分の中に対策ができるようになっていきます。だからこそ私は、自信をもつためにも、まずは行動することが大事だと思います。 Just do it!
まとめ & 実践 TIPS
「自信」をつけるためには、まずは「行動」することが大切だとわかりました。
また行動することで、自分自身の問題解決能力を高めていくことができるので、保護者のかたからの子どもが失敗することを恐れずに行動できるような声かけや、普段の接し方が大事なようです。
非認知能力を高めながら、子どもの自信を育んでいきたいですね。
非認知能力について、もっと詳しく読みたいかたはこちら
子どもを幸せにする非認知能力の育み方
- 育児・子育て















