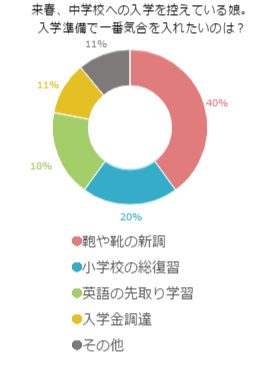現代の子育てでも活かせそう?! 祖父母世代も聞いて育った日本の迷信
お気に入りに登録
子育ての方法はひと昔前とは様変わりしていますが、しつけの基本は今も昔もそれほど変わっていません。おはようやありがとうがちゃんと言えるとか、食事のときは残さず食べる、ちゃんと座って食べる、お箸の持ち方や人に迷惑をかけないなど…。昔の暮らしの智恵の中にも、現代の子育てに活かせそうな迷信があります。知っておけばしつけに役立つかも?

はさみ箸は不吉
一つのものを二人の箸を使ってつまむのが「はさみ箸」です。お葬式の儀式のため、不吉といわれています。子どもが日常ではさみ箸をすることはあまりないと思いますが、箸の使い方を教えるときには、正しい持ち方とともに、やってはいけない作法も教えてあげては? 箸のNG作法としてよく挙げられるのは、箸の先を舐める「ねぶり箸」、箸で器を引き寄せる「寄せ箸」、箸を口にくわえる「くわえ箸」、箸を握って使う「握り箸」など。作法は子どもの頃からきちんとしつけてあげたいものです。
お米をこぼすと目が見えなくなる
昔から日本はお米を主食としてきました。お米は、江戸時代には価値の高い作物とされ、農民は年貢をお米で納めるなど、お金のような存在でした。庶民は収穫のときのお祭りでしかお米を食べられなかったそうです。その価値もさることながら、農民たちが一から丁寧に作ったお米を大事にする意味でも、お米を粗末にしないように言われた迷信です。食べ物の大切を伝えるときに、教えてあげましょう。日頃から言って聞かせていれば、子どもの心にも残るはずです。
茶碗を叩くと餓鬼(がき)が集まる
子どもは、食事中に茶碗やお皿を箸などで叩いたり、騒いだりします。そんなときに子どもを沈めるために使えそうなフレーズです。餓鬼というのは、文字通り鬼のこと。生前悪事を働いた人が餓鬼道に落ちた姿といわれています。この鬼は、飢えと渇きをさいなまれているため、人間界に降りてきて人にとりつき、食料を食べ尽くすという説があるとか。昔のように飢餓に苦しむ時代ではありませんが、食料は無駄にしてはいけないことを子どもに伝えられるのでは。子どもは鬼を怖がります。食料を無駄にしたら良くないことを早くから教えてあげることで、子どもの心の中に食料は大事なものという意識を植え付けることができるのではないでしょうか。
火遊びをする子はおねしょをする
好奇心が旺盛で、いろんなことにチャレンジしたい子どもたち。好奇心は大事ですが、いつもよいことばかりにチャレンジするわけでないでしょう。大人が危ない、やめなさい! と叱るようなことにも興味を持つのが子どもです。そんな子どもをたしなめるための迷信といえるのではないでしょうか。火遊びは言語道断ですが、火遊びに限らず、悪いことをした子どもに注意を促すときに使えるのでは。子どもにとっておねしょはとても恥ずかしく嫌なことです。そんな子どもの羞恥心に訴えることで、いたずらを防ぐことができるかもしれません。
日本には数多くの迷信があります。その多くは、社会のルールや習慣、価値観に基づいたものだといわれています。子どものうちに迷信でしつけを覚えた人も多いはず。迷信のほとんどは科学的根拠が少ないようですが、これは日本人の歴史の中に根付いてきたしつけや暮らしの智恵です。現代の日本にはそぐわない迷信もありますが、しつけという点では、基本的に大きな変化は少なそう。迷信を伝えることは、子どもたちが日本の伝統に触れる機会にもなるかもしれませんね。
あなたにおすすめ
- 子育ての今と昔 子の子育てについて祖父母の本音は?
- 子どもの幸せは、保護者の幸せから? 2万組の親子調査で判明した「収入や成績よりも大切なこと」
- 心理学ってどんな学問?
- こんな時どうする?子どもの心をあっためる声かけレッスンCASE3:子どもをほめてもうれしくなさそうな場合
- 子どもの「幸せ」につながる読書って?
- 毎日繰り返すあの時間。9歳の我が子の「仕上げ磨き」が、母にくれたもの
- 【入学準備】どうする?年長さんの文字の学習。ひらがなやカタカナを正しく美しく書けるようにするコツ | 小学校入学準備 ベネッセ教育情報サイト
- 小学校の成績や通知表の付け方は?知っておきたい読み解き方とお子さまへの声かけ
- お母さんは毎日大変!育児の息抜き、何してる?