苦手な算数 あと約100日間ですべきことは?[中学入試 6年生]
お気に入りに登録
入試本番があと100日程度まで迫ってくると、特に苦手教科の対策に頭を悩ませる保護者のかたが多いと思います。入試が近づけば近づくほど、受験勉強は「優先順位のつけ方」が重要になってきます。
今回は、算数が苦手な場合の対策法についてお話しします。
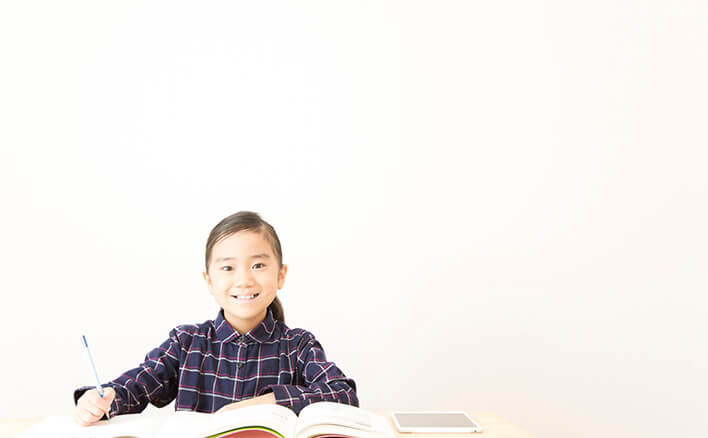
「△」の問題を「○」に変え、「×」は断捨離を
一部の難関校を除き、計算問題と、「一行問題」と呼ばれる基本的な文章問題は、入試には必ず出題されます。ここだけでもミスのないようにきっちり正解すれば、受験者平均点に達するケースが多いのです。残りの大問は、たいてい4つか5つありますので、自分の得意な問題から順に解けるようにしていきましょう。この優先順位のつけ方が大切です。
過去問を解く際、まず全体を見渡し、自信のある問題に○、なんとか解けそうなものに△、歯が立ちそうにないものに×をつけましょう。○、△の順に解き、×はいさぎよく捨てます。その後、丁寧に復習しながら、△の問題をひとつずつ○に変えていけば、合格者平均点は近づいてきます。「捨てる」のは怖いことですが、「不可能に挑戦する」より「できることをきちんとやる」ほうがずっと大切です。「断捨離」を肝に銘じてください。
過去問演習の得点が、合格者最低点の10%を上回れれば(合格者平均点に相当)、合格の可能性は非常に高くなります。それは△を○にすることで可能になるのです。
計算問題は、速く正確に解く工夫を
入試では、複雑に見えるけれど、工夫次第ですっきりと簡単に解ける計算問題がよく出されます。このような問題には、「解き方のプロセスを考えられる、思考力のある子に来てほしい」という学校側のメッセージが込められているのです。こういった問題をやみくもに頭から計算すると、まちがえる確率も高く、時間もかかりすぎてしまいます。計算が苦手な子にこそ、分配法則や結合法則を使って、「速く、簡単に解く方法はないか」と工夫する習慣がつくよう、アドバイスしてあげてください。
「なんとなく」をなくしてミスを防ぐ
算数が苦手な子に共通していることは、一つひとつのプロセスを明確にしないまま、「なんとなく」解き進めてしまうことです。例えば図形の問題で、「直角」と示されていないのに、見た目で「ここは90度」と早合点してしまう、「12÷□=3」で□の数を問われたとき、「わり算の反対はかけ算だから、3×12で答えは36」と勘違いしてしまう、といったミスがよくあります。考え方の道筋を、丁寧に式や図にし、確かめながら解き進める習慣を、今から徹底させてください。
また、面積を求める問題などで、「補助線をひけば解ける」と考え、やみくもに線をひいて考え込んでしまうケースもよく見かけます。面積の問題は、「三角形の面積の組み合わせ」と考えれば解けるものが多いので、補助線は三角形の「底辺」と「高さ」がわかるようにひくのがコツです。
「なんとか解けそう」な△の問題は、「なんとなく」や「やみくも」をなくし、「こうすれば解ける」という手ごたえや手順をつかむことが大切です。「なんとなく」数多くの問題をこなしても、その問題の意図や法則を理解しなければ身にはつきません。解ける問題を一つずつ増やしていけば、合格者平均点は必ず手の届くところに見えてきます。保護者のかたには、「あれもできない、これもできない」ではなく、「これが解けるようになった、あれが解けるようになった」と前向きに考えて、お子さまの挑戦を見守ってあげていただきたいものです。
(筆者:金廣志)













![算数の苦手、どう克服する? [中学受験 5年生]](http://benesse.jp/juken/201610/img/LP_20161026_01.jpg)
![【6年生】 入試説明会の活用、志望校最終決定 [中学受験歳時記コラム ~いま取り組むべきこと~ 第56回]](/img_o/kj/juken/201510/20151029-1.jpg)
![算数の苦手を防ぐ3つの習慣とは?[中学受験 4年生]](http://benesse.jp/juken/201610/img/LP_20161025_01.jpg)









