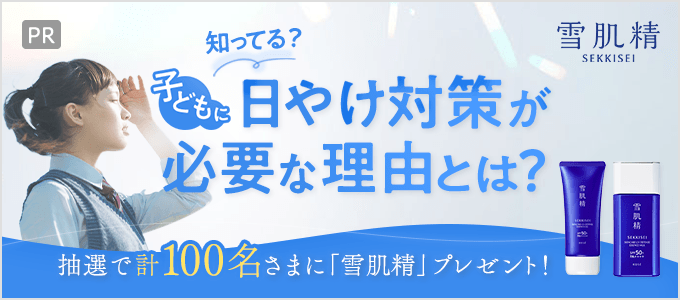文章問題でひっかかると、解けるレベルの問題も途中までしかできない[中学受験]
お気に入りに登録
平山入試研究所の小泉浩明さんが、中学受験・志望校合格を目指す親子にアドバイスする実践的なコーナーです。保護者のかたから寄せられた疑問に小泉さんが回答します。

【質問】
算数の計算問題は得意で、過去問は超難関校の問題も9割以上正解します。ただ、文章問題で一度ひっかかってしまうと、他の解けるレベルの問題まで途中までしかできていないことがよくあります。試験の時間配分もあまりうまくないようです。どのように改善すればよいでしょうか?
相談者:小6男子(論理的・強気なタイプ)のお母さま
【回答】
客観的に状況を判断できる冷静さや能力を身に付けて結果を残す
■「ステ問」の対処により点数に大きな差が出る
「文章問題でひっかかると、他の解けるレベルの問題も途中までしかできていない」ということはよくあります。よくありますが、何とも悔しいことでもあります。特に簡単な問題に気付かず手を付けなかった時は、もったいないことをしたと本当に情けなくなるものです。入試では1点差によって合否が分かれる場合がありますから、こうした難しい問題は後回しにして、すぐできる問題からやってしまうということが大切です。やり残した問題でも、あとで解答を見ると解けそうもない難問であれば、やらずに捨ててしまって正解であったということです。
このような問題を一般的に「ステ問(捨て問)」と呼びますが、「ステ問」の対処の上手・下手により、同じ実力があってもテストの点数で大きな差が付いてしまうのです。
■精神的な要因、あるいは「ステ問」を見抜けない可能性も
それでは「ステ問」の対処に、なぜ上手・下手が出てしまうのでしょう。一つには、精神的な要因が関わっていると思います。たとえば、強気なお子さまは解けない問題を意地でも解こうとするでしょう。また、神経質なお子さまは途中でやめるとそれまでの時間がもったいなくて、もう少し、もう少しと深みにはまってしまうかもしれません。本当は、ある程度やってできそうもなければ、途中でやめることがよい選択なのですが、それがなかなかできないのです。
こうした状況は、よく山登りに例えられます。「登る勇気より引き返す勇気」を持ちなさいというものです。試験でも、全体を考えて、できそうもなければ他の問題を先に解くという冷静さや決断力が必要なのです。
あるいは精神的な要因だけでなく、できるかできないかわからないから引き返せないのかもしれません。深みにはまる前に、「これは難しい問題だ」ということがわかれば、諦めることもできると思います。しかし、そうした問題の難しさがわからないのであれば、決断ができないのも無理はないでしょう。
■ステ問かどうかの見分け方
それでは、「ステ問」の見分け方はどうしたら身に付くのでしょうか。それはいわゆる“問題慣れ”だと思います。問題を見た時、以前やったことがあるとか、同じような問題を見たことがあると感じれば、自信を持って前に進むことができます。問題量を解いている生徒は、このような問題にあたる可能性が高くなります。そして、見たことがない問題は、あまり出てこないでしょうから、万一出てきた場合はとりあえず後回しにすることが比較的容易に決断できるでしょう。
しかし、見た目は簡単そうなのに、やってみると意外に難しいという場合もあります。そんな時こそ、「ステ問」の対処の上手・下手で差が出ます。解き方がわかるか、答えまでのだいたいの手順が読めるようであれば、もう少し時間をかける価値はあるかもしれません。しかし、手詰まりになったと思ったら、潔く諦めるべきなのです。そして、その問題が果たして「ステ問」であったかどうか、すなわち、自分には手に負えないような難問であったかどうかを、あとでしっかり解答解説で確認することが重要です。そしてもし難問の「ステ問」であったら、よかったと安堵(あんど)するだけではなく、その問題を諦めた時の感覚、つまり、解法の方針が見えなかった時の感覚をしっかり覚えておくことです。次回、ステ問にあたった時に役立ちます。こうしたことを繰り返すことにより、「ステ問」に対する嗅覚が鋭くなってくるのです。
■スコアメーキングという考え方
「ステ問」の考え方は、もっと広げて考えれば、いわゆる「スコアメーキング」という方法論にたどり着きます。「スコアメーキング」とは、直訳すれば「点数を作る」ということですが、もともとはゴルフで使われる用語です。ゴルフではよいプレーもあれば、悪いプレーもあります。それらを組み合わせながらもよいスコアを出すことを意味します。そして、入試においてもこの「スコアメーキング」が、6年生の9月以降は特に重要になってきます。たとえば、それまでは算数の実力をつけることが目先の目的でした。できるだけ問題を多く解き、どんな問題が出ても解ける実力を付けるべく勉強してきたのです。
しかし、6年生の9月以降は状況が変わります。その時点からは、算数の力を付けることではなく、志望校に合格することが目先の、しかも最大の目標になります。そのためには、算数を勉強するよりも、たとえば苦手な社会を勉強するほうが全体の点数を上げるためにはよいかもしれません。なぜなら、得意な算数を80点から90点にするよりも、苦手な社会を40点から50点にするほうが一般的には簡単だからです。要は、同じ時間をかけるなら、一番伸びそうなところに時間をかけようということで、「ステ問」の考え方とまったく同じです。入試では、このような客観的に状況を判断できる冷静さや能力がとても大切です。しっかり身に付けて結果を残していきましょう。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 東大入試は難しい? 実は、教科書レベルの理解をもとに思考力を問う【良問】が多い東大の問題
- 問題文と設問(3)問題を読みながら設問を解く?[中学受験合格言コラム]
- 大学授業レポート│【授業レポート】倫理観(大学2年生対象)仏教学者である西本照真武蔵野大学学長が登壇「自分の軸は何か」「どうすれば人としての正しさを保てるのか」に正面から向き合う
- 記述問題の解答や、作文、意見文など、文章を書くのが苦手です[中学受験]
- 問題文と設問(3)問題を読みながら設問を解く?[中学受験合格言コラム]
- 大学授業レポート│【授業レポート】プロジェクト基礎C(大学1年生対象) まずやってみる、行動する! 1年生が「社会に新しい価値を生み出す」プロジェクトに挑む
- 類似問題や数値替え問題はすらすら解けるのに、第一印象でひらめかないと迷い込んでしまう[中学受験]
- 集中力を増す「問題文」の読み方[中学受験合格言コラム]
- 意味を体感・実感させることで「言葉」を自分のものにする授業















![記述問題の解答や、作文、意見文など、文章を書くのが苦手です[中学受験]](/_shared/img/ogp.png)