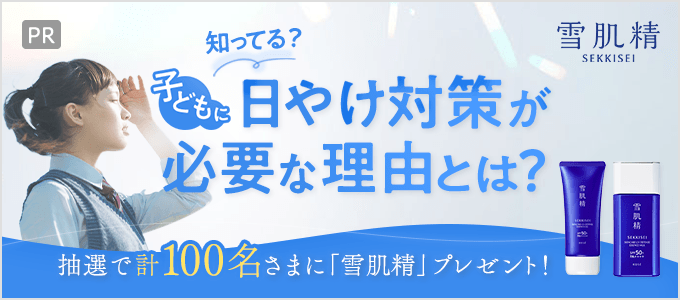筑波大学 芸術専門学群 構成専攻(1) 色彩で街づくりに寄与する[大学研究室訪問]
お気に入りに登録
日本が転換期を迎えた今、大学もまた大きく変わりつつあります。そんな時代に、大学や学部をどう選び、そこで何を学べば、お子さまの将来が明るく照らされるのでしょうか。環境色彩、環境心理について研究されている筑波大学芸術専門学群の山本早里准教授の研究室をご紹介します。今回は、先生の研究について伺いました。
■色彩で街をより魅力的に

スペイン・バルセロナ近郊のジローナの街並み
色彩によって環境をよりよくする方法について研究しています。現在取り組んでいる研究は、大きく2つあります。まず、環境における色彩の研究です。世界中の街の色彩を調査し、色彩の分布によって、私たち人間がどのような印象を受けるかということを、実験によって明らかにしています。これまで、日本だけでなく、海外で美しいと呼ばれる都市、たとえばウィーン、ザルツブルク、ボストンなどの街の色彩について調査しました。
最近、特に興味を持っているのが、街づくりに色彩が寄与しているという事例です。スペイン・バルセロナ近郊のジローナという街は、街の色彩を変えたことで、観光地としてとても有名になりました。
写真に写っている川沿いのこれらの家々は、もともと白がベースの壁で今のようなカラフルなイメージはありませんでした。ある建築家により、改修工事をする際に活気ある美しい色に塗り替えようという案が持ちかけられ、街全体の色彩を変えていったのです。これまで観光するところは、大聖堂やシナゴーグ(ユダヤ教の会堂)だったのですが、街の色彩が有名になり、多くの観光客が集まるようになりました。

外壁の色を変え、学生宿舎は人気に
色彩を変えることで、人々の印象や住み心地がよくなるということは、どの街でも可能なことです。私は、筑波大学内にある4000戸の学生宿舎の外壁の色を変える手伝いをしました。前は白やベージュなど目立たない色で、かつ単色でしたが、学生たちに愛着を持ってほしいという思いから、環境との調和も考えつつも、学生たちの住まいなのでおもしろみも感じられるような色を選びました。外壁の色を変え、学生宿舎は人気になったということを聞き、とてもうれしかったですね。
■学生にも仕事の現場を体感してもらう

ひたちBRTのプロジェクトには学生も参加
研究のもう一つの柱が、公共サインの研究です。企業や自治体との共同研究に関わり、調査、実験、分析、評価、最終的にデザインに生かすところまでを目指しています。これまで、筑波大学の西川潔先生とご一緒に、つくば市の公共サインや文京区の公共サインづくりに携わりました。サインとは、「目印」「符号」「合図」などのことを指します。なかでも公共のサインとは、その街に暮らす人々が行動するために必要な情報(地図・案内)を伝えるものです。
こうしたプロジェクトに興味のある研究室の学生には、積極的に手伝ってもらっています。たとえば、私が手がけた日立市の高速バス輸送システム(以下、ひたちBRT)のデザイン計画は、学生にも参加してもらいました。BRTとは、廃線になった鉄道路線にバスを走らせるというプロジェクトです。システムは優れていても、周辺にお住まいのかたたちに認知していただき、実際に利用していただくことが必要なため、地域活性化を目的としたデザインが求められていました。
公募で選ばれた原作をもとに、私がデザインを監修しました。コンセプトには、ひたちBRTを認知してもらうこと、地域の人々から愛着を持ってもらうこと、地域の個性を大事にすることなどを掲げました。バスだけでなく、停留所のサインも地域に合ったものをデザインしようと考え、そのサイン案を学生にも考えてもらい、一緒に作り上げました。開業以来1年間、目標乗車数もクリアしていると聞き、デザインが少しでも地域活性化の力になれたのかなと思っています。
こうしたプロジェクトに学生にも参加してもらうことで、大勢の人と作り上げることの楽しさや喜びも知ってもらいたいと思っています。また、多くの人の価値観にふれる中で感性を磨き、将来の学びや仕事に生かしてもらいたいですね。学部のころから参加し、大学院を卒業するまで仕事を手伝ってくれた学生もいます。そうした学生は、サインや公共施設のデザインに関わる企業に就職しています。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 筑波大学 芸術専門学群 構成専攻(2) 優れたデザインに必要なのは教養[大学研究室訪問]
- 薬学ってどんな学問?学ぶ内容や関連する職業についても紹介!
- 桜美林大学 リベラルアーツ学群 心理学専攻プログラム(2) 体験を重視し、主体的な学びの力を育む[大学研究室訪問]
- 「算数」と「数学」ってどう違う? ニガテをつくらないためにできることは?
- 桜美林大学 リベラルアーツ学群 心理学専攻プログラム(1) スキンシップが脳を育む[大学研究室訪問]
- 実力テストって何? 対策法は? 勉強法や定期テストとの違いをご紹介
- 東京学芸大学 教育学部 初等・中等教育教員養成課程 社会科教室 (2) 好きなことを学んで高めた専門性が社会に出たときの武器になる[大学研究室訪問 学びの先にあるもの 第2回]
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 サイバニクス研究センター(1)体を動かそうという意思によってその動きをサポート人と一体化する世界初の「ロボットスーツHAL®」を開発[大学研究室訪問]














![筑波大学 芸術専門学群 構成専攻(2) 優れたデザインに必要なのは教養[大学研究室訪問]](/_shared/img/ogp.png)
![桜美林大学 リベラルアーツ学群 心理学専攻プログラム(1) スキンシップが脳を育む[大学研究室訪問]](/img_o/kj/juken/201502/20150223-1.jpg)