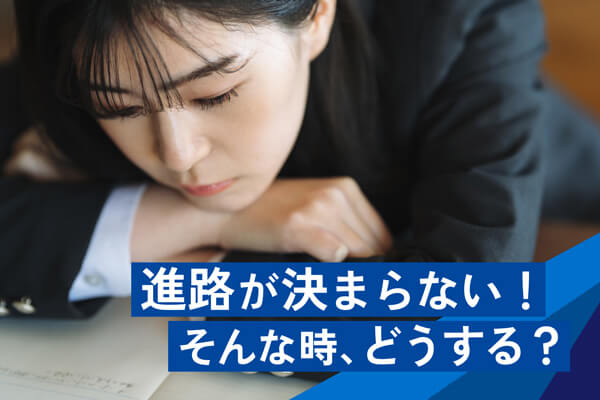「まったくわからない」 そんな時のヒントの出し方を専門家が指南
お気に入りに登録
 習ったことが増えて問題が複合的になることで、ちんぷんかんぷんになってしまうという小学5年生女子の子どもを持つ保護者。ヒントの出し方に迷っているという。平山教育研究所の小泉浩明氏がアドバイスをくれた。
習ったことが増えて問題が複合的になることで、ちんぷんかんぷんになってしまうという小学5年生女子の子どもを持つ保護者。ヒントの出し方に迷っているという。平山教育研究所の小泉浩明氏がアドバイスをくれた。
***
【質問】
算数の問題で、1つの解き方で解ける問題はすらすら解けるのですが、知識を組み合わせて解く応用問題になると、着眼点すら見つけられないことがあります。解き方のヒントを与える時によい方法があれば教えてください。(小5女子の母親)
【小泉氏からのアドバイス】
「ヒント」を与えるのは、解いている本人に考えてもらうためです。ヒントを与えずにいれば、解くことを諦めてしまうかもしれません。解き方そのものを教えてしまっては、自分の頭で考えることをやめてしまうでしょう。適切なヒントをピンポイントで与えることは大切なことですが、非常に難しいことでもあります。しかし、最適なヒントが出された時、問題は見事に解け、達成感や自信をお子さまに与えることができるのです。
算数でヒントを与えるということは、次に「何を(するのか)?」「どこに(するのか)?」「どのように(するのか)?」「なぜ・何のために(するのか)?」などを教えるということであり、これらが「ヒントの種類」です。“どのヒントを出すか?”がポイントになります。
与えることで次の手順に進め、自分の頭を最大限に使って考えるようなものが、望ましいヒントといえます。小出しにしながら、どの程度のヒントがお子さまにちょうどよいか様子を見ていくとよいでしょう。なお、「なぜ・何のために?」を単独で出すのがいちばん難しいヒントだと思います。「なぜ・何のために?」をヒントとして与えることは、“解法の方向性”を示すことだからです。「なぜ・何のために?」をヒントとして出すには、ヒントを出すほうもある程度勉強しておく必要はありますが、やさしい入試問題レベルであればご家庭でも対応できると思います。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 夏休みに勉強の計画を立てる意義|高校生の受験勉強におすすめな計画方法
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- 【高校受験】キーワードは「併願だって行きたい高校!」受験校選びのポイントは?
- 【高校受験】第1志望の入試日まで、あと何日?優先順位のつけかたと保護者のサポート法
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 記述問題は比較的点数がとれるのに、選択問題だと間違いが多い[中学受験]
- 1学期のE判定…保護者は信じていれば大丈夫?
- クラス替え 仲のよい友達とクラスが分かれて元気がない我が子…何と声をかける?
- 【Q&A】志望校合格に向けた受験勉強はいつから始める?高校受験の勉強時間や年間スケジュールは













![「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201003/20100309-1.jpg)