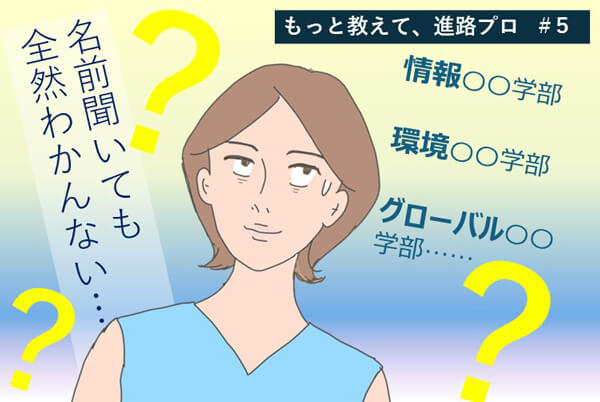「選ぶ」ことと「ステル」こと[中学受験]
お気に入りに登録
目標設定が明確で、目標達成のためのモチベーションも十分にあれば、あとはそのための「手段」を選べば良い。しかしこの「手段」に関する情報もあふれているため、選択に困る場合が多い。たとえば「塾選び」に悩む場合などである。
塾はそれぞれの方針で、さまざまな形態で運営されている。大手塾から個人塾、通塾日数の多い・少ないなど実に多様である。だからこそ子どもに合うかどうか、学力を伸ばしてくれるかどうかなど選択に迷う。入塾する時はもちろん、塾を決めて勉強を始めてからもいろいろ迷う。本当にこのままその塾で勉強させて良いのか、他の塾に移るほうが良いのではないかといった迷いである。2月に出てくる新年度の合格実績という「情報」を得るたびに、新たな迷いが増すものである。特に子どもの目指す学校の合格実績があまり良くない時などはなおさらであろう。
塾を変わるというのは非常に重大な決断であるから、相談を受けた時はさまざまなデータを検討しながら考えていく。特に「成績の変化(偏差値の変化)」が重要な判断材料になる場合が多い。たとえば少しずつでも成績が上昇している時は、塾を変わることは中止すべきであるとか、少なくとももう少し様子を見るようにお話する。偏差値は相対的なものであり、その上昇は他の受験生に比べて学力が増加していることを意味する。「良い状態の時には変えない」が、受験におけるセオリーの一つであろう。
ところで、受験における「手段」で悩むのは、「選ぶ」ことよりも「ステル」ことにあるかもしれない。
志望校という目標に向かう「手段」は、それこそ無限にある。であるからこそ迷い、より効率的で、成功しそうな手段を選ぼうとする。これは人情であろう。成功した他の人の例を信じ、あるいは情報雑誌が良いとすすめていることを取り入れたくなる。しかし、ここで心しておきたいことは、「目標到達のためにぜひとも必要なことなのか?」あるいは「子どもに必要なことなのか?」という視点である。
特に6年生も後半になってくると、実に多くの学習をこなさなくてはならない状況になる。ここで多くの生徒は「すべきこと」と、「残された時間」のアンバランスに苦しむのだが、この時「目標達成のためには何をすべきか?」を意識している保護者であれば、あふれる情報の中から、正しい手段を選ぶことが可能になってくる。
何かを選ぶということは、相対的に必要のないものを「ステル」ということなのだが、実はこの「ステル」という行為にはかなり怖いものがある。しかし子どもがその時必要なものは何かを考えれば、答えは自然に出てくる。
たとえば志望校の入試では国語に記述問題が多く出てくるのだが、6年生になってもまだまだ記述に苦手意識があるとしよう。当然、何らかの方法で苦手を解消する必要がある。待っていても誰も、何も解消してはくれない。記述問題の苦手を解消するために、算数の学習の時間が取られることになるかもしれない。しかしそれが子どもに必要であるならば、たとえば算数の学習時間をつぶしてでも国語の記述に力を入れなければならない。何かを「ステル」ことなく国語を「選ぶ」こと、つまりすべてを「選ぶ」ことは、パニックに陥る可能性があるので避けるべきであろう。
塾はそれぞれの方針で、さまざまな形態で運営されている。大手塾から個人塾、通塾日数の多い・少ないなど実に多様である。だからこそ子どもに合うかどうか、学力を伸ばしてくれるかどうかなど選択に迷う。入塾する時はもちろん、塾を決めて勉強を始めてからもいろいろ迷う。本当にこのままその塾で勉強させて良いのか、他の塾に移るほうが良いのではないかといった迷いである。2月に出てくる新年度の合格実績という「情報」を得るたびに、新たな迷いが増すものである。特に子どもの目指す学校の合格実績があまり良くない時などはなおさらであろう。
塾を変わるというのは非常に重大な決断であるから、相談を受けた時はさまざまなデータを検討しながら考えていく。特に「成績の変化(偏差値の変化)」が重要な判断材料になる場合が多い。たとえば少しずつでも成績が上昇している時は、塾を変わることは中止すべきであるとか、少なくとももう少し様子を見るようにお話する。偏差値は相対的なものであり、その上昇は他の受験生に比べて学力が増加していることを意味する。「良い状態の時には変えない」が、受験におけるセオリーの一つであろう。
ところで、受験における「手段」で悩むのは、「選ぶ」ことよりも「ステル」ことにあるかもしれない。
志望校という目標に向かう「手段」は、それこそ無限にある。であるからこそ迷い、より効率的で、成功しそうな手段を選ぼうとする。これは人情であろう。成功した他の人の例を信じ、あるいは情報雑誌が良いとすすめていることを取り入れたくなる。しかし、ここで心しておきたいことは、「目標到達のためにぜひとも必要なことなのか?」あるいは「子どもに必要なことなのか?」という視点である。
特に6年生も後半になってくると、実に多くの学習をこなさなくてはならない状況になる。ここで多くの生徒は「すべきこと」と、「残された時間」のアンバランスに苦しむのだが、この時「目標達成のためには何をすべきか?」を意識している保護者であれば、あふれる情報の中から、正しい手段を選ぶことが可能になってくる。
何かを選ぶということは、相対的に必要のないものを「ステル」ということなのだが、実はこの「ステル」という行為にはかなり怖いものがある。しかし子どもがその時必要なものは何かを考えれば、答えは自然に出てくる。
たとえば志望校の入試では国語に記述問題が多く出てくるのだが、6年生になってもまだまだ記述に苦手意識があるとしよう。当然、何らかの方法で苦手を解消する必要がある。待っていても誰も、何も解消してはくれない。記述問題の苦手を解消するために、算数の学習の時間が取られることになるかもしれない。しかしそれが子どもに必要であるならば、たとえば算数の学習時間をつぶしてでも国語の記述に力を入れなければならない。何かを「ステル」ことなく国語を「選ぶ」こと、つまりすべてを「選ぶ」ことは、パニックに陥る可能性があるので避けるべきであろう。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 入学祝いのお返しは、いつ何を贈ればいい?入学内祝いの相場とマナー
- 「選ぶ」ことと「ステル」こと[中学受験合格言コラム]
- 教育フォーカス│新課程における新しい学びとは│[第3回]自ら考える思考力を育むために大切なこと[2/4]
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第11回 国立大本番でのハプニング!
- 高校生が大切だと考える5つのルールとは?【高校生のスマホの使い方調査】
- 教育フォーカス│新課程における新しい学びとは│[第3回]自ら考える思考力を育むために大切なこと[3/4]
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第6回 併願大、決定!
- 小学校のクラス替えはどう決める?保護者の要望は通る?元小学校教員に聞いた
- 教育フォーカス│【特集16】新課程における新しい学びとは