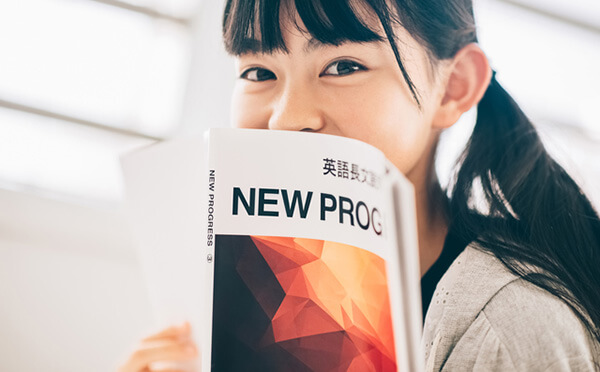記述問題対策について[中学受験]
お気に入りに登録
今年の入試に関して「記述問題が増加した」と前回述べたが、超上位校を中心に増えているのであり、上位校や中堅校はほぼ昨年並みであった。具体的にはお子さまの志望校の過去問を入手し、昨年の問題と比較してみると良いだろう。やり方としては記述問題の数(例:昨年は2問だったが今年は4問になったなど)や制限字数(例:昨年は15字以内で述べる問題と30字以内の問題で合計45字だったが、今年は30字以内の問題が2問で合計60字になったなど)を比べ、それらの増減を比較するのである。記述問題数は増加したが、制限字数が大幅に減少した場合などは結果として増減無しと考えるべきであろう。なお、「10字に満たない字数制限の記述問題」や「抜き出し問題(「本文から抜き出せ」という問題)」は、私は原則として記述問題にはカウントしないことにしている。
さて志望校の入試問題を分析してみて、「もともと記述問題が多い」とか「記述問題が年々増加している」という場合は、とにかく記述問題対策が重要になってくる。模擬試験や実力試験で、記述問題の解答欄がいつも空白、あるいは常にお情けの部分点しかもらえていない場合は、緊急に手を打つ必要がある。「そのうち書けるようになる……」などと、自然に改善することを期待すべきではない。何度も記述の練習を繰り返し行うことで、徐々にうまい答案が書けるようになるのである。ただし、記述練習を行う時は、守るべきポイントがいくつかある。
たとえば「何を書くべきか」という原則は、最初に子どもに教えるべきであろう。この原則を教えることなく、「とにかく何でも良いから、答案を埋めなさい」では子どもが少々気の毒である。「書くべきもの」は解答欄の大きさや制限字数にもよるが、問われているもの(これを「キーワード」と呼ぶことにする)とその理由などである。たとえば「~の気持ちが読み取れますか」であれば、「やさしい(気持ち)」とか「~をうらやむ(気持ち)」がキーワードになる。そして「なぜやさしい(気持ち)」になったかの理由も、書く必要があるということだ。この「理由+キーワード」という文の構造を知っているだけで、かなり得点が違ってくる。
それからもう一つ心がけたいのは、模範解答の扱い方。模範解答は参考にすべきだが、「その通りに書く」必要は必ずしもないということである。なぜなら、模範解答とは国語の先生たちが、かなりの時間をかけて(他の人から文句が出ないように)、十分に考えて作った解答であるからだ。そんなすばらしい解答を、小学生の子どもが時間内にスラスラと書けることを期待するのはやはり酷であろう。実際問題として、子どもの答案と模範解答を比べてみて、「ここまでは書けないよなあ……」ということは多くある。そんな場合、模範解答のようなすばらしい文を期待すると、子どもは「とても無理です……」と萎縮(いしゅく)してしまう。そうではなくて、内容が同じであれば、どんなに幼い表現であろうと「合格点!」と認めてあげることが大切だ。これをしないと、書き出す勇気が阻害されてしまうことがあるから十分注意したい。そして自分なりの答案が書けるようになったら、「この表現は、模範解答にあるような表現のほうがベターだね」という次のステップとしての指導を行い、徐々に表現力を上げていくことが大切であろう。
さて志望校の入試問題を分析してみて、「もともと記述問題が多い」とか「記述問題が年々増加している」という場合は、とにかく記述問題対策が重要になってくる。模擬試験や実力試験で、記述問題の解答欄がいつも空白、あるいは常にお情けの部分点しかもらえていない場合は、緊急に手を打つ必要がある。「そのうち書けるようになる……」などと、自然に改善することを期待すべきではない。何度も記述の練習を繰り返し行うことで、徐々にうまい答案が書けるようになるのである。ただし、記述練習を行う時は、守るべきポイントがいくつかある。
たとえば「何を書くべきか」という原則は、最初に子どもに教えるべきであろう。この原則を教えることなく、「とにかく何でも良いから、答案を埋めなさい」では子どもが少々気の毒である。「書くべきもの」は解答欄の大きさや制限字数にもよるが、問われているもの(これを「キーワード」と呼ぶことにする)とその理由などである。たとえば「~の気持ちが読み取れますか」であれば、「やさしい(気持ち)」とか「~をうらやむ(気持ち)」がキーワードになる。そして「なぜやさしい(気持ち)」になったかの理由も、書く必要があるということだ。この「理由+キーワード」という文の構造を知っているだけで、かなり得点が違ってくる。
それからもう一つ心がけたいのは、模範解答の扱い方。模範解答は参考にすべきだが、「その通りに書く」必要は必ずしもないということである。なぜなら、模範解答とは国語の先生たちが、かなりの時間をかけて(他の人から文句が出ないように)、十分に考えて作った解答であるからだ。そんなすばらしい解答を、小学生の子どもが時間内にスラスラと書けることを期待するのはやはり酷であろう。実際問題として、子どもの答案と模範解答を比べてみて、「ここまでは書けないよなあ……」ということは多くある。そんな場合、模範解答のようなすばらしい文を期待すると、子どもは「とても無理です……」と萎縮(いしゅく)してしまう。そうではなくて、内容が同じであれば、どんなに幼い表現であろうと「合格点!」と認めてあげることが大切だ。これをしないと、書き出す勇気が阻害されてしまうことがあるから十分注意したい。そして自分なりの答案が書けるようになったら、「この表現は、模範解答にあるような表現のほうがベターだね」という次のステップとしての指導を行い、徐々に表現力を上げていくことが大切であろう。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- 今からはじめる高校入試対策!数学の証明問題で意識すべき3ステップとは?【記述力対策〜数学編〜】
- 小学校のクラス替えはどう決める?保護者の要望は通る?元小学校教員に聞いた
- 入学祝いのお返しは、いつ何を贈ればいい?入学内祝いの相場とマナー
- 今からはじめる高校入試対策!得点アップにつながる英作文の勉強法 出題傾向と問題演習のコツまで 【記述力対策~英語編~】
- 選択肢を選ぶ問題で、間違いではないが正解のほうがより適切な場合の指導をどうすればよいのでしょうか[中学受験]
- 入学式にどんなバッグを持っていけばいい?サブバッグは?持ち物とマナーを知っておこう
- 記述問題対策について[中学受験合格言コラム]
- 子どもの意思を尊重するつもりが甘やかしになっている?! 保護者が気にしておくべき2つのこと