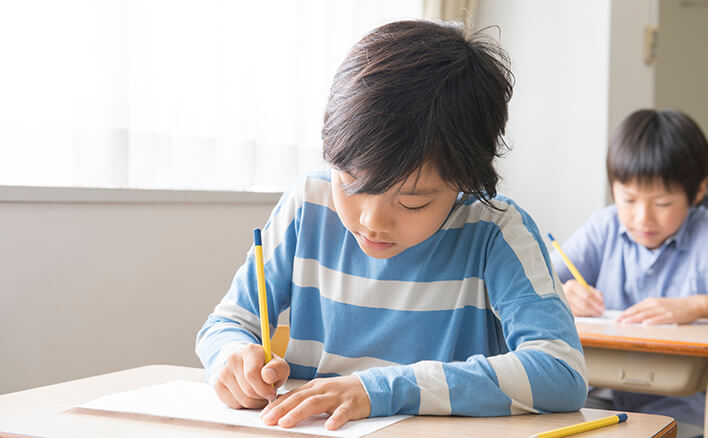小中学校の学習状況調査に見る、アクティブ・ラーニングの効果とは
お気に入りに登録
 次期学習指導要領の目玉になっている「アクティブ・ラーニング」(課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び、AL)に対し、小中学校の授業は既に十分アクティブだという見方がある。「実際に、小中学校ではALに当たる学習形態が広がっていることを示す調査結果もある」という教育ジャーナリストの渡辺敦司氏に、ベネッセ教育情報サイトが話を聞いた。
次期学習指導要領の目玉になっている「アクティブ・ラーニング」(課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び、AL)に対し、小中学校の授業は既に十分アクティブだという見方がある。「実際に、小中学校ではALに当たる学習形態が広がっていることを示す調査結果もある」という教育ジャーナリストの渡辺敦司氏に、ベネッセ教育情報サイトが話を聞いた。
***
2015(平成27)年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の学校質問紙調査では、前年度までの授業で「児童生徒自ら学級やグループで課題を設定し、その解決に向けて話し合い、まとめ、表現するなどの学習活動」を取り入れたかどうかをたずねています。これに対し、「よく行った」と答えた学校の平均正答率は、一部の問題を除いて60~70%台の高率です。こうした学習活動をする学校ほど、ペーパーテストの成績もよくなる傾向があるという結果が出ていますから、知識の習得にもALは有効であることが証明された格好です。
このような学習活動は、現行の学習指導要領において「言語活動」として重視されていますが、あくまでも各教科で育もうとする思考力・判断力・表現力を身に付けさせるためのものです。一方、次期学習指導要領では、教科を超えて思考力・判断力・表現力を育成するために、
(1) 習得・活用・探究のプロセスを通じた「深い学び」
(2) 他者との協働などを通じて自分の考えを広げ、深める「対話的な学び」
(3) 見通しを持って粘り強く取り組み、自分の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」
にまで深めることを、今回あえてALという言葉を使って打ち出しています。
小中学校ではAL自体が既に各教科の言語活動として行われており、あとは一工夫を加えれば、子どもたちの資質・能力をさらに高めることは十分可能だというわけです。問題は、依然として知識偏重・一方通行の講義中心であるとされる、高校の授業といえるでしょう。
出典:「アクティブ・ラーニング」、実は既に行われている? -ベネッセ教育情報サイト
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 小中学生の学びに関する実態調査 速報版 [2014]
- アクティブ・ラーニング、やれば既に効果 全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)
- PTA広報誌(紙)、全体を読む保護者は約6割
- 東京大学社会科学研究所・ ベネッセ教育総合研究所共同研究 「子どもの生活と学びに関する親子調査2018」
- 第10回 全国学力・学習状況調査に見る「論理的思考力」
- 小学校の保護者会で行われる内容って?仕事を休まなければならない行事や出来事リストも公開!
- 学ぶことの目的と意味を大切にする社会の授業[こんな先生に教えてほしい]
- 「全国学力・学習状況調査」における課題の「活用」って何?
- 9割以上の保護者は子どもに新聞を読んでほしいと思っている!