情報化社会とは? AI時代を生きる子どもが身につけたい力と保護者に求められる姿勢
- 育児・子育て

急速に進む情報化社会を生きていく子どもたちには、どのような力が求められるのでしょうか。その答えを考えるには、まず情報化社会の定義やこれからの進展を正しく理解することが重要です。
広島工業大学 情報学部の安藤明伸先生に、情報化社会の本質や子どもたちが身に付けるべき力、そして保護者が果たすべき役割について伺いました。
情報化社会には、2つの段階がある
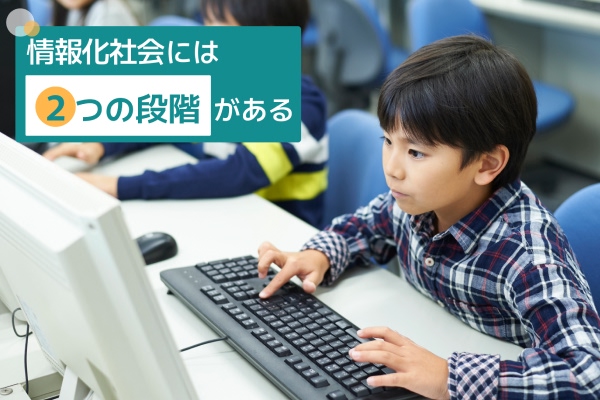
ーー 情報化社会とはどのような社会なのでしょうか。
情報化社会とは、情報を活用して価値を創り出す社会のことです。ビジネスにおいても、従来のアナログな工業生産だけでなく、デジタルな情報生産や収集、処理が大きな割合を占めるようになっています。
情報化社会は、2つの段階で進化してきました。1つ目は、デジタル化による進化です。Society4.0とも呼ばれ、通信技術の発達でさまざまなことがアナログからデジタルに移行し、利便性が格段に高まりました。
2つ目は、AI技術の急速な発展による進化です。人では処理しきれないほどの大量のデータと共存する現在は、実世界とサイバー空間とが高度に融合されたSociety5.0へ移行しつつある段階です。
ーー 処理しきれないほどの膨大なデータと共存というと、どこか怖さも感じてしまいます。
私たちは既に努力だけでは処理しきれない情報の渦の中に生きています。多くのニュースサイト、SNS、動画サイト等多くのチャネルで流れてくる情報を扱うことは、もう人の努力では手に負えなくなっています。膨大なデータを処理するのはもはや人間ではありません。AIを用いたシステムやアプリが処理し、自分の目的や嗜好に合ったニュースを選別・予測し、人間の意思決定を補助します。
ここで大切なのは、AIがデータを処理するといっても、それらは人間が何らかの意図をもって作ったプログラムで動いている点です。この大前提をおさえずに、情報化社会を表面的にとらえると「得体がしれなくて怖い」という不安感だけが大きくなります。2020年度から小学校でのプログラミング教育が必修化されたことで、「コンピュータを『魔法の箱』にさせない」ために全国の学校現場では試行錯誤しながらもプログラミング教育を推進しつつあり、正しい理解を促す基盤が整いつつあると言えるのではないでしょうか。
情報化社会の進展が子どもたちの未来に与える3つの影響
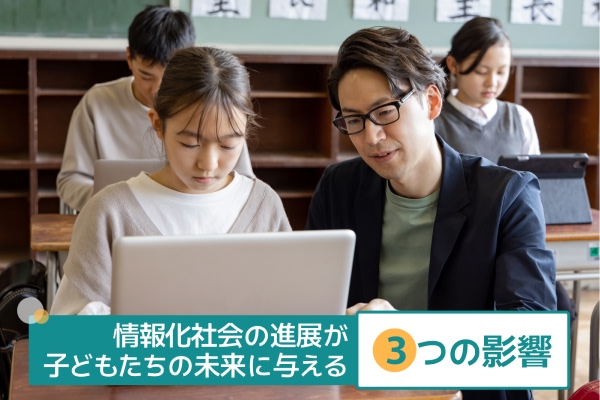
ーー 情報化社会の進展は、子どもたちの将来の仕事や社会生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
まず前提として、「AIネイティブ」が生まれてくるということを、AIが今のように普及していなかった時代を生きてきた我々大人世代が理解しておくことが重要です。AIが当たり前に存在する環境で育つAIネイティブは、大人世代とは価値観や考え方そのものが大きく変わるはずです。大人世代が持つ古い価値観を持ち出して対応することは、子どもたちの成長の芽を摘みかねません。
AI技術の発展による情報化社会の進展は、子どもたちの将来に3つの影響をもたらすでしょう。
1つ目は、AIを適切に活用するスキルが評価されるようになるでしょう。これまでは、人間自身がスキルを高めることで評価されてきましたが、AIという道具をうまく使えるかが問われるようになります。たとえばAIを使って作文を書くと、現在のところは、AIを使っているというだけでネガティブに評価される面がありますが、今後はAIの活用を当然のものとして評価する価値観が出てくるのではないでしょうか。もちろん従来からの自分の力だけで作文を書くことが大切であることは変わらないでしょう。しかし、自分で書くだけでなく、自分が何を書きたいのか、どのように書きたいのか、誰に対して書きたいのかなど自分が書きたいことを言語化し、AIに書かせる、という力にも価値がおかれるのではないでしょうか。
逆にいうと、AIを使いこなせなければ、表現の幅や生産性が上げられない場面が増え、生活や職業選択に困難が生じるリスクも大きくなるといえるでしょう。
2つ目は、より質の高い仕事への専念が求められるようになるでしょう。ルーティンワークのようなAIで代替できることから解放されるということは、創造的で高度な仕事に集中できる環境を手に入れるということです。この変化は、既に教育現場でも事例が生まれつつあります。たとえば、生徒の英作文の添削であれば、AIが基本構造や文法をあらかじめチェックし、教師は内容に関する質的なフィードバックに専念するような取り組みも見られます。
3つ目は、ファクトチェックの重要性が増すということです。AIが生成する情報は、必ずしも正確なわけではなく、人間なら絶対しないようなミスを犯すこともあります。そのため、生成されたものをうのみにするだけでなく、批判的に検証して見極めるファクトチェックを常に行う態度が求められます。
ーー 3つの影響に対応できるのか不安に感じてしまいます。
適切に対応するには、AIの仕組みの理解が欠かせません。AIはデータとプログラムによる動作の仕組みなので、データが違えば結果が変わるし、同じデータでも何を学習させたのかということやプログラムによって結果が変わります。仕組みを理解すれば、AIのメリットだけでなく、デメリットや限界も踏まえて一歩引いた客観的な視点で判断できるようになります。そうすれば、やみくもにAIに振り回されず、冷静にAIを使いこなすことができるようになるでしょう。
AIの活用というと、プロンプトと呼ばれるAIへの指示の出し方のテクニックばかりが先行していますが、それでは表面的な理解にとどまり、懸念が残ります。
子どもたちが身に付けておきたい3つの力

ーー 情報化社会を生きていく子どもたちが身に付けておくと良い力はどういったものでしょうか?
「デジタルな言語活動としてのプログラミング」「データを活用する力」「情報モラルのアップデート」の3つです。
1つ目の「デジタルな言語活動としてのプログラミング」とは、プログラミング言語を用いてコードを書くというだけではなく、プログラミングをとおして、コンピュータと効果的なコミュニケーションをとるための思考やスキルをコンピュータの特徴を押さえながら体験的に理解することです。
ーー コンピュータとのコミュニケーションとはどういうことでしょうか。
コンピュータに指示をして望む結果を得ることです。これは、普段、私たちが人間同士で行っているアナログコミュニケーションと大きく異なります。アナログコミュニケーションでは、聞き手は行間や空気を読んで話し手の意図を解釈していきますが、対コンピュータではそうはいきません。曖昧な指示ではまったく伝わらないんですね。解釈の余地のないほど明確かつ、具体的な指示が必要です。
たとえば「ライトをぴかぴかさせる」ということを指示する場合、「ライトをつけたあと、消すことを繰り返す」というだけでは不十分。何秒光らせたあとに、何秒消して、また何秒光らせるというように、精緻(せいち)化・数量化した指示が必要です。試行錯誤しながら、正確な指示をしていく中で、コンピュータの特性を体感的につかめるようになります。これは、コンピュータに指示をする体験以外からは決して理解することはできません。そして、これらの体験はより早期から子どもに積ませることが求められます。
ーー なぜでしょうか。
ChatGPTなどの生成AIの発達で、状況が変わってきているためです。コンピュータは曖昧な指示では動かないものですが、生成AIは「いい感じにきれいにまとめて」「小学生でもわかるように簡単にして」といった曖昧な指示でもアウトプットしてしまいます。
これでは、コンピュータの仕組みや特性について十分な理解が進まない事態になりかねません。だからこそ、デジタルな言語活動としてのプログラミングを早い段階から始め、現状より早期からアナログとデジタルの対比に気付かせることが求められます。
コンピュータの仕組みや特性を体感的につかむことができれば、過剰な期待を避け、現実的、効果的な使い方ができるようになるでしょう。
ーー 子どもたちが身に付けておきたい力の2つ目 「データを活用する力」、3つ目の「情報モラルのアップデート」についても教えてください。
2つ目の「データを活用する力」とは、データが意味していることを読み解き、データの特性を踏まえて意思決定を行うデータリテラシーのことです。これからの社会では、データに基づく意思決定が今以上に重要になります。これは経験に基づく主観的な判断が少なくなかったこれまでの社会とは大きく異なります。
導き出されたデータが想定と異なる結果となることもあるでしょう。だからといって「データがこういっているから」という単純な意思決定だけでは不十分ですし、データを無視した意思決定では意味がありません。データを材料として、さまざまな条件から最適解をいかに導き出すか。このスキルは、データを活用するトレーニングを積むことで養われます。
プログラミングとデータ活用ができるようになってはじめて、DX(デジタルトランスフォーメーション)による社会の変革は進みます。ICT機器や通信技術が発達するだけでは進展しません。プログラミングだけでなく、データ活用についての教育も合わせて進むことが望まれます。
3つ目の「情報モラルのアップデート」とは、デジタル社会の変化に応じた自分自身の情報モラルの概念を更新するということです。たとえば、以前は情報機器やインターネットを使うとトラブルになるからできるだけ使わせないようにする、という考え方が強かった時期がありました。しかし、子どもたちが学校や家庭から一歩外に出ればすぐ手が届くのです。学校や子育ての中で、実際に使い、試し、時には小さな失敗もし、そして失敗した時にどうするのか、なぜそうなってしまったのか学ぶことこそが、デジタル社会の中での自立になります。リテラシーや知識・技能を身に付けて、責任を持った使い方や情報発信をしていくマインドセットが求められます。
保護者に求められるのは自分の価値観・常識だけで判断しない姿勢

ーー 子どもが情報化社会を生きる力を身に付けるために、保護者はどのようなサポートが必要なのでしょうか。
保護者世代は、AIがまだ身近でなかったアナログな社会の中で育ってきています。まずは、自分の価値観が古くなり、陳腐化しているかもしれない可能性を認識する謙虚さが大切です。デジタルネイティブである子どものほうが情報化社会にマッチした考え方をしているかもしれません。デジタルに関わるお子さまの言動や考え方を、自分の価値観・常識で判断しないようにしたいですね。成長の芽を摘んでしまうことになりかねません。
これは、これまでの経験を否定しているのではありません。むしろ今の保護者世代が経験してきた時間はもう2度と訪れない貴重な体験を積んだ時代です。その経験の価値観やノスタルジーだけに留まってはいけないということです。そのためには、保護者も情報化社会について学び、知識や価値観をアップデートすることが求められます。子どもと同じデジタルツールを使って体験を共有するのも有効でしょう。使ってみてはじめて、メリットやリスクに気付くことも多いものです。イメージ先行の判断や、SNS等での聞きかじりの知識だけでわかった気になるのは危険です。
また、リスクを未然に防ぐことばかりに目が行きがちですが、トラブルが起きてしまった時の初動対応についての教育も重要です。お子さまと一緒に学ぶというスタンスで臨めるといいですね。
まとめ & 実践 TIPS
子どもたちは、急速な情報化社会の進展の中で生きていきます。生成AIやデジタル機器を活用することは、ついリスクが気になってしまいますが、それだけでは情報化社会を生き抜くスキルは身に付けられません。保護者も共に学び、支えていけるといいですね。
編集協力/岡聡子、Cue`s inc.
- 育児・子育て














