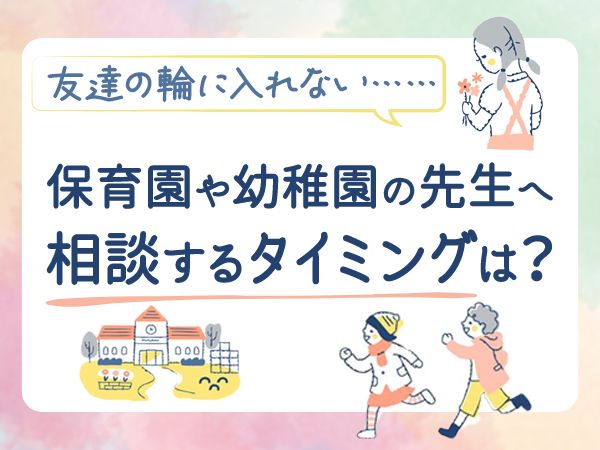鬼ごっこで身に付く力とは?ケース別の遊び方のアイデアやルールの工夫も
お気に入りに登録
- 遊び・ゲーム

子どもたちが大好きな遊びである鬼ごっこ。ただ楽しいだけではなく、実は成長に欠かせないさまざまな力を育むことができます。年齢ごとに身に付く力や、ケース別の遊び方の工夫について、和洋女子大学の佐藤有香教授にお話を伺いました。
年齢別!鬼ごっこで身に付く力とメリット

まずは鬼ごっこでどんな力が育まれるのか、どのようなメリットがあるのか、年齢ごとに見ていきましょう。
1~2歳:追いかけっこを楽しみながら信頼関係を築く
この時期の子どもは、鬼ごっこのルールを理解するのは難しく、「逃げる・追いかける」単純な動きややり取りを楽しむ段階です。先生や保護者、きょうだいとマンツーマンで追いかけっこをすることで、信頼関係や愛着形成を育むことにつながります。情緒の安定にもつながるでしょう。
3歳以上:運動能力・判断力が向上
3歳を過ぎると、少しずつ体の動きがスムーズになり、簡単なルールを理解しながら鬼ごっこを楽しめるようになります。
逃げる、止まる、方向転換するといった動きを繰り返すことで、瞬発力やバランス感覚など運動能力全般が発達していきます。ルールに基づいて「どう逃げるのか」「どうしたらつかまりにくいか?」を考えながら遊ぶことで、判断力も養われます。
5〜6歳(年長):戦略性やチームワークが身に付く
年長児になると、「どろけい」など、より高度な遊び方ができるようになります。鬼になって動きを予測したり、仲間と協力して作戦を考えたり、協力して逃げたりすることで、戦略的な考え方やチームワーク、協調性が育まれます。
また、異年齢の子がいる、運動が苦手な子がいるといった状況に応じて、自分たちでルールを工夫しながら遊びを発展させる力も育まれます。
意外と複雑な鬼ごっこのルール、どう理解できるようにする?

鬼ごっこは、集団遊びであるため、ルールを理解していないと楽しめません。ルールがわからないと、遊びが成り立たないどころか、いざこざになってしまうこともあります。お子さまにとっては、鬼ごっこが「ルールに従って遊ぶ初めての遊び」かもしれませんね。
とはいえ、鬼ごっこのルールは意外と複雑なので、ある程度の理解力が必要です。「逃げる」「追いかける」だけの単純な遊びに見えても、状況によって役割が変化するため、次のようなことを考えながら遊ぶ必要があります。
・誰が鬼か
・つかまらないためにどうすればいいか
・つかまったらどうなるか(鬼になるなど、役割が変わることもある)
・つかまったあとの復活の方法(氷鬼など)
こうして見ると、意外と複雑なことに気付かされますよね。しかし、ルールが複雑だからといって、長々と説明しても子どもには伝わりにくいもの。途中で飽きてしまうこともあるでしょう。大人が子どもの理解度を考えながら、遊びの中で自然にルールを覚えられるようにサポートしてあげることが大切です。次のような工夫を取り入れてみましょう。
鬼ごっこのルールを理解しやすくするための工夫・アイデア
・鬼のお面を使うなど、誰が鬼か視覚的にわかるようにする。
・物語と鬼ごっこを連動させる。
◦例)
▪『おおかみと7ひきのこやぎ』の絵本を読んだあと、鬼ごっこの設定を伝える。
▪大人がおおかみ(鬼)、子どもたちがこやぎ。
▪こやぎが「今何時?」とおおかみに聞き、おおかみが「12時だよ!」と答えたら逃げる。
▪おおかみは「12時」の合図でこやぎをつかまえにいく。
こんな時はどうする?年齢やケース別の遊び方の工夫

鬼ごっこは、さまざまな子どもが一緒になって遊べるのが魅力です。しかし、その分、遊び方の工夫も求められます。異年齢の子どもが交ざって遊ぶ場合や、走るのが苦手な子どもがいる場合など、さまざまなケースが考えられますよね。ケース別の遊び方の工夫を紹介します。
年齢別のおすすめ鬼ごっこ
・1~2歳:鬼ごっこというより、追いかけっこでマンツーマンの関係性を大切にしましょう。先生や親が鬼になり、子どもは逃げるだけでも十分楽しめます。
・3~4歳:普通の鬼ごっこに慣れると「つかまえたい」「鬼になりたい」という気持ちが強くなります。そのため、鬼になる機会をつくることがおすすめ。鬼をみんなでつかまえるものや、鬼が増える「増え鬼」などを取り入れてみてください。
・5歳以上:個人で逃げるだけでなく、チームで作戦を考えながら協力して遊べる「どろけい」などがおすすめです。
走るのが苦手な子どもがいる場合
走らなくても楽しめるルールを導入してみましょう。たとえば、次のような遊びがあります。
・お尻歩き鬼:お尻を床につけ動いて逃げる鬼ごっこ。
・電車鬼:前の人の肩につかまって電車のようにチームで逃げる。
・ひょうたん鬼:地面に描いたひょうたんの絵の中を逃げる鬼ごっこ。鬼はひょうたんの外から追いかける。
鬼になるのが苦手な子どもがいる場合
年齢が低い場合、鬼になるのを怖がる子どもも少なくありません。先生と一緒に鬼になったり、鬼を2人以上にしたりすることで、鬼になる子どもの心理的負担を減らしてあげてみてください。
異年齢が交ざって遊ぶ場合
異年齢の子どもが一緒に遊ぶ際、年齢が上の子に合わせると小さい子どもにとって危険になり、逆に小さい子どもに合わせると大きい子どもが物足りなく感じることも。次のような工夫を取り入れると、年齢差があっても楽しく遊べます。
・年長の子どもと年少の子どもでペアになる:上の子どもが下の子どもを守りながら逃げることで、スピード調整ができる。
・ハンデをつける
◦年齢が上の子どもは歩いて逃げたり、追いかけたりする。
◦年齢が上の子どもはお尻歩き、小さい子どもは歩いて逃げる。
いつもと違うアレンジ鬼ごっこがしたい場合
鬼ごっこは、さまざまなアレンジができるのがいいところ。設定に工夫をしたり、他の遊びと組み合わせるのもいいですね。子どもたちのアイデアをもとに、新しい遊び方をつくるのもおすすめです。たとえば、次のような遊び方を参考にしてみてください。
・しっぽ取り
◦小さい子ども向け:鬼役の大人が、おなかまわりにたくさんのしっぽをつける。鬼以外の子どもは、大人のしっぽをとる。
◦大きい子ども向け:鬼も逃げる子どももしっぽをつけ、自分のしっぽを守りながら相手のしっぽをとる。どろけいのような集団戦にするのもおすすめ。
・手つなぎ鬼
◦鬼につかまったら、鬼と手をつないで一緒に追いかける。鬼がどんどん増えていく。
・もの鬼
◦鬼が「花」などの言葉を言い、言われた「もの」に触れていないと鬼につかまる。色鬼のアレンジバージョン。
より楽しく、安全に遊ぶために

鬼ごっこは、子どもたちが思いきり体を動かして楽しめる遊びですが、安全に配慮することも大切です。服装や遊ぶ場所など、次の点に気を付けていきましょう。
服装
・フード付きの服は避ける
走っているときに引っかかる危険があるため、フード付きの服は控えるのがベスト。もし着ている場合は、フードを服の中に入れると安全です。
・ヒラヒラした服や長いひもが付いた服は避ける
周りのものや、他の子と絡まるリスクがあります。シンプルなデザインの服装を心がけましょう。
遊ぶ場所
・1~2歳の場合
広すぎる場所では「どこまで逃げていいのかわからない」と不安になってしまうことも。室内やフェンスのある空間など、遊ぶ範囲がはっきりしている場所が適しています。
・3歳以上の場合
ルールを理解できるようになれば、広いスペースで遊ぶとより楽しめます。ただし、鬼ごっこに参加している子ども同士が見える範囲内にしておくことが大切。広すぎると、鬼や仲間が見えなくなり、不安を感じたりゲームが成立しにくくなったりすることもあるため、注意が必要です。
まとめ & 実践 TIPS
シンプルな遊びに見える鬼ごっこですが、意外な奥深さに驚いたかたも多いのではないでしょうか。運動能力の向上だけでなく、考える力や社会性など、さまざまな力を育むことができる鬼ごっこ。子どものアイデアを大切に工夫を凝らしながら、楽しんでいけるといいですね。
- 遊び・ゲーム