【医師監修】子どもの寝言が多い……原因と正しい対処法は?

寝ているはずなのに大声を出したり、話しかけてきたり……時に驚いてしまう子どもの寝言。寝ている最中に苦しそうな声を出したり、何度も寝言を言ったりしていると、「眠る環境が悪いのでは?」「学校で嫌なことがあったのかな?」と心配になる保護者のかたもいるのではないでしょうか。
今回は、日本睡眠学会が認定する総合専門医であり、「スリープクリニック銀座」院長の渋井佳代先生に、子どもの寝言についてお話を伺いました。「そもそもどうして寝言を言うの?」「子どもの寝言の対処法は?」といった疑問を解消していきましょう。
この記事のポイント
子どもが寝言を言う理由とは?
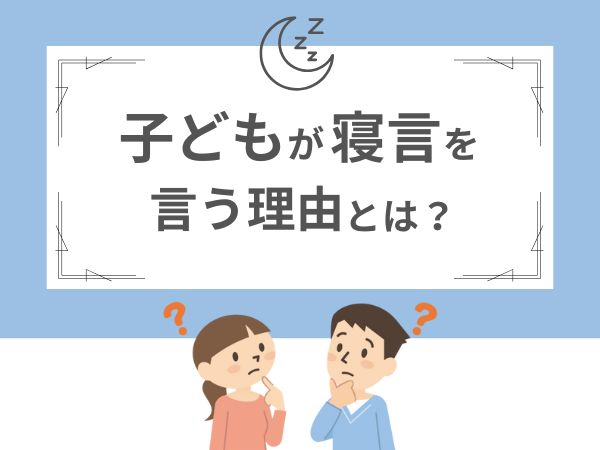
一生のうちに、寝言を経験したことがある人は、約67%と報告されています。さらに、3歳から10歳の子どもの寝言を調べた調査では、約半数の子どもが少なくとも年に1回、寝言を言っているようです。このことから、寝言は多くの人が経験する自然なことで、子どもによく起こる現象だということがわかります。
なぜ子どもの寝言が多いのかというと、脳がまだ成長の途中だからです。実は脳というものは、生まれた時から大人のように完成しているわけではなく、体と同じように成長していきます。脳が未成熟であるために、睡眠時に体の抑制がきかず、寝言が出ることがあるのです。
寝言は、話せるようになる1~2歳ごろから始まります。よく寝言を言うお子さまであっても、中学生くらいになると自然と落ち着く場合がほとんどです。子どもの寝言は、多くが自然な現象であり、寝言が多いからといって特に心配する必要はありません。
寝言が起きやすい睡眠のタイミングは?

睡眠には、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」の2つの状態があります。2つの状態を簡単に説明すると以下のとおりです。
ノンレム睡眠:脳も体も寝ている深い眠り
レム睡眠 :脳は動いているが体は寝ている
寝言は、ノンレム睡眠でもレム睡眠でも起こります。ただ、子どもの場合、寝言が起きやすいのは、深い眠りをしている「ノンレム睡眠」のタイミングです。あまりにもはっきりした寝言に、保護者のかたはびっくりするかもしれませんが、お子さま本人はぐっすり眠れているので、安心して見守っていてください。
寝言が増える原因とは?

寝言は子どもに出やすい自然な現象ですが、「最近、子どもの寝言が増えている気がする……」と思うと、気になるかたもいらっしゃるでしょう。寝言が増える背景には、次のような要因が考えられます。
ストレスや感情の大きな動き
寝言は、学校や家庭などでの出来事に影響を受けることがあります。
たとえば……
・きょうだいが生まれて生活が変化した
・学年が上がってクラスが替わった
・日中に怖い思いをした
・とても楽しいことがあった
などでも寝言は出やすくなります。
お子さまの寝言が最近多いなと気付いた時は、お子さまの生活の変化や感情が大きく動く出来事があったのかもしれません。お子さまが寝言で言っている言葉や普段の様子を見て、もしストレスや怖い出来事が要因になっているようであれば、その要因を取り除いてあげると寝言が減る場合があります。
睡眠不足や生活リズムの乱れ
寝言は、睡眠不足や生活リズムの乱れにも影響を受けます。夜更かしや寝る前のスマホやテレビは控えたほうがよいでしょう。特に、寝る前にスマホで動画を見ると、動画からの音や光、動きといった多くの情報が頭に入ります。
そのため、脳が興奮状態になり寝言が増えることがあります。寝る1時間前はスマホなどの光の刺激が出るものを控えましょう。寝る前は、二次元で動画より刺激が少ない絵本がおすすめです。
成長期特有の脳の活動
たとえば子どもが初めてピアノに触れたり、野球を始めたりするような、新しい体験を行うと、脳は寝ている間に新しく得た大量の情報を整理します。その過程で、寝言が出ることがあります。何か寝言を言っていても「新しいことをがんばっている証なんだな」と、温かい目で見守ってあげてください。
病気や睡眠障害の可能性
まれなケースではありますが、寝言で病気や睡眠障害が見つかる時もあります。さらに、寝言以外にも、
・いびきがひどい
・息が止まる
・苦しそうに見える
などの様子が見られる場合は、扁桃腺(へんとうせん)や呼吸の問題などがあるかもしれません。
気になる場合は、小児科や耳鼻咽喉(じびいんこう)科などで相談してみましょう。受診の際に、寝ているお子さまの動画を医師に見せると、説明がしやすいのでおすすめです。
保護者のかたができる寝言への対処法4つ

1.起こさず、そっと見守る
多くの場合で、お子さまの寝言は、深い眠りにある「ノンレム睡眠」の時に言っています。どんなにはっきり言葉を発していても、本人は熟睡しているため、会話をしたり、起こしたりする必要はありません。ベッドから落ちたり、布団が息苦しかったりしないよう、お子さまの安全だけ確保してあげましょう。
2.子どものストレスを減らす
ストレスがあると、寝言が増える時があります。まずは、家庭内の穏やかな雰囲気づくりから始めてみましょう。保護者のかたの笑顔が増えると、子どもは安心してストレスが減り、寝言の回数も少なくなるかもしれません。
3.よい睡眠環境を整える
子ども時代は成長が著しい時期であるため、規則正しく十分な睡眠時間を確保することが大切です。よい睡眠環境のためには……
・夕方以降は部屋をオレンジがかった光(電球色)にする
・寝る部屋は暗くする
・動画などの刺激を避ける
・絵本の読み聞かせ
・穏やかなスキンシップ
などがおすすめです。
4.専門家に相談する
多くの場合で、子どもの寝言は見守るだけで大丈夫です。しかし、寝言に加えて、いびきや無呼吸、苦しそうな様子がある場合は、小児科や耳鼻咽喉科など専門家への相談をおすすめします。お子さまの様子を観察してみてください。
まとめ & 実践 TIPS

子どもの寝言は、成長の一部として自然な現象であることがほとんどです。子どもの成長とともに、寝言の回数は減っていきます。良質な睡眠や生活習慣を心がけ、睡眠時の安全面にも気を付けながら、温かく見守りましょう。「寝言も成長の証」と前向きにとらえ、安心して子育てを続けてくださいね。
【参考文献】
Bjorvatn et al. Prevalence of different parasomnias in the general population. Sleep Med. 2010;11:1031-4.
Reimao et al. Prevalence of sleep-talking in childhood. Brain Dev. 1980;2:353-7.
編集協力/海田幹子、Cue`s inc.















