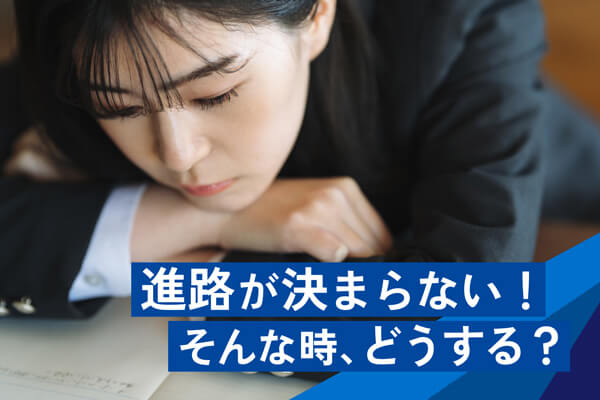動物園で自由研究! 見学のポイントを上野動物園学芸員が伝授
お気に入りに登録
 夏休みに家族でお出かけするなら、子どもの自由研究の題材にもなるような場所を選びたい。そんな保護者の希望をかなえる、人気のスポットが動物園だ。動物を見て回るだけでも楽しい動物園を、もっと楽しく充実したものにする見方やコツを、上野動物園教育普及係主任(学芸員)の井内岳志氏に聞いた。
夏休みに家族でお出かけするなら、子どもの自由研究の題材にもなるような場所を選びたい。そんな保護者の希望をかなえる、人気のスポットが動物園だ。動物を見て回るだけでも楽しい動物園を、もっと楽しく充実したものにする見方やコツを、上野動物園教育普及係主任(学芸員)の井内岳志氏に聞いた。
***
保護者のかたは「せっかく来たから、すべての動物を見せたい」と思いがちですが、すべてを見ようとせずに、子どもの好きな動物や興味のあるテーマ、エリアに絞って見学するのがポイントです。多くの動物園のホームページなどをチェックして、一緒に見たい動物やエリアを事前に決めておくと、当日はより盛り上がると思います。
上野動物園には、ご存知のようにパンダがいます。「パンダを見るのを楽しみに来たのに寝ていた」という声を聞くことがありますが、活発に動く開園直後か、閉園間際の見学がおすすめです。パンダは開園後に寝室から運動場へ移動し、自分のテリトリーに異常がないかパトロールします。閉園間際には、室内にエサを置いて運動場から寝室に誘導します。これらのタイミングは大好きな食事の時間でもあり、動いている姿や食事の様子を観察できると思います。
パンダの食事を見る時は、前足の使い方や歯を観察してみてください。あの堅い竹をどの歯で割るのか、どうやって竹を持っているのかなど、パンダならではの特徴がわかります。ほかのクマと比べてみると、新たな発見があるかもしれません。
テーマを決めていろいろな動物を比較しながら観察して回るのもおすすめです。たとえば、動物の「口」に注目してみましょう。草食動物のヤギやキリンには前歯がありませんが、同じ草食動物でもウマやバクには上の歯があります。「どうしてかな?」と話し合いながら見学したり、それらを写真で撮影したり記録したりするだけでも、自由研究になります。足、糞(ふん)、毛をテーマにするのもよいですね。ぜひ、チャレンジしてください。
あなたにおすすめ
- 子どもが自分で「選択する」ために必要な関わり方 [やる気を引き出すコーチング]
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- グリット(やり抜く力)は、環境や才能に関係なく自分で伸ばすことが出来る能力 ボーク重子さんに聞く!これからの子どもを幸せにする「非認知能力」の育み方~Lesson6 グリット(やり抜く力)
- 勉強の遅れに不安や焦りを感じている子どもの気持ちにどう関わる?[やる気を引き出すコーチング]
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 多様性社会で特に身につけたいのは「共感力」。 どう伸ばせばいい?ボーク重子さんに聞く! これからの子どもを幸せにする「非認知能力」の育み方~Lesson3 共感力
- 「この子に問題がある」と感じた時に見直してみることは?[やる気を引き出すコーチング]
- クラス替え 仲のよい友達とクラスが分かれて元気がない我が子…何と声をかける?
- 好奇心は親が子どもの手本になることで育つ ボーク重子さんに聞く!これからの子どもを幸せにする「非認知能力」の育み方 ~Lesson8 好奇心













![「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201003/20100309-1.jpg)