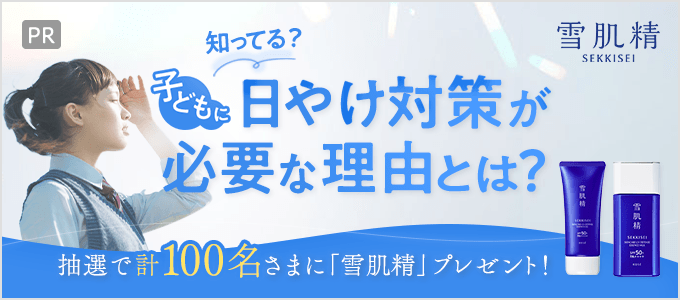図を使う応用問題、具体例と一緒に覚えるのが早道と中学受験の専門家
お気に入りに登録
 中学受験の算数では図や比を使って解く問題が多い。図を描いて答える問題が苦手という小6女子の保護者に、ベネッセ教育情報サイトが、平山入試研究所の小泉浩明氏からアドバイスをもらった。
中学受験の算数では図や比を使って解く問題が多い。図を描いて答える問題が苦手という小6女子の保護者に、ベネッセ教育情報サイトが、平山入試研究所の小泉浩明氏からアドバイスをもらった。
***
【保護者からの質問】
線分図や面積図などを描いて考える問題で、どの図をどの問題で使えばいいのかわからないようです。応用問題ともなると、解答を見ながらでないと解けません。(小6女子の母親)
【小泉氏からのアドバイス】
算数の文章題で使う図には、「線分図」「てんびん図」「面積図」などがあります。どの問題でどの図を使うのか、具体例とともに覚えてしまうのが早道でしょう。
たとえば食塩水の濃度の問題なら、てんびん図か面積図と覚えます。例題をもとに、てんびん図の描き方のポイントをお話しします。
6%の食塩水(A)300gと14%の食塩水(B)100gをまぜました。できた食塩水は何%の食塩水ですか。
【図を描く手順】
(1) 三角形の支点の上に横棒を書き、てんびんの形にする
(2) 横棒の両端の上と支点の上に、問題に出てくる3つの濃度を書く。めもりは右にいくほど大きくなる
(3) 横棒の両端に、おもりのようにつり下げる
食塩水の量を書く問題にある濃度は、6%、14%、まぜてできる食塩水の濃度△%です。△%は6%より大きく、14%より小さいはず。つまり、6%<△%<14%ということになります。そして、めもりは右にいくほど大きくなる。この二つがポイントです。
したがって、手順(2)→ てんびんの横棒の左端に6%、支点の上に△%、右端に14%手順(3)→ 6%の下に300gのおもり、14%の食塩水の下には100gのおもりを下げるここまでくれば、あとはてんびんのつり合いから、両端から支点までの長さの比を求め、逆比にすれば食塩水の濃度が求められます。
てんびん図が描けないのは、どこに、何を、どの順番で描くかを覚えていないから。まずは図を何回も描き、手順を覚えましょう。ほかの図も同じように克服してください。
出典:線分図や面積図など、どの図をどの問題で使えばいいのかがわかりません -ベネッセ教育情報サイト
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 学生のマインドセットを行いながら大学1年生から「就職力」を鍛えていく【変わる大学】
- 算数「濃度」[中学受験]
- 【10年使うことも】子どもの学習机の選び方のすべて
- 学部横断型で学ぶ、先進のグローバル教育 専門性を生かして世界を舞台に活躍する人材を育成【変わる大学】
- 【専門家】 5-6年生で習う間違えやすい漢字とは?難しい熟語を覚える時や、保護者の声かけを嫌がる時はどうする?
- ミシンで作る入園、入学アイテム別名入れのポイント
- CO-BO│「発達障害のある子どもたちの学びに関わる問題」 フォーラム NPO法人特別支援教育研究会 未来教室 秋山明美先生(東京都文京区立柳町小学校 元校長)【前編】
- 読書好きなのに問題文だと思考停止の小4男子に、受験の専門家がアドバイス
- ひらがなの勉強や生活習慣の準備は、みんなどうしてる? 入学準備アンケート結果をチェック!













![算数「濃度」[中学受験]](http://benesse.jp/common/static/kj/common/images/chu/tukamu05/01.gif)