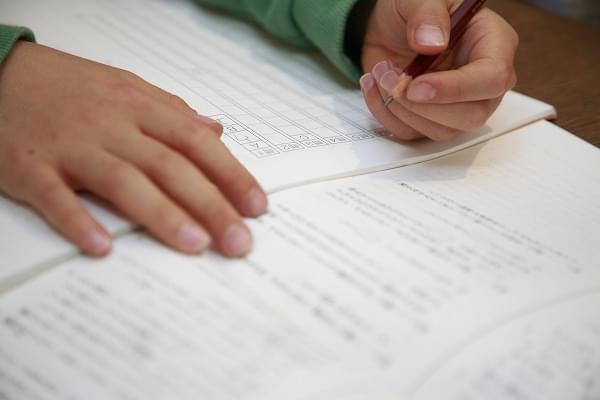過去問で付けたい……整理する力[中学受験合格言コラム]
お気に入りに登録
過去問演習で付けたい力の一つに、「整理する力」がある。この力は与えられた条件をうまく整理する能力であり、問題を解く前の「準備」と言ってもよいであろう。ただし「準備」と言っても、これがなかなか難しい。「準備」の上手・下手により、解ける問題も解けなくなってしまうのだから非常に重要なステップと言える。
たとえば国語の記述問題でも、この「準備」する力が重要である。特に文字数が100字を超えてくると、「何を」「どのように」書くのかを的確に準備していないと、書き上げたものが書きたかったものとズレてしまい、減点の対象になってしまう。下書きの用紙を配布する学校もあるが、おそらく完全に下書きをする時間はないだろうから、簡単なメモで済ませることになる。
また社会の記述でも、書きたいことやそれらをどの程度詳しく書くかを、事前に決めておく必要がある。
算数でも「準備」は非常に重要である。問題が難しくなればなるほど、準備の善し悪しによって問題が解けなくなってしまうことがある。その理由は、算数や数学における「解法の手順」を考えてみればよくわかる。たとえば算数や数学の「解法の手順」を、以下のように単純化して考えてみよう。もちろん問題が複雑になれば、この手順をくり返す必要はあるが、多くの場合、以下の手順で問題を解いているはずである。
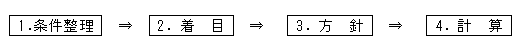
多くの問題では「条件整理」は作業であり、「着目」のステップこそが問題解法のポイントであると言える。ただし、難関校になればなるほど、「条件整理」も解法のポイントになる問題を出す場合がある。たとえば「立体の切断」の問題で複雑な切断の場合は、切断面の状況を的確に把握するのが難しいが、それができなければ次のステップに進めないのである。あるいは非常に長く、かつ複雑な文章題の内容を理解し、場合によってはその図を描くというのもこの「条件整理」のステップと言える。このように、難関校の問題は「条件整理」が難しい場合があるので、過去問演習で十分にトレーニングすべきであろう。
たとえば国語の記述問題でも、この「準備」する力が重要である。特に文字数が100字を超えてくると、「何を」「どのように」書くのかを的確に準備していないと、書き上げたものが書きたかったものとズレてしまい、減点の対象になってしまう。下書きの用紙を配布する学校もあるが、おそらく完全に下書きをする時間はないだろうから、簡単なメモで済ませることになる。
また社会の記述でも、書きたいことやそれらをどの程度詳しく書くかを、事前に決めておく必要がある。
算数でも「準備」は非常に重要である。問題が難しくなればなるほど、準備の善し悪しによって問題が解けなくなってしまうことがある。その理由は、算数や数学における「解法の手順」を考えてみればよくわかる。たとえば算数や数学の「解法の手順」を、以下のように単純化して考えてみよう。もちろん問題が複雑になれば、この手順をくり返す必要はあるが、多くの場合、以下の手順で問題を解いているはずである。
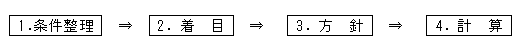
| 1. | 条件整理 | : | 与えられた条件を整理するステップ。 問題理解のために、線分図や図表などを使う場合もある。 |
| 2. | 着 目 | : | 整理した条件や線分図などを見て、解法の「糸口」を見つけ、そこに着目するステップ。 |
| 3. | 方 針 | : | 公式やその単元に特有の考え方(図の性質など)を使ったり、式を立てたりするステップ。 |
| 4. | 計 算 | : | 立てた式などを計算して、答えを出すステップ。 |
多くの問題では「条件整理」は作業であり、「着目」のステップこそが問題解法のポイントであると言える。ただし、難関校になればなるほど、「条件整理」も解法のポイントになる問題を出す場合がある。たとえば「立体の切断」の問題で複雑な切断の場合は、切断面の状況を的確に把握するのが難しいが、それができなければ次のステップに進めないのである。あるいは非常に長く、かつ複雑な文章題の内容を理解し、場合によってはその図を描くというのもこの「条件整理」のステップと言える。このように、難関校の問題は「条件整理」が難しい場合があるので、過去問演習で十分にトレーニングすべきであろう。














![国語の物語文で人の気持ちを読み取るのが苦手です[中学受験]](/_shared/img/ogp.png)
![算数「数の性質」[中学受験]](http://benesse.jp/common/static/kj/common/images/chu/tukamu13/01.gif)