【専門家監修】「これって過干渉?」は誰もが持つ悩み。合言葉は「手を出さずに見守ること」
お気に入りに登録
- 育児・子育て
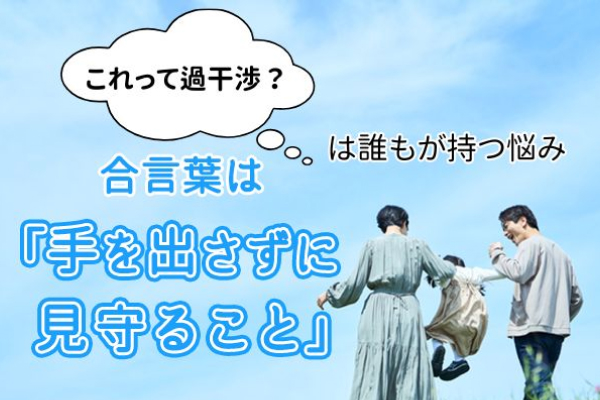
「これは過干渉? それとも適切?」と、日々悩みながら育児をしている保護者のかたも多いのではないでしょうか。お子さまが健やかに育つためには、保護者のかたが適切なタイミングで少しずつ手を離していくことが大切です。
そこで今回は、過干渉になりやすい現代ならではの理由や、保護者のかたの心がラクになる「手を出さずに見守る育児」について、日本女子大学の塩﨑尚美先生にお話を伺いました。
どこからが過干渉なの?

そもそも過干渉とは?
「過干渉」とは、必要以上に保護者のかたがお子さまに関与し、お子さま自身が自分で考えたり、チャレンジしたりする機会を奪うことを指します。
過干渉をし続けると、子どもの自立心や自主性を妨げられ、保護者のかたが意図せずとも、お子さまの成長に悪影響を及ぼすことがあります。
過干渉と適切な干渉は明確にラインを引きづらい
では、「どこからが過干渉なの?」という疑問が出てくるかと思います。しかし、残念ながら、明確にこことラインを引くのは難しいです。
なぜなら、子どもの性格や年齢などによって、適切なラインが違うからです。たとえば、1歳の子どもに服を着せてあげるのは適切ですが、理由なく小学生に服を着せてあげるのは過干渉といえるでしょう。
あと少しでできそうなことは、手を出さずに見守り、お子さまの状態に目を配りながら、その子その子に合った対応を行うことが大切です。
どうして過干渉になってしまうの?

次に、どうして過干渉になってしまうのかを見てみましょう。
根底にあるのは、令和の保護者のだれもが持つ「不安感」
テレビのニュースやネットの情報、SNSなどから、育児に関する情報があふれている現在。
さまざまな情報により、「この年齢ではこれができなくてはいけない」「あの子はもうひらがなが書けている」「ちゃんとしなければ将来この子が困るのではないか」など、他の子と自分の子を比較したり、教科書どおりの成長度合いを意識しすぎたりするあまり、不安感を強めてしまうことがあります。
子どもに「ちゃんと育ってほしい」という親心から、必要以上に干渉してしまうのです。いいところだけを切り取ったような、あいまいな情報に惑わされず、まずはお子さまの様子をじっくり見てあげることが大切です。
つい待てずに助けてしまうことも
「子どもがモタモタしていると、つい待てずに助けてしまう……」という保護者のかたもいるのではないでしょうか? そのお気持ち、とてもよくわかります。お子さまがしていることを、手や口を出さずに見守るというのは、思った以上に大変で忍耐力が要ります。
しかし、お子さまのこのモタモタこそ試行錯誤の表れで、まさに成長している道半ばなのです。つい手助けしたくなるかもしれませんが、「自分の忍耐力が試されている」と心に刻み、優しく見守ってあげてください。
何かができた時の「やった! できた!」という、お子さまのうれしそうな笑顔が見られる喜びを感じられるかもしれません。
過干渉が子どもに与える影響は?

過干渉が子どもに与える影響を、心・成長・人間関係の3つの面からご紹介します。
心への影響:常に漠然とした不安を抱く
過干渉を受けて育った子どもは、漠然とした不安を持つことが多いです。それは、過干渉によって自分で考え行動した経験が乏しいため、保護者のかたがいないと「これでいい」「こうやれば大丈夫」という実感が持てないからです。
いつも不安で安心感が持てず、結果として自分に自信がなくなる傾向にあります。逆に、自分で考え行動し成功した経験があれば、「自分でできる」「やってみよう」と自分に自信が持てるようになるのです。
成⻑への影響 :無気力・無関心につながる
過干渉を受けて育つと、自分に自信がないため、いろいろなことに興味・関心を持つことが少なくなり、自発的に何かに取り組まないという傾向が出てきます。
「これやってみたい!」より「どうせ自分にはできないし……」という気持ちが勝ってしまうのです。そのため、無気力・無関心につながっていきます。
保護者のかたが「失敗しても大丈夫だからやってみよう!」と声をかけてあげるだけで、お子さまには勇気がわいてきます。自分の意思でやりたいことをやってみるという経験は、きっとお子さまに自信を与えてくれるでしょう。
⼈間関係での影響:受け身になり人との距離感がつかみにくい
過干渉により、何も言わなくても保護者のかたに助けられてきた経験から、他の人に助けを求めたり頼ったりするのが苦手になりやすいです。
そのため、受け身の姿勢になり人との距離感がつかめず、結果的に他人と深い関係をつくりにくくなってしまうかもしれません。「察してくれないならいいや」と、不信感を持ち、殻に閉じこもりがちになることもあります。
保護者のかたは、お子さまのヘルプを先読みして助けるのではなく、助けを求めてくるまで待つことで、お子さまが自分の意思をしっかりと伝えられるようになります。
お子さまが成長し自立していくために、保護者のかたが頭の片隅においておきたいこと
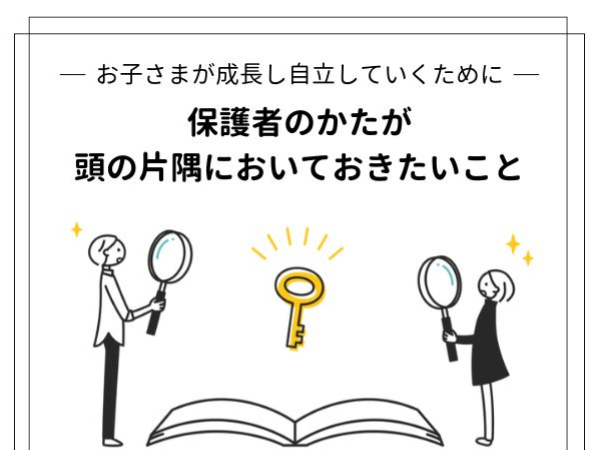
最後に、保護者のかたが過干渉をせずとも、お子さまが成長し自立していくために、覚えておきたい点をご紹介します。
子どもが助けを求めたら助けよう
前述したとおり、過干渉か適切な干渉かの判断は、お子さまの状況によって違うため、難しい問題でしょう。しかし、一つの目安に、お子さまが助けを求めているのか、そうでないのかということがあります。
お子さまが自らの意思で助けを求めるまでは見守り、助けを求めてきたら保護者のかたが関わるというスタンスが大切です。
まだ、おしゃべりができないお子さまであれば、保護者のかたが積極的に助けることもあります。たとえば、自分で危険かどうかが判断できない時です。危険回避の時以外は、お子さまが求めてきた時に助けに入りましょう。
過干渉にならないためには、状況を読み取るために、お子さまをよく観察するところから始めてみてください。
やってあげるよりも応援してあげる
すぐに助けを求めたり自分でやろうとしなかったりするお子さまには、手を出してあげるよりも、応援してあげるとよいでしょう。
「待ってるよ」「やりたいようにやってごらん」「見てるよ」と声をかけるだけでも、お子さまの不安が和らぎ、勇気がわいてくるものです。
お子さまの不安が減ると、保護者のかたの不安も減ってきます。「過干渉にならないように」と思うあまり急に突き放すことはしないで、「大丈夫だよ」「失敗してもいいんだよ」と伝えて、お子さまを安心させてあげましょう。
つい手助けしたくなるラインを知る
つい手助けしたくなる保護者のかたは、まずは自分がどの段階で手助けしたくなるのかを、認識することから始めましょう。
たとえば、通学前の朝の準備をモタモタしている小学生のお子さまなら、口や手を出したくなるのが、家を出る何分前なのか認識してみるといいでしょう。そして手助けしたくなったタイミングで一呼吸おいて、もう一歩待とうとすることで、だんだん待てるようになっていきます。
保護者のかたが手助けせず、待てるようになることも大切です。手助けせずに見守れるようになった時は、ぜひご自身をほめてあげてくださいね。
まとめ & 実践 TIPS

過干渉な育児は、お子さまの心や成長、人間関係などさまざまなことに影響を与える可能性があります。過干渉にならないためには、まずは、手助けする前に一呼吸おいてお子さまを見守ること、そして助けを求められた時に助けることが大切です。
「手を出さずに見守る」、言うのは簡単ですが、つい手を出したくなることもあるかもしれません。保護者のかたは、まず自分の待てるラインを知り、少しずつそれを延ばしていきましょう。保護者のかたとお子さまとで、一緒に成長する機会になればいいですね。
編集協力/海田幹子、Cue`s inc.
- 育児・子育て
あなたにおすすめ
- 反抗期に悩む保護者に「自分の時間」が大切なワケ
- 「私ってヘリコプターペアレントかも……」チェックリストと、そんな人に試してほしい子離れの方法
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 反抗期は子どもからの「サイン」? 向き合うのに疲れた時、大切にしてほしいこと/保護者のお悩み解決隊#10
- 親が過干渉になる原因と5つの特徴 子どもへの影響は? チェックポイントと対処法を専門家が解説
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第13回 進学先、決定?
- E判定に落ち込む受験生の我が子が心配…どうサポートすべき?/保護者のお悩み解決隊#7
- 大切なのは親子の自立心~子離れできない親「ヘリコプター・ペアレント」
- 【どうなる?どうする?娘の大学受験】第12回 合格発表

























