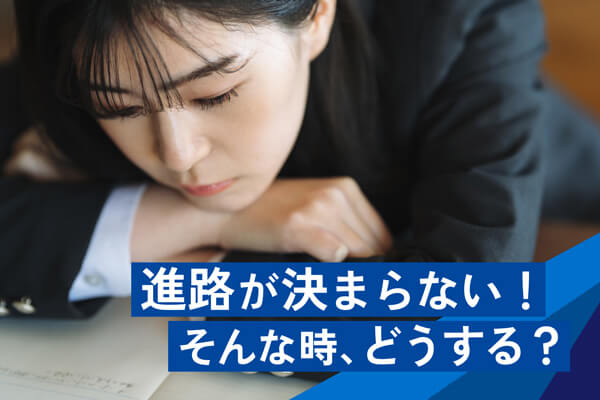子ども社会にも広がる電子マネー、利便性の裏にはらむ危険とは?
お気に入りに登録
 近年、急速に進化を続ける電子マネーは、大人社会だけではなく子どもたちにも広まっている。子どもたちが「目に見えないお金」を利用することで、お金に対する感覚に影響が出るのではと不安を抱く保護者も少なくないだろう。ファイナンシャル・プランナーの宮里惠子氏に、進化し続ける電子マネーとの付き合い方について伺った。
近年、急速に進化を続ける電子マネーは、大人社会だけではなく子どもたちにも広まっている。子どもたちが「目に見えないお金」を利用することで、お金に対する感覚に影響が出るのではと不安を抱く保護者も少なくないだろう。ファイナンシャル・プランナーの宮里惠子氏に、進化し続ける電子マネーとの付き合い方について伺った。
***
電子マネーは、1990年代後半から普及し始め、年々利用者数を伸ばしています。SuicaやPASMO、Edyなどプラスチックのカードに移し替えた「ICカード型」やクオカードなどの「プリペイド型」、携帯電話に移し替えた「携帯電話型」、インターネット上のサーバーで「現金に相当する通貨価値」が管理されている「サーバー型」を利用する人も増えています。
最近は、子ども専用の「ICカード型」電子マネーや、保護者のクレジットカードと連携させたオートチャージ付き子ども専用電子マネーが販売されるなど、子ども社会へも急速に広がっています。たくさんの現金を持ち歩かせなくてもすむ、小銭がいらない、支払いがスムーズなど、多くの利便性がありますが、一方でさまざまな危険性が考えられます。
利便性を求めて、子どもに電子マネーを持たせている保護者のかたも多いのではないでしょうか? 確かに電子マネーは便利な道具ですが、慣れすぎると「物の価値がわからなくなる」「いくら使ったか意識しなくなる」などの危険性もあることを、念頭に置いてほしいと思います。
出典:電子マネー「目に見えないお金」との付き合い方【前編】 -ベネッセ教育情報サイト
あなたにおすすめ
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- 海外日本人学校や補習授業校で教員不足 原因を専門家が解説
- 種類を見分けて上手に落とす! シミ抜きのコツ
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 海外進学を実現するには「自己分析力」が必要と専門家語る
- 【これからの時代に必要な力】新しい時代に対応する、中学生の学びと親の関わり方
- クラス替え 仲のよい友達とクラスが分かれて元気がない我が子…何と声をかける?
- 自信のない子に否定的な言葉は絶対NG! 大切なのは「たくさん褒めてあげること」と専門家
- 受験勉強どうする?先輩たちの後悔から学ぼう













![「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201003/20100309-1.jpg)