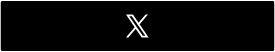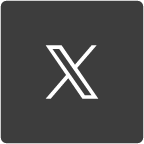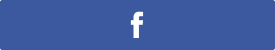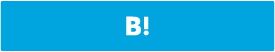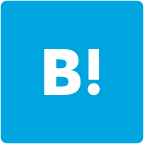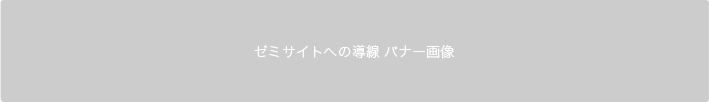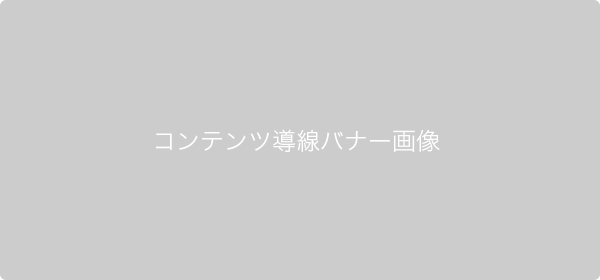コロナ後に学校はどう変わるか?不登校新聞編集長に聞く【不登校との付き合い方(27)】
- 育児・子育て
新型コロナ流行の間、学校が一時期閉鎖になり、「学校に行かない」ことが「安全」を意味した時期がありました。あらためて、学校とはどういう存在だったのかが問われたともいえるでしょう。「不登校新聞」編集長の石井志昂さんとともに、これまでの学校の役割と、これからの学校の在り方について考えました。

昭和の時代、学校は「希望に溢れた輝ける施設」だった
もうすぐ夏休みが始まります。ホームルームで先生が「明日から夏休みに入ります」と話した時に、子どもたちがワーッと盛り上がる、というよくあるシーンが思い浮かびます。でも、これってよく考えると、みんなそんなに学校を休みたいんだ、ということではないでしょうか。もし、学校が誰もが行きたい、楽しい場所であるならば、「明日から夏休み」と言われれば、残念だと感じるはずなのです。
学校は、かつては誰もが行きたい、輝かしい希望の施設でした。今の保護者世代の、さらに親の世代にとってはそういう場所でした。なにしろ最新の設備がそろっているし、給食が出る場所であり、女性であっても、教育を受けて大学にも行ける、さらに学校の先生になるという選択肢もある、素晴らしい場所でした。こうした人々の「希望」というものが集まっている施設が学校だったのです。
学校にそうしたイメージをもつ世代に育てられた、今の子どもの保護者世代も、「学校は楽しく通って当然の場所」というイメージが強いでしょう。子どもが「学校に行かない」ということについて、非常に受け入れづらいものです。
学校は輝ける希望の施設なのに、なぜ学校へ行きたがらないのか、どうしても理解できない世代にとっては、不登校はネガティブな話題でしかありませんでした。
少し歴史を紐解いてみると、教育の義務は日本国憲法が定められた時にできました。憲法26条第2項に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。」と書かれています。これが定められた背景には児童労働があり、子どもを学校へ行かせない保護者への牽制だったわけです。学校ができたばかりのころには、子どもにとっては労働を振り切って学校に行くことは喜びでしかなかった、という歴史があります。
「学校は喜んで行くもの」という考え方を刷り込まれてきた3世代目が今の保護者世代。ここであらためて「なぜ学校は行かなくちゃいけないの?」と問われても、「なぜも何もないでしょう」というくらい、学校に行くことは当たり前なのが、多くの保護者だと思います。
不登校という言葉は意外と古くからある
「登校拒否」という名称が出てきたのは日本では1960年代ごろ。元はアメリカのジョンソンという学者が、1946年に「学校に行かない子たちがいるようだ」ということで8人の事例などをもって論文を書いたのが、世界的にインパクトをあたえたそうです※。そこでは「学校恐怖症」という言葉が使われていますが、その後、日本に渡ってくる中で、病ではないけれど、学校に行かないという現象がある、ということで「登校拒否」という言葉を研究者たちが使うようになったそうです。
日本で、学校に何人の登校拒否児がいるかという調査が行われるようになったのは1966年から。このデータをとり始めた時期は、世界的に見てもかなり早かったのです。
「登校拒否は誰にでも起こりうる」と当時の文部省が発表したのが1991年、今からちょうど30年前。保護者が学校へ行かせないのではなく、本人が学校に行きたくない、行こうとしても行けない事例を「不登校」と呼ぶことにする、と、行政主導で名称は変わりました。
不登校は今も、ネガティブな論調で語られる。でも、レアなものではなくなった
世代を超えて「学校って素晴らしい場所だ」と刷り込まれてきましたが、最近になって、不登校の子どもたちがいるということを少しは認知されました。多少ポジティブな面についても語られるようにはなってきましたが、やはりまだネガティブにとらえている保護者は多いでしょう。保護者向けの講演をすると、上がってくる声には、学校へ行かないことへの恐怖感・不安感、ある日我が子が急に変わってしまった感じがする、ということが今も多いのです。
それでも、不登校の子どもは、昔ほどレアな存在ではなくなりました。私が小学生だったころは、1学年に1人いるかいないか、というくらいでしたから。今では、不登校の子どもに「なぜ学校に行かないのかな」と、考えてくれるような環境にはなってきたと思います。学校に行きたがらない子どもはいるみたいだけれど、それは珍しいものだった、というところを経て、「学校に行きたがらない子どもは少なからずいる」と気づく人が増えてきたのだと思います。
コロナによって、学校はもっとゆるくて大丈夫だとわかり始めた
不登校が頭ごなしに否定されなくなってきたのは、徐々に変わったのではなく、ここ最近のこと。特にコロナ禍以降大きく変わってきました。コロナによって大きく変わったのは、「学校ってもっとゆるくても大丈夫だったんだ」と感じる人が増えたことではないでしょうか。
顕著に表れているのは、教育学者の内田良さんが指摘しているマスクに関する校則。マスクは白じゃなくちゃダメといわれていたのが、昨年の今頃、マスク不足が深刻だった時に、白いマスクが必ずしも手に入らないという状況がありました。マスクをすることが大事で、色まで指定する学校の方が非人道的だといわれて変わっていきました。今や登校する生徒のマスクはカラフルになっています。それでも、多くの学校が荒れたわけではありません。
制服も、何がなんでも着なくちゃいけない、というわけではなくなった学校が増えました。衛生面の問題から毎日洗いたいとなると、洗い替えがないので、ジャージや私服でもOKとうする学校が増えました。「制服の乱れから学校が荒れる」と、長く言われてきたわけですが、実際には制服をやめてもそんなに深刻なことは起こりませんでした。もう少し、学校は弾力的に運営しても大丈夫なんだとわかってきた、というのが、コロナ禍で起こった大きな変化です。
こうした流れは、希望が持てることだと思います。校則ってこんなにガチガチにしなくて大丈夫だという事例が集まると、もう少し子どもの人権に配慮した校則へと全体的に変化していくでしょう。
先生自身も、もっと楽になるはずのオンライン授業
もちろん、オンライン授業も大きな変化です。オンライン授業の実施によって、子ども自身が安心して学べる環境を学校が提供できるということがわかりました。一方で端末が足りないことや地域格差も如実になって、大変な混乱もありましたが、一過性のものだったでしょう。
オンライン授業は導入までは大変でも、先生たちの働き方改革にもつながるはずです。一度軌道に乗れば、ある程度は一斉授業にできるとなると時間に余裕ができ、個別の生徒に対応できるようになります。オンラインとオフラインの融合は、N高校などでも実践されています。先生たちの時間の余裕が生まれることで、先生たちがより子どもたちに安心な教育環境を整えてあげられるようになるでしょう。
「オンラインのほうがいい」というよりも、裏を返せば、全てオフラインでやろうとしたら無理がたたった、ともいえる数十年間だったともいえます。オンライン授業だけでなく、いつかやらなくては、といわれつつ進まなかったことが、このコロナ禍で一気に進んだのです。
なぜ、学校に行きたがらない子どもが増えたのか、を考えた結果、じゃあこれからの学校は、どのような施設であったらいいのか、ということについては課題もたくさん見えてきました。課題が見えたというのは大きな前進です。
まとめ & 実践 TIPS
かつての学校は、児童労働から子どもを守り、将来への希望をつなぐための、輝ける場所でした。その思いがあるからこそ、保護者もその上の世代も、学校に行かないことは悪いことと言われてきました。それが、不登校の子どもが増えたことで「なぜ学校に行きたがらないのか」ということを、多くの人が考え直すようになり、さらにコロナ禍によってこれまでの学校の常識が、覆されるようになってくると同時に、課題が浮き彫りになり始めたのです。次号では、その課題について掘り下げます。
※“School Phobia” Johnson, A. M., Falstein, E. I., Szurek, S. A. & Svendsen, M.

- 育児・子育て