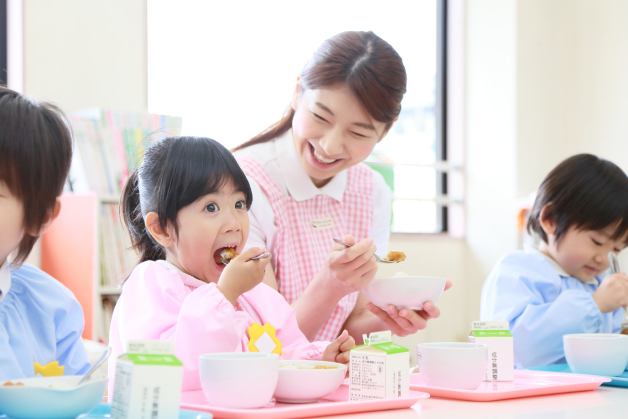セリ・ナズナ、ゴギョウ……春の七草を全て言えますか? 「七草粥(がゆ)」で食育を!
お気に入りに登録
お正月を過ぎてスーパーに行くと、春の七草パックが売られているのを見かけます。1月7日は人日(じんじつ)の節句。ご家庭で七草粥をいただいて、1年の無病息災を祈りましょう。春の七草の由来や意味を教えながら一緒に作れば、子どもの食育にもなります。

春の七草の簡単な覚え方は?
七草粥に入れる7種類の葉が「春の七草」と呼ばれるのはご存じのとおり。子どもの頃にがんばって覚えた記憶のある方もいるかもしれませんが、全て言うことはできますか。
春の七草は、次のとおりです。
・セリ(芹)
・ナズナ(薺)
・ゴギョウ(御形)
・ハコベ(繁縷)
・ホトケノザ(仏の座)
・スズナ(菘)
・スズシロ(蘿蔔)
漢字にすると難解なものが多いですね。スズナは蕪(かぶ)、スズシロは大根、ナズナはペンペン草といったほうがわかりやすいかもしれません。
春の七草は、次のように「5・7・5・7・7」のリズムで唱えると、自然に覚えてしまいます。お子さまにもぜひ教えてあげてください。
「セリ・ナズナ / ゴギョウ・ハコベ/ ホトケノザ / スズナ・スズシロ / 春の七草」
どうして1月7日に七草粥を食べるの?
七草粥は、お正月の食べすぎ・飲みすぎで疲れた胃をいたわるために食べるといわれることがあります。確かに胃にはやさしいのですが、これは後から考えられた理由であり、歴史をさかのぼると、より深い意味が込められています。
七草粥は、もともと五節句の一つである「人日の節句(1月7日)」にいただく節句料理です。七草粥の由来となる風習は中国から平安時代に伝わりました。江戸時代、幕府が五節句を公式行事としたことをきっかけに、この日に七草粥を食べる風習が庶民にも広がったといわれています。
七草は早春にいち早く芽吹くことから「邪気を払う」とされています。そのため、七草粥を食べて1年の無病息災を祈るという思いがこの風習に込められています。
七草粥の作り方は?
春の七草は、スーパーに行けばパックが手に入りますが、子どもと一緒に野原や河原などに出かけて探してみるのも楽しいかもしれません。全て見つけるのは難しいかもしれませんが、ナズナ(ペンペン草)などは比較的見つかりやすいでしょう。ただし、野外で七草を探す際には、有毒植物には十分に注意してください。
七草粥の作り方は、普通のお粥に七草を混ぜるだけです。七草をきれいに洗って細かく刻み、お粥ができ上ったら混ぜ入れて、お好みによって塩で味を調えましょう。
あなたにおすすめ
- 育児生活が10年を超えるころ、気が付くと家族関係がギクシャク!? 原因と対策は?
- もうすぐ入園・入学! 友達づくりが上手な子に育てるには【基礎編】友達づくりが上手な子と苦手の子の差って何?
- 【マンガ】どうなる!? 息子2人の大学受験…イマドキ保護者の悶えるホンネ <第92回>親にされてよかったこと1 声かけ
- 九九の覚え方のコツは?つまずきの原因や間違えやすい段も徹底解説!
- 第4回学習基本調査・学力実態調査 [2006年]
- 【マンガ】どうなる!? 息子2人の大学受験…イマドキ保護者の悶えるホンネ <第90回>失敗談2 知らなさすぎたこと
- 【体験談】おすすめ勉強法!5つのお悩み別に効果的な方法&NG勉強法をプロが解説
- 基礎・基本力を定着させ「細やかなセンス」を育む授業[こんな先生に教えてほしい]
- 【マンガ】どうなる!? 息子2人の大学受験…イマドキ保護者の悶えるホンネ <第91回>失敗談3 遅すぎたこと