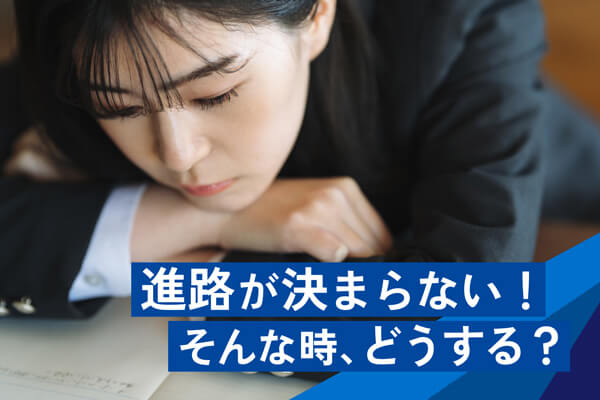仲間の厳しい評価が刺激に 大学研究室の学びとは
お気に入りに登録
 先が予測できない現代。子どもたちの明るい将来を築くには、大学や学部をどのように選択して何を学んでいくべきだろうか。早稲田大学スポーツ科学部教授の平田竹男氏の研究室を訪ね、ゼミでの学びがどのように行われているか、また学生のうちに学んでおくべきことは何かについて伺った。
先が予測できない現代。子どもたちの明るい将来を築くには、大学や学部をどのように選択して何を学んでいくべきだろうか。早稲田大学スポーツ科学部教授の平田竹男氏の研究室を訪ね、ゼミでの学びがどのように行われているか、また学生のうちに学んでおくべきことは何かについて伺った。
***
私のゼミでは毎回必ず全員に、テーマについて調べさせ、発表をさせています。傍観者としてではなく当事者として参加する経験を積むことで、自分でものを調べ、自分の頭で考え、まとめる、という力が身に付くからです。加えて、発表後の評価も学生たちに任せます。その日の発表の上位3人と下位2人を決めるのですが、下位で選ばれ続けていた学生が、刺激を受けて発奮し上位に選ばれることも。ゼミを重ねるごとに明らかに顔付きが変わる学生も出てきます。そんな瞬間に立ち会えるのは、私にとって大きな喜びです。
また、好きなことをさまざまな角度から徹底的に「分析」するという経験は、高校生までに積んでおくべきです。たとえば、スポーツが好きなら、技術や体力を磨いたり、好きなチームを応援したりするでしょう。それだけではなく、「ボールはどこでどのように開発・製造されるのか」「チームの運営者は誰なのか」というように、物事の一面だけではない幅広い視点を持って調べてみるのです。好きなことに夢中になりすぎると、勉強に差し障りがあると心配する保護者のかたもいるかもしれません。しかし、一つの分野を徹底的に分析し極めることは、どんな分野にも通じる力が付くものなのです。
「分析」は人生において壁にぶつかった時にも役立ちます。順調な人生を歩んでいても、いつかは壁に当たり、挫折を味わうことがあります。どんな時に体や心の調子がよくなるのか、あるいは悪くなるのか、学生時代から自分を客観的に見る姿勢を備えておけば、そんな時にも対応できるでしょう。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]
- 【体験談】大学生保護者激白!高1・2のときにしておけばよかったことは?~学習習慣・生活編~
- 「面倒見の良い学校」考 その2[中学受験合格言コラム]
- 進路が決まらない!そんな時に、高校生と保護者がやるべきこと【体験談あり】
- 「勉強しない高校生」にならないために、今、保護者ができること
- 「面倒見の良い学校」考 その1[中学受験合格言コラム]
- クラス替え 仲のよい友達とクラスが分かれて元気がない我が子…何と声をかける?
- 国公立大と私立大でどこが違う?一般選抜について国公立・私立大別にわかりやすく解説!
- 「面倒見の良い学校」考 その4[中学受験合格言コラム]













![「○○さんと同じクラスにしてほしい」と先生に頼むのは、わがままでしょうか?[教えて!親野先生]](/img_o/kj/kyouiku/201003/20100309-1.jpg)