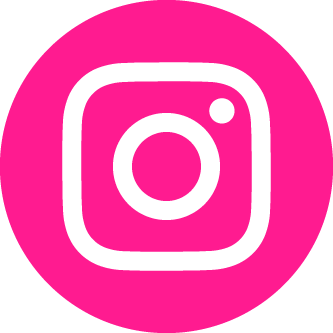赤ちゃん言葉で話しかけるのは、やめるべき? 話す頻度が重要?[教えて!親野先生]
- 育児・子育て
お子さまに赤ちゃん言葉で話しかけるのがいいのか、やめるべきか迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。赤ちゃん言葉はお子さまが聞きやすく、真似しやすいとは思いつつも、最初から普通の言葉で話すほうがムダがなくてよいのではないかと感じられることもあるでしょう。
赤ちゃん言葉はやめるべきなのでしょうか。教育評論家の親野智可等先生に伺いました。

【質問】子どもに赤ちゃん言葉を使うべきか、普通の言葉を使うべきか夫婦で意見が割れています。
子どもに赤ちゃん言葉をつかうべきか、やめるべきか、迷っています。夫(子どものパパ)は、「わんわん」「にいに」「ぶうぶ」などの赤ちゃん言葉ではなく、はじめから「犬」「お兄さん」「車」などの普通の言葉を教えた方がムダがなくていいと言います。子どもには言いにくいように思うのですが…。
クリニカさん(1歳 男子)
親野先生からのアドバイス
拝読しました。
結論から言うと、赤ちゃん言葉を使ったベビートークの方がいいです。
つまり、「犬」より「わんわん」、「お兄さん」より「にいに」、「車」より「ぶうぶ」、「ご飯」より「まんま」、「片づけ」より「ないない」の方がいいのです。
赤ちゃん言葉で話しかけられるほうが「言葉への意欲」や「語彙力」が向上することが研究で明らかに
これは学術的な研究ではっきりと結論が出ています。
アメリカのワシントン大学とコネチカット大学の共同研究によって、赤ちゃん言葉で話しかけられた赤ちゃんの方が、早く、かつたくさんの言葉を覚えるということがわかっているのです。
研究では最初に、1才児26人とその親を観察しました。
すると、その時点で既に、親が赤ちゃん言葉を使っている子の方がよく喃語が出るということがわかりました。
「喃語」とは、「あぶう」「あう」「まむ」「ばぶばぶ」「あむあむ」「まんまん」など、赤ちゃんが発する意味を伴わない音声のことです。
これは、赤ちゃんが意味のある言葉を発する前の段階であり、言葉への意欲の表れでもあり、練習の意味もあります。
そして、次に子どもたちが2才になった時点で再度調査をしました。
すると、親が赤ちゃん言葉を使って話しかける機会が多かった乳児は、平均で433の言葉を獲得していました。
それに対して、親が赤ちゃん言葉で話しかける機会が少なかった乳児は平均169語の言葉でした。
つまり、前者は後者の約2.6倍の語彙力なのです。
平均で約2.6倍ですから、圧倒的な差といえます。
赤ちゃん言葉は真似しやすく、言葉を話す喜びを感じられる
なぜこうなるかは、子どもの気持ちになってみればわかります。
例えば、親が「わんわん」と言えば、それを真似して子どもが「わんわん」と言えます。
そして、親がにっこり笑いながら「わんわん。言えたねえ」と言ってくれればうれしいですよね。
子どもの気持ちとしては、「うまく言えた。楽しいなあ。もっと言ってみたい」となるはずです。
こういう喜びが言葉の獲得意欲につながります。
ところが、親が「犬」と言っても、その発声は難しいので子どもは真似して言うことができません。
あるいは、既に「わんわん」と言える子が「わんわん」と言ったとき、親が「わんわん」と返さずに「犬だよ。犬!」と返したらどうでしょう?
子どもは、「あれ?違っちゃったかな?なんだか難しいな。楽しくないな」となるはずです。
これでは、言葉の獲得意欲が下がってしまいます。
ベビートークで赤ちゃんのコミュニケーションへの意欲が高まる
こういったことを親たちは本能的に知っていて、赤ちゃんに話しかけるときは、自然に赤ちゃん言葉になってベビートークで話しかけることが多いです。
例えば、「パパでちゅよ。にいにもいるよ。ねえねもいるよ。ああ、わらったあ。あら、あら、ご機嫌でちゅねえ。楽ちいでちゅねえ」というように。
同時に、目を大きく見開いて、口角をたっぷり上げた満面の笑みで、表情豊かに話しかけます。
このようなベビートークで話しかけると、赤ちゃんの意識を引きつけることができます。
普通の話し方よりもベビートークの方がはるかに赤ちゃんの反応がよいのです。
赤ちゃんとしてはうれしいでしょうし、それによってコミュニケーションへの意欲も高まります。
このようなわけで、赤ちゃん言葉をつかったベビートークが、赤ちゃんの成長にとてもよい影響を及ぼすのです。
こういったことを親たちは本能的に知っているはずなのですが、人間の常として理屈を優先すると、「最初から普通の言葉を教えた方がムダがなくていいのではないか」と考えてしまうのです。
大人の理屈よりも、子どもが楽しく幸せと感じられることを優先させて
ちょっと話を広げると、親や大人の理屈優先で子どもが楽しくなくなり、結果的に子どもによくない影響を及ぼすことが、子育てや教育では非常によくあります。
例えば、しつけのために叱りすぎて、子どもが自己肯定感を持てなくなったり、親子関係が崩壊したりといったようなことです。
何事においても、とにかく、子どもが楽しい、愉快、楽、気持ちがいい、幸せと感じられるようにしてあげることが大事です。
つまらない、不愉快、苦しい、嫌な感じ、不幸せなどと感じられる状態は、何事においてもよくない結果をもたらすことが多いです。
私ができる範囲で、精一杯提案させていただきました。
少しでもご参考になれば幸いです。
みなさんに幸多かれとお祈り申し上げます。
- 育児・子育て