通信制高校が「不登校のセーフティーネット」を超え、いまや「最先端の学び方」と称される理由とは?
- 育児・子育て
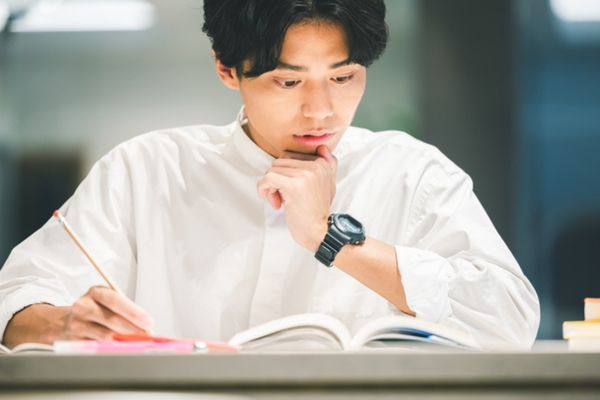
これまでの学校教育の枠を超え、子どもたちが自分らしく学び成長できる場としていま注目を集めている通信制高校。かつて担った限定的な教育機関という役割を超え、よりポジティブな選択肢として認識されるようになりました。
時代の変化とともに教育のあり方にも変化が問われる昨今、子どもたち一人ひとりの個性や状況に寄り添う教育を推進する通信制高校は、そのニーズを柔軟に満たす存在として注目されているのです。
この記事では通信制高校がどのように進化してきたのか、その仕組みや学び方、そして選び方のポイントを解説します。通信制高校の現状について、ぜひアップデートしてみてください。
なぜいま、通信制高校が注目される?時代の変遷と共にポジティブな側面が明確化
通信制高校の歴史は、昭和時代に勤労学生のための教育機関としてスタートしています。当初は働きながら学ぶ人々を支援する役割を担い、やがて時代の変遷とともにその役割を終えると予想されていたなか、実際には平成時代に生徒数が増加に転じています。増加の背景に通信制高校が「不登校のセーフティ-ネット」としての新たな役割を持つようになったことが挙げられ、「好きなことを自分のペースで学べる」として、むしろ「時代の最先端の学び方」としてポジティブにとらえられるようになっています。それを裏づけるようにして、毎年生徒数が約2万人(※)ずつ増えているとされます。
さらに、不登校生の増加が通信制高校生数に影響していることのほかに、教育機会確保法の成立が大きく関係しています。この法律で「不登校は問題行動ではない」と定義されたことで、「不登校が子ども個人の問題ではなく、環境としての社会に課題がある」という考え方に社会がシフトする要因となっています。
それにより、少しずつ社会全体で前向きに学びを支援する空気が広がり、時代と共に社会の受け止め方も変化を遂げているわけです。

また、教育の一律化が実社会と乖離していることも見逃せません。現代の子どもたちは、自由にタブレット端末でYoutube等を見たり、好きなことを好きなときに行える生活環境にある一方で、相変わらず学校教育では、時間割で一律に決められた学び方が求められています。このような環境が合わない子どもたちが増えていることも、通信制高校が注目される理由のひとつになっています。
通信制高校の仕組みと学び方について理解を深める。気になる学費は?
通信制高校の仕組みは、大きく3つの形式があります。
1. 通信制高校単体での高卒資格取得
単独型の卒業率は決して高くなく 、自主的な学習が求められるため難易度が高い形式
2. 通信制高校+学校運営の通学コース
通学コースを設け、レポート作成や学習をサポートする形式。通学を通じて学びを補助する仕組みが特徴
3. 通信制高校+サポート校(民間事業者による運営)
サポート校が通信制高校と連携し、学習支援や進路選択の補助を行う形式。eスポーツや起業教育など、多様な学びを提供するサポート校も登場
通信制高校の学び方として、インターネットを活用した通信教育のほか、単位取得に必要となるスクーリングがあります。主にレポート作成の指導を受けるスクーリングは、公立私立によって頻度は異なりますが、最近は週に数日と頻繁に通える形式も人気となっています。
スクーリングは対面授業が必要で、集中型(合宿型・通学型)と定常型とがあります。特に私立通信制高校では動画授業を活用し、5日間から10日間程度の日数に減免されているところが多いことも特徴的です。
また、レポート作成と聞くと難易度が高そうな懸念もされますが、実際には記号問題が中心となっており、動画授業を活用して取り組むことできるため、心配しすぎる必要はありません。

さらに、気になる通信制高校の学費については、私立通信制高校の場合、就学支援金の対象となりほぼ無償化される方向に進んでいます。ただし、学校が運営する選択コースやサポート校は就学支援金の対象外であるため、これらの費用は自己負担となる点に注意が必要です。
「通信制サポート校」は、通信制高校と連携して民間事業者が運営しており、通信制高校の生徒が学習を進めやすくするための補助的な役割を果たしています。このサポート校にもさまざまな形式があり、学校によっては授業料が一コマごとに加算される形式があり、年間で200万円~300万円といった高額になるケースもあるため、事前に詳細を確認することが重要です。
通信制高校の選び方3つのポイントを知ることで、子どもにとってよりよい選択ができる
通信制高校を選ぶ際のポイントとして、以下の3点を挙げます。
1. 子どもの個性と合う環境を探す
子どもの現在の困りごとや弱みなどを整理して、合う環境の学校を選ぶことが大切です。 たとえば、「人が多い環境が苦手」という子どもに対しては、少人数制の学校や個別指導が中心の学校を選ぶと良いでしょう。
2. 得意分野や興味を活かした選択
「プログラミング」「料理」「ゲーム」「絵を描く」といった子どもの関心事がある場合、そうした好きなことを基準に学校を選ぶことが将来の可能性を広げることにつながります。
好きなことを学びに結びつけることは、興味を深め、社会で活躍する力を育むことができるからです。
3. 子どもの意思を尊重する重要性
子ども自身が「自分で選んだ学校だ」と感じられることがなによりも重要です。学校見学会や体験会に参加し、先生と話をして直感的に「ここが良い」と感じる学校を選ぶことが望ましいです。子どもが主体的に選んだ学校であれば、責任感や自己決定力が育まれるので先々に良い影響を期待できます。

高校・大学進学がゴールではない。「子どもの個性と学び方」を鍵に考えること
今回の記事では、通信制高校の最新事情や選び方のポイントを解説しました。通信制高校は多様な学び方や進路の選択肢を提供しており、子どもの個性や状況に合わせた柔軟な対応が可能です。
長い人生において高校や大学進学だけを目標とせず、その先の人生を自立して生きていくためには、子どもの弱みと認識していることを強みに変える視点を持つことが大切です。子どもにとって最適な進路を選ぶには、早めの情報収集を開始しアップデートしながら準備を進めていきましょう。
(※)
出典:
文部科学省 学校基本調査(令和6年度)

- 育児・子育て
















