思春期の子どもの不登校。心とからだには一体なにが起きている?変化の理由から考える対応とは【加藤 弘通先生に聞く≪思春期と子ども≫ 前編】
- 育児・子育て

気づけば子どもが「ウザい」「エグい」ばかり多用するようになった気がする…。言葉が減って会話が続かなくなり、やけに態度も反抗的。保護者としてどう接したらいいかわからないだけでなく、思わずムカっとくることも珍しくないかもしれません。
思春期を迎えた子どもが心身ともに変化していく一方で、保護者がこれまでの関わり方に戸惑いを感じることが増える時期でもあります。子どもに起きている変化の中身を知ることで、親としてどのようにコミュニケーションを取ればよいかが見えてきます。本記事では、発達心理学の専門家である北海道大学大学院 教育学研究院の加藤 弘通先生にお話をお聞きし、思春期の子どもに起きる事実を解説し、親子がより良い関係を築くための具体的な方法を前後編にわたってお伝えします。
4月から6月は環境変化への適応が難しいタイミング。さらに「社交性と協調性」という性格はどう影響する?
加藤先生の研究室でわかっていることとして、「 “中1ギャップ” と呼ばれる小学生から中学生へ進級するこの時期は、不登校などさまざまなことが表面化してくる」とし、中学1年生は小学校から中学校への移行を経験しますが、いくつかの出身校から同じ中学校へあがったときに、規模の小さい小学校出身の子どもは適応に苦労する傾向があるそうです。ほかに、発達に気になる特徴を持っている子どもの場合も4月の出だしは不適合になるリスクが高まりますが、いずれの場合も一時的で、1ヶ月ほどで収まっていくことが多いようです。
これらは、「今までと違う環境に行くことで、誰に相談したらいいのか、どこになにがあるかわからないという状況により “不確実性” が高まる。不確実性が高まると、自分が持っている特徴があらわになりやすいという脆弱性が現れる。つまり、環境が大きく変わるときに弱さが出やすい人たちが一定数いる。適応に苦労した結果として、行きしぶりや不登校につながる可能性が高い」と加藤先生は説明します。
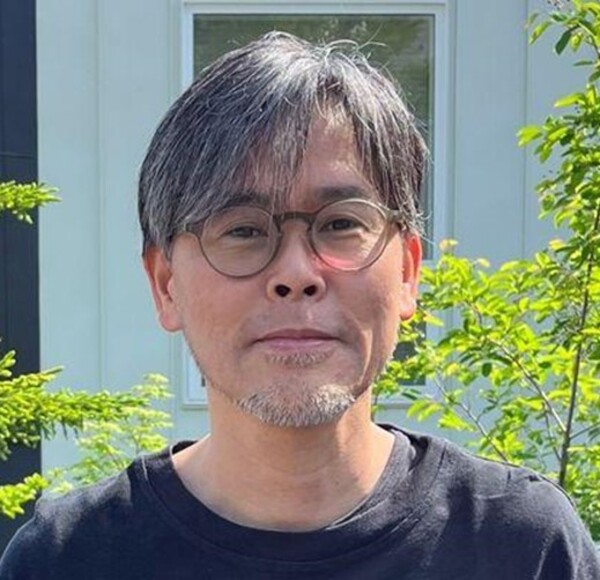
発達心理学の専門家の加藤 弘通先生は、
中学生男子のお父さんでもある
そうした小規模小学校の出身、発達に特徴がある場合といった少数派の子どもたちは、この時期に困ったことがあった際に「この人(保健室の先生など)に聞けばいい」とか「ここに行けばいい」などわかっていると、それだけで救われることもあります。こうした環境要因に加えて、不適合に影響する「性格の特徴」もあることがわかってきました。
「社交性とは人とかかわることが得意な人たちで、人と合わせるのが得意なのは協調性。彼らは4月の不確実な状況のなかでも、変化に合わせながらうまくやっていくことができるが、実は6月くらいから社交性の効果が減っていく代わりに、協調性の効果はつづく傾向にある」。新しい環境で自分のなかにある社交性をフル活用していた子も、6月あたりには人間関係がかたまっていき、だんだんと信頼がベースとなっていきます。そのときに社交性を武器にしていた子たちが、それだけでは乗り越えていけなくなると「学校に行きたくない」という傾向になることもあるのだそうです。
緊張した新学期が過ぎ、社交性は見方を変えると「調子がいい」と受け取られ、それだけでは行き止まりになってしまうこともあるそうです。こうした、時期による不適合リスクに加えて思春期が重なることで、子どもの言動はさらにこれまでと大きく変わっていくのです。
ついイラっとする子どもの受け答え、実は物事を論理的に見られるようになった成長の証
「家で全然しゃべらなくなった」、「反抗的な態度ばかりで頭にきてしまう」。思春期の子どもの変化に戸惑うことは、ごく自然なことです。つい、思春期を反抗期と同意で考えてしまいがちですが、加藤先生によると思春期におけるもっとも重要な変化は「論理的に物事を見られるようになること」だと言います。
「たとえば、親が子どもに “うるさい!” と言ったら子どもから、 “おまえの方がうるさいじゃないか” とか言われたりする。これは実は子どもが正しいと言える」。想像しやすいケースとしては、子どもにズバッと正論で返されたとき、大人は急に話を変えて「そんなにえらそうなことを言うなら、自分の飯代くらい自分で稼いで来い」というような返事をすることがあるかもしれません。
「子どもは論理的なのに、大人が非論理的な例。大人はどうしても権威的になってしまいがちだ」としつつ、「論理的な観点で子どもが話しているとき、その内容が正しくても言い方がキツくて傷つけたりする。言い方に気をつけてみよう、と先生や大人の立場からは返してみてあげてほしい」。せっかく本質的には良いことを言っていても、素直に受け取れない言い方や誤解を生む言い方を子どもがしていることが多いので、保護者は思わずカッとしてしまうのです。

言葉が極端に減る時期にも子どもたち同士では、「ガチとえぐ、だけで会話が成立してしまっていて、こちらはなにを言ってるのかさっぱりわからない。ではどうすればいいか?と言えば、もうちょっと具体的に教えてくれない?と聞くしかない」と、加藤先生も中学生のお子さまとの実体験を例に教えてくれました。
「大人は忙しいから “なにいってんの?” と片付けてしまうことが多いが、おそらく言葉が足りないだけで、子どもはなにか理屈立ったものを伝えようとはしているはず。意味ないと投げ捨てずに、もうちょっと詳しく聞かせて、と大人が歩み寄ることは大切だ」とし、大人側が「わからない」や、「知りたいから教えて」ときちんと子どもに言えるということは、裏を返すと子どもを対等に扱い始めていることを伝えることにつながるのです。
また、不登校の場合、子どもが論理的なことを述べたとしても、時に「学校も行っていないのに、正論だけは言って…」となりがちです。しかし、正論を言うことと不登校は本来、別物ですので、その正論に耳を傾け、どうしてあなたはそう思うのか、そして保護者として私はどう思うのか、互いを知り合うきっかけにしていくことが大切です。
大人だって思春期に試されている。「わからないから教えて」から始めてみよう
加藤先生は「思春期は子も大人もお互いに試されてる時期」であるとし、なにを尋ねても「別に」「ふつう」「どうでもいい」ばかり返してくる子どもに対して、いかにあきらめず「あなたはふつうだと思うんだね。でも私はよくわからないからもうちょっと教えてほしい」と言ってみることを薦めており、意外になにか反応が返ってくるかもしれません。
話をしてくれない、返事をしない、と終わりにせずに、大人が少しがんばってみる。
一方で、子どもが論理的な視点を手にいれはじめるこの時期から、さまざまなトラブルが増えることも事実です。
後編では子どもが「世界をどうとらえているか」という認知の変化について解説していきます。

- 育児・子育て
















