子どもの叱り方、大丈夫?心理学から考える「子どもの心に響く伝え方」で、叱る回数を減らそう
- 育児・子育て
「何度叱っても同じことをする」「叱ってばかりでつらくなる」など、子どもを叱るのは難しいと感じる保護者のかたも多いのではないでしょうか。アメリカやイギリス、オランダで心理学を学び、子育て心理学が専門の佐藤めぐみ先生に、「子どもの心に響く叱り方」についてお話を伺いました。
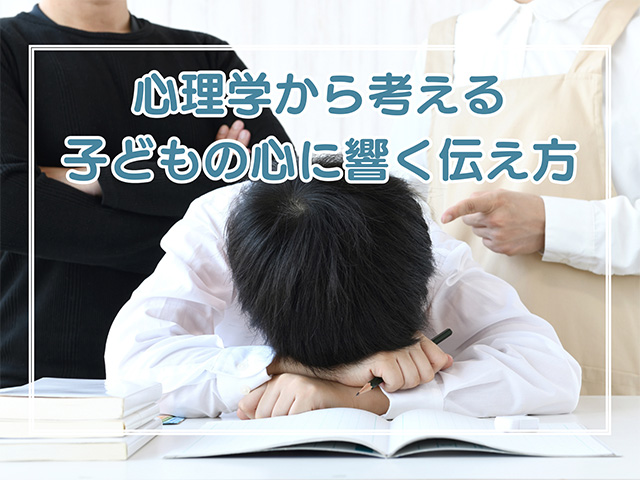
叱られる経験は自制心を育む
佐藤先生:私が受ける相談でも、保護者のかたが子どもの叱り方に悩み、育児ストレスを抱えてしまっているケースがよくあります。そもそも叱ることで悩む背景には、最近の風潮として、「子どもをまるごとすべて受け入れてあげなくてはいけない」、「子どもを叱ることで傷つけてしまうのではないか」といったことを、おうちのかたがすごく気にしてしまい、本来叱るべきところでも叱らずに過ごし、その結果子どもが家庭の中で力を持ち、少し大きくなってからコントロールが効かなくなってしまうというケースが多いように思います。
「叱らない子育て」とは、響きがよく、保護者としても取り入れたいと思いますが、言葉通りただ叱らないだけでは、その子自身が、自分を自制する力が育めません。小学校に入学すると集団行動にともない、我慢する機会も増えますが、小さい頃に自分を自制する力を身につけてきた子とその経験の場数が少ない子とでは、ここで大きな差が出てきます。我慢する経験が少ない子は、自分の思った通りにできないことでクラスになじめなかったり、先生に注意されてばかりだったりで、学校生活にやる気をなくしてしまうこともあります。
叱ることと叱らなくてもいいことは明確に区別する
佐藤先生:私は叱るべきことと、叱らずに学んで習得していくべきこととは、分けて考えた方がいいと思っています。叱るべきこととは、即介入した方がいいこと、例えば自分自身を傷つける、相手を傷つけるというのは、すぐに注意したほうがいいです。
一方、叱るより少しずつ教育していくほうが合っているのは、”習慣”として定着させていきたいもの。たとえば勉強や習い事、あとは歯みがきやお着替えなどの自立行動です。叱って無理やりやらせるよりも、少しでもできている行動をほめたり認めたりしていくほうが、モチベーションが保ちやすいため、結果的に早く習慣化できます。
「勉強をしなくて困っている」というときに、ランドセルからその日の宿題を出したこと、それをテーブルに持ってきたこと、これらは保護者からしたら、「ほめるほどのことではない」かもしれません。5分間だけドリルに取り組んだくらいでは「たいしたことはない」という気がしてしまうでしょう。でもそこも「宿題を終わらせる」という目標行動の一環であり、大事なスタート地点でもあるのです。
人間は今やっている行動を認めてもらうと、それを継続したいという心理が働きやすいので、習慣化していきたい行動の”芽”を見つけ、そこから育んでいけると望ましいです。たとえば、「ランドセルから出して持ってきたのね」「1問目、ちゃんと解けているよ」「昨日よりスピードアップしたね」など。できている行動を保護者が言語化していくことで、「ママ・パパが見てくれている」という気持ちも満たせるので、心も安定しやすくなります。大人もそうですが、習慣というのはコツコツたどり着くものなので、「叱りルートではなく、ほめルートでたどり着けないか」と検討できるといい導きにつながりやすいです。
子どもは「言われたこと」より「自分の身に起こったこと」から学ぶ
佐藤先生:子どもは自分の好きなことをするのが大好きです。嫌いなことはやりたくありません。それは人間の本能なのですが、好き放題にしておいてよいのかと言われれば、どこかで自分で自制する力を身につけていかなくてはいけません。
—子どもが叱られても何度も同じことをしてしまうのは、心理学的には満足遅延耐性が備わっていないこと、バウンダリー(境界線)がうまく提示できていないことが考えられます。
満足遅延耐性を身につけるには、ちょっとした我慢が大事
佐藤先生:「満足遅延耐性」とは、例えばダイエットをする時に、2週間甘いものをやめることで、3キロ減量した自分を想像し、今は我慢する、といった力です。この力は成長すれば一律に身についているわけではなく、大人でも幅があると思います。子どものうちは、どうしても「今」やりたいことを優先してしまいがちですが、ちょっと我慢するという経験の場数を踏むことで、身につけていくことができます。
実現可能なバウンダリー(境界線)で、保護者の言葉が子どもに届く
佐藤先生:またバウンダリー(境界線)というのは、ここまではいいけれどここからはダメだという線のことです。例えば子どもが部屋を散らかしっぱなしにしていた時に、「いつもこんなに部屋を散らかして!おもちゃ全部捨てるからね!」と子どもを叱ったとします。保護者は「言えばわかるだろう」と考えているので、それで片づけると思っていますが、子どもは片づけません。なぜかと言うと、子どもは自分の身に起こったことから学んでいるからです。
「散らかしたままでもおもちゃは捨てられない」という経験が重なると、「お母さん・お父さんが言ったことは本当には起こらない」と考えるようになります。ここで何がいけないかというと、バウンダリーが現実的なものになっていないことです。例えば、「おもちゃを片づけなければ捨てる」、というのは実際に行わないわけですが、「片づけなければおもちゃを次の日まで一切使わせず預かる」であれば実際に行動に起こすことが可能です。そういった実現可能な線にすることで、保護者のかたの言葉が子どもに通じるようになります。
また、そういう線を設ける時は、子どもと一緒に決めることをお勧めします。特に小学生以上になれば、例えば、ゲームは〇分、勉強は〇分など、子どもと一緒に決めていきます。親子で話し合いを設けて、両者がアグリーメント(合意)したバウンダリーを作っていくことで、叱る回数を減らしていけます。
子どもの心に響く叱り方 3つのポイント

佐藤先生:子どもを叱る時には、次の3つのポイントに気をつけると、伝えたいメッセージが子どもにきちんと伝わるようになります。また叱ることで溜まってしまうおうちのかたのストレスも、叱り方を変えるだけで減らすことができます。
ポイント① 今のことだけを言う
保護者としては「昨日も片づけなかった」「いつもいつもゲームばかりして」など、これまでのことも持ち出して叱りがちですが、これは叱り方としてはあまりよくありません。なぜなら、内容がぼやけてしまい、子どもは何を叱られているかがよくわからなくなるからです。
ポイント② 話を広げない
叱りだすとあれもこれも言っておかなきゃとつい話を広げがちですが、それも先ほどと同じ理由で効果的ではありません。内容は1つに集中させた方が、子どもは理解がしやすいです。
ポイント③ 〇〇な子と言わない
言葉は時に武器になってしまうこともあります。「そんな悪い子はうちの子じゃない」といった叱り方では、子どもがとても傷つきます。そういう場合は「言葉を調整する」ことが大事で、今ある行動をどうしたいかということだけ盛り込み、シンプルに叱ることを心掛けてみてください。
「そんな悪い子はうちの子じゃない」とその子自身を攻撃せずに、「それをやるのはダメ」と行動を指摘すれば、自己肯定感は低下しません。直して欲しいのはその子の行動だということをいつも頭に置き、正しい行動が取れるような具体的な言葉で「何をすればいいのか」を伝えていくことを意識して欲しいと思います。
まとめ & 実践 TIPS
叱っても子どもの心に響かないのは、保護者のかたの言葉と子どもの経験が一致していないことや、我慢する経験が少ないことなどが関係しているようです。また叱る時は「今」のことだけをシンプルに、ほめる時はあれもこれもと、どんどん広げていくことで、自己肯定感を高められるそうです。
- 育児・子育て















