【専門家監修】人見知りは成長のサイン!個性を大切にしながら保護者ができること
- 育児・子育て

知らない人を見て、恥ずかしがって隠れたり、泣いたりしてしまうお子さまの「人見知り」。人見知りは個人差が大きいため、「人見知りが激しすぎて心配」「人見知りしなさすぎて大丈夫?」など、保護者のかたのお悩みもさまざまでしょう。
今回は、子どもの人見知りの要因や人見知りをしない子の特徴、また人見知りについて保護者のかたができることなど、和洋女子大学家政福祉学科 佐藤有香先生にお話しいただきました。
そもそも人見知りって? いつから始まる?
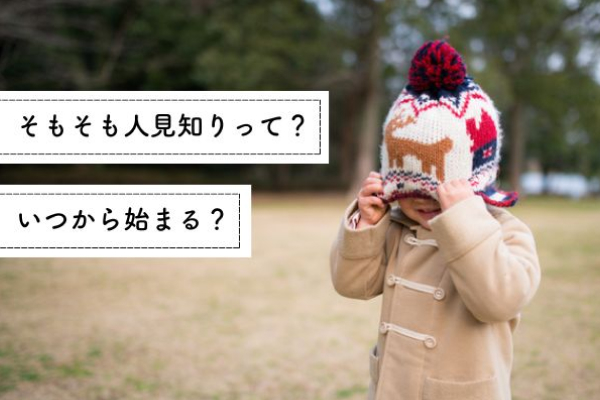
子どもの成長段階によって、人見知りをする要因は異なります。乳児期の人見知りと、幼児期の人見知りの違いを見てみましょう。
初めての人見知りは生後6か月~8か月ごろ
初めての人見知りは、生後6か月~8か月ごろから始まるといわれています。この時の人見知りは、8か月不安とも呼ばれ、人の顔を認識できるようになり、保護者のかた以外の見慣れない人が近づいてくる時に感じる不安が要因になります。
たとえば、「ママ以外の人に抱っこされたら泣く」のは、ママの顔を認識できているからこそで、知らない人に抱っこされると恐れや不安を感じ、泣いてしまうのです。これは、養育者との特別な関係を築き始めたことで、成長の過程であり、大変喜ばしいことといえるでしょう。
1歳半~2歳ごろの人見知りは自我が要因に
次に、1歳半~2歳ごろの人見知りは、自我が芽生え、自分が周りの人にどう見られているかを意識することにより表れます。
たとえば、「誰かに声をかけられると保護者のかたの後ろに隠れてしまう」のは、
声をかけてくれた人を意識してしまうからです。
「ママとパパにべったりで祖父母にさえ懐かない」などがあると、気まずかったり心配になったりする保護者のかたもいらっしゃるかもしれません。しかし、1歳半~2歳ごろの人見知りも、自我の芽生えという成長の証なので、安心して見守ってくださいね。
乳児期の人見知りも幼児期の人見知りも、個人差が大きいため、過剰に心配する必要はありません。お子さまの成長の過程だと、大きく構えていましょう。
人見知りをしない子どもがいるのはどうして?
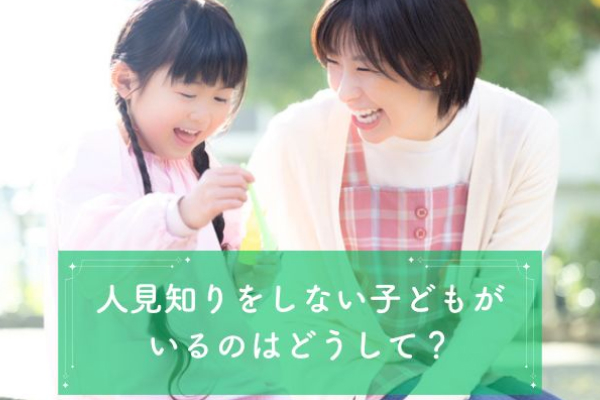
人見知りの程度にも差があり、中にはほとんど人見知りをしない子どももいます。どうして人見知りをしないのでしょうか。
普段からたくさんの大人と接する機会がある
大家族であったり、小さいころから大勢の人に会う機会が多かったりすると、人と接することに慣れていて人見知りしにくくなる可能性があります。さらに、いつも優しく肯定的に周りに接してもらっていると、より他者に対する抵抗が少なくなります。
その子の気質や性格
大人でも、社交的ですぐ誰とでも仲良くなれる人がいれば、人と話すことが苦手ですぐに緊張してしまう人もいます。また、他者に興味がある人もいれば、まったく興味がないという人もいらっしゃるでしょう。
それと同じで、性格や周りへの興味・関心の持ち方は、子どもによって違いがあり、個人差があります。人見知りをしない子は、その子自身の気質や性格によるところもあるでしょう。
「人見知りが激しすぎて心配」「人見知りをしなさすぎて心配」保護者のかたができることは?

前述したとおり、人見知りは個人差が大きいです。「人見知りが激しくて心配」という保護者のかたも、「人見知りをしなさすぎて心配」という保護者のかたもいらっしゃることでしょう。ここでは、人見知りへの心配に関して、保護者のかたができることをご紹介します。
人見知りが激しいお子さまは、ゆっくり慣れる機会をつくろう
人見知りが激しいお子さまにおすすめなのは、ゆっくり時間をかけてさまざまな人と関わり、慣れる方法です。
保護者のかたから始まり、次に祖父母、少し慣れてきたら近所の子育て広場へというように、段階を踏み、ステップアップしていくのがよいでしょう。また、子育て広場のような、同年代の子どもがいる場所に通うことは、同じ場所や同じ職員さんという安心感がありつつも、初めての人にも出会えるため、お子さまの気持ちの負担を減らしながら、人に慣れる機会になります。
無理に人見知りを克服しようとしなくても、穏やかに少しずつ社会と接する機会をつくれば、自然と落ち着いていくことが多いです。
人見知りをしないお子さまには、社会のルールや危機管理を教える
幼児期のお子さまは、常に誰かと一緒にいる状態なので安心かもしれませんが、少し大きくなると人見知りをしないがために「知らない人について行かないか」「さらわれないか」と心配になる保護者のかたもいらっしゃるでしょう。
また、知らない人にグイグイ話しかけて、困らせてしまうということもあるかもしれません。そこで、人見知りをしないお子さまには、知らない人とお話しをする時の心がけや、危機管理について教えておくと安心です。
たとえば、
・人に話しかけた時は、相手の反応を見ること
・どんな理由があっても、知らない人について行かない
・できるだけ一人にならない
・防犯ブザーを常に携帯し、使い方も練習しておく
などを伝えておくと安心でしょう。
まとめ & 実践 TIPS

人見知りは、認知能力や自我の芽生えなどの成長の表れのため、大変喜ばしいことです。
また、成長し経験が増えることで、人との付き合い方や距離感を覚えて自然と落ち着いていくことも多いため、多少人見知りが激しかったり、まったくなかったりしても、過剰に心配することはありません。
保護者のかたができる対応策も試しながら、優しく見守ってみてください。もし、それでも心配事がある時は、専門家に相談してみるのも一つの手です。
編集協力/海田幹子、Cue`s inc.
- 育児・子育て














