子どもが恥ずかしがり屋になる原因と、一歩を踏み出す方法とは?保護者のかたのリアルな声も紹介!

「人前で話すのが苦手」「新しいお友達となかなかなじめない」といったことがよくある「恥ずかしがり屋」のお子さま。
慎重に相手を見て発言ができる、親しい人には心を開けるといった点を魅力的に思いつつも、「もっと積極的に人とコミュニケーションをとったほうがよいのでは?」と感じている保護者のかたもいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、恥ずかしがり屋になる原因と、一歩を踏み出すための方法を、和洋女子大学家政福祉学科 佐藤有香先生にお話しいただきました。
恥ずかしがり屋ってどんな子? 内向的との違いは?

年齢によって違う「恥ずかしがる理由」
「恥ずかしがり屋」とひと言でいっても、実は恥ずかしがる理由は、成長によって変わります。
まず、「恥ずかしい」という感情が芽生えるのは、2~3歳くらいといわれています。他の人から自分がどう見られているかを認識できるようになるため、「周りの大人に注目されたらモジモジする」などの恥ずかしがる様子が見られるのもこのころからです。
4~5歳では、自分と他者との比較ができるようになり、「できる・できない」または「自分とは違う」などの事実や気持ちから恥ずかしさが芽生え、「お遊戯会でのソロパートを恥ずかしがる」などの様子が見られるお子さまもいます。
小学校以降での恥ずかしさは、社会的な経験や他者との比較の中で表れます。たとえば、「一度授業で手を挙げて発表したら、まちがえてそれを周りにからかわれたため、恥ずかしくてもう手は挙げられない」などが当てはまるでしょう。
思春期に差しかかると、さらに「みんなと同じがいい」「自分を表に出しにくい」などが加わり、「周りと違っていたら恥ずかしい」となることがあります。
「内向的」との違いと恥ずかしがり屋の特徴
恥ずかしがり屋とよく似ている「内向的」は、本人の気質を指し、その人が持って生まれた個性で、先天的なものです。一方「恥ずかしがり屋」は、自身の学習や経験にもとづき形成される後天的なものとされています。
恥ずかしがり屋の特徴には、以下のようなものがあります。
・初対面の人と話すのが苦手
・目立ちたくない
・人との付き合いに慎重
ただ、ひと口に「恥ずかしがり屋」といっても、やることなすこと全部が恥ずかしいということはなく、「大勢の前での発表」や「初対面の人と話すこと」など、特定の分野や行動が恥ずかしいということが多いです。
また、恥ずかしがることは決して悪いことだけではなく、周りの人をよく見たり、話を聞いたりすることが得意な傾向にあり、「協調性がある」「お友達とのトラブルが少ない」などの長所もあります。
子どもが恥ずかしがる原因にはどんなものがある?
子どもが恥ずかしがる原因はさまざまですが、ここでは大きな3つの原因をご紹介します。

1.失敗した経験
「人前で発表し、まちがえてしまった時に、他の人から笑われた」などのように、失敗した経験がもととなって、恥ずかしさを感じるようになることがあります。「あの時みたいに失敗したら……」と考え、萎縮してしまい、積極的に取り組めなくなってしまうのです。
2.周囲の大人たちの過度な干渉
保護者のかたを始めとする周りの大人たちの過度な干渉も、お子さまが恥ずかしがる原因となり得ます。
お子さまが自発的に何かをしようとした時に、つい手や口を出しすぎると、お子さまの心の中に「自分だけでは何もできないんだ」という気持ちが生じ、考えや行動をすることに消極的になってしまう場合があります。
自己評価が低くなると、人前が怖くなったり、恥ずかしがったりすることにつながりやすいでしょう。
3.経験が十分でない
恥ずかしがる原因には、単に経験の積み重ねが足りていない時もあるでしょう。「人前での発表」であれ「初対面の人との会話」であれ、経験する機会が十分でないばかりに、チャレンジしたらできることでも、「できない」という不安が生まれ、尻込みをして恥ずかしがるという結果につながるのです。
恥ずかしがり屋のお子さまが、一歩踏み出したくなる保護者のかたのサポートとは?
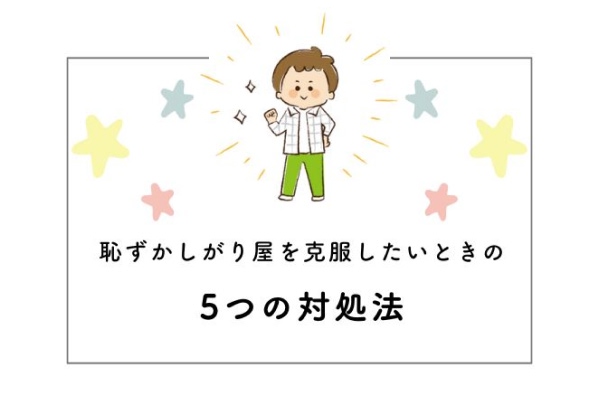
お子さまは少し「恥ずかしい」と思うかもしれませんが、勇気を持ってあえて一歩を踏み出してみると、ぐっと成長できる場面もあります。
恥ずかしがり屋のお子さまにとって、保護者のかたの関わり方や周りの人の対応は、大きな勇気になります。ここでは、保護者のかたがお子さまにできるサポートを5つご紹介します。
【対処法1】得意なことを伸ばして自信を持てるようサポートする
恥ずかしがるお子さまには、お子さま自身の得意なことを伸ばして、自信を付けられるようサポートするのがおすすめです。自信が持てるようになると、周囲の視線が気にならなくなったり、何事にも積極的に取り組めるようになったりします。
お絵描き、ダンス、歌、縄跳び、かけっこなど、お子さま自身が没頭していることを伸ばしてあげてください。「上手にできたね」などと認めるだけでも、お子さまはどんどん自信を付けていくでしょう。
【対処法2】目標を掲げ、達成感を味わえるようサポートする
目標を掲げ、達成感を味わうと、自信が付き、恥ずかしがることの克服につながります。大きな目標だと達成するまでに時間がかかり、息切れしてしまう可能性があるため、まずは小さな目標を設定するとよいでしょう。
たとえば、家庭内の目標であれば……
・家の中のごみ集め
・回収したペットボトルつぶし
・お風呂そうじ
など、自分のためだけでなく、家族の役に立つ手伝いがおすすめです。
学校でのことは……
・毎朝クラスの友達に「おはよう」と声をかける
・次の日の学校の準備を一人でする
・上履きを自分で洗う
そのほか、ご家庭の中のことや、学校でのこと、お子さまがやりたい習い事など、チャレンジしやすいものから選ぶとよいでしょう。
【対処法3】経験して慣れるようサポートする
どんな時に恥ずかしがるのかを知り、その分野の経験を積んで慣れるのも一つの手でしょう。その時に大切なのが、少しずつ慣れてもらう点です。
たとえば、「一人で大勢の前で発表をすること」を恥ずかしがり、話すことを苦手に思っているお子さまの例でお話しします。まずは「1日1回仲のよいお友達以外に話しかけてみる」、できるようになれば「1日1回、授業で手を挙げる」というように、最終目標の「人前で恥ずかしがらずに発表をする」に向けて、一歩ずつ進んでいくのがおすすめです。
経験を積み重ねる際は、結果をすぐには求めず、じっくりくり返し取り組んでいくことが大切です。
【対処法4】結果ではなく努力やプロセスを認めるサポートを
いろいろな経験をさせていくうえで、失敗することもたくさんあるでしょう。その時に大切なのは、「チャレンジしたという事実」と「チャレンジのプロセス」を認めることです。
できた・できないの評価ではなく、チャレンジしたこと自体や過程を認めることで、「これからもがんばろう」と思えるでしょう。
【対処法5】お子さまのタイミングを大切にする
お子さまがモジモジしていると、「ほら、早く」とせかしてしまうことがあるかもしれません。しかし、せかしてしまうとお子さま自身のタイミングを逃してしまい、うまく対応できずに自信を失ってしまう可能性があります。
自信を失い恥ずかしがることを加速しないようにするためにも、せかしたい気持ちは抑え、お子さま自身のタイミングを待ってあげるようにしましょう。
保護者のかたが実践している恥ずかしがり屋対処法
そのほか、保護者のかたはこんな方法を実践しているようです。参考にしてみてくださいね。
「とりあえず場慣れさせる! 夏休みを利用して、さまざまな体験や活動に挑戦してもらいました。最初は不安がって一緒にいてとくっついていたけれど、回を追うごとに新しい場所や人と会うことに慣れてきたのか、経験が自信につながったのか、一人でも臆せず参加できるようになってきました」(小学2年生の保護者)
「人前できちんとあいさつができるのに、それ以外はモジモジしてしまう子ども。ある日、子どもから『どうしてお母さん以外の大人は質問しておきながら、私が一番よい(適した)答えを考えている時間を待ってくれずに勝手に解釈して話を終わらせるの?』と質問されました。『恥ずかしがり屋』=『うまく意思疎通ができない』ではなく、会話のキャッチボールをする時間には個人差があるのだと気付き、返答は遅いけれど少し待ってほしいと周りにお願いしました」(中学2年生の保護者)
「ダンスをするのが好きだったので、ダンスを習わせました。10人くらいのダンスチームですが、発表会では大勢の前に立つことになり、何度かくり返しているうちに度胸が付いてきたように思います」(小学4年生の保護者)
※2024年にベネッセが行ったWEBアンケートより
気を付けたいNG対処法は?

お子さまの前で「うちの子、恥ずかしがり屋で」と周囲の人に言う
お子さまが恥ずかしがっている様子を見て、つい「うちの子、恥ずかしがり屋なんです」「恥ずかしがり屋で困ってるんです」と先生やほかの保護者のかたに言ってしまうことがあるかもしれません。
しかし、こうした言葉をお子さまが聞いてしまうと「自分は恥ずかしがり屋なんだ」「恥ずかしがり屋は困る子なんだ」と思い、お子さまがさらに自信をなくしてしまう場合があります。
お子さまが恥ずかしがっていたら、「ママたちに囲まれちゃって恥ずかしいね」のように、子どもの恥ずかしさに共感するのがおすすめです。
失敗をからかったりたしなめたりする
「ほらやっぱり」や「だから言ったじゃない」などの、からかったりたしなめたりする行為は、お子さまの自尊心を傷付け、チャレンジする気持ちを持てなくさせる可能性があります。
また、「私は5歳ではもう逆上がりできていたよ?」のように、保護者のかたの子ども時代と比べる発言も控えたほうがよいでしょう。前述したように、お子さまのペースに合わせ、しっかりとプロセスや努力をほめてあげるのがおすすめです。
まとめ & 実践 TIPS

恥ずかしがることを克服するためには、経験を積むことと、自信を少しずつ持つことが大切です。そのためには、お子さまの慎重な気持ちに寄り添い、できてもできなくても、がんばったことや過程をたくさん認めてあげましょう。
「恥ずかしがり屋は悪いことではない」ということを前提に置き、お子さまが人前でも自然に、堂々と振る舞えるようになる手助けができたらいいですね。
編集協力/海田幹子、Cue`s inc.














