所得制限なしの「高校授業料無償化」はいつから?制度の最新情報と進路選択で気を付けたいポイントを解説
- 高校受験

高校授業料の所得制限なしでの無償化が、2026年度から予定され、注目が集まっています。「言葉は知っているけど、制度の詳しい内容はわからない」「私立も無料?」と気になるかたも多いかもしれません。
高校無償化の最新の制度内容はどのようなもので、進路選択にどのような影響を及ぼすのでしょうか。ベネッセ教育総合研究所・教育イノベーションセンターの小村俊平センター長に聞きました。保護者が知っておきたい学校選びの視点にも注目です。
私立も対象に! 高校授業料無償化はどう進む?

ーー 「高校授業料無償化」の現状について教えてください。
高校授業料無償化は、2010年より公立高校でスタートしました。
私立高校に通う生徒には、「就学支援金」の支給を実施。2020年4月からは年間所得590万円以下の世帯を対象に、年間39.6万円が補助されています。さらに、2025年4月からは、収入に関係なく、国公立・私立問わず、高校に通う子どもがいる世帯に最大年11万8,800円の支援が始まっています。
また、東京都・大阪府では、2024年度より所得制限なしの授業料無償化の独自の支援が実施されています。いずれも通信制も含めた支援ですが、東京都と大阪府で制度に違いがあります。
東京都では、授業料が支援の上限を超えた場合、保護者が超過分を負担。
一方、大阪府では学校が負担し、保護者には負担が発生しない形になっています。
ーー 全国での「高校授業料無償化」の検討はどのようになっているのでしょうか。
現在、自民党・公明党・日本維新の会の3党間で、全国的な授業料無償化に向けた合意がなされています。国公立・私立・通信制すべての高校が対象となる予定で、2026年度からは世帯の収入に関係なく、授業料を最大45万7,000円まで支給する制度が始まる予定です。
《無償化》でも自己負担ゼロではない! 注意すべきポイントとは?

ーー 最大45.7万円まで支給ということは、完全に無料というわけではないのでしょうか。
「高校無償化」という言葉だけが先行してしまいがちですが、完全に無料で高校に通えるというわけではありません。あくまで《授業料》が実質無償になるだけです。
特に私立高校では、入学金・施設費・積立金などの諸費用が別途かかるのが一般的です。
さらに、国が支給する授業料補助の上限額(45万7,000円)と実際の授業料との差額を保護者が負担することになる可能性もあります。
また、公立高校であっても、制服代や教材費などの費用は発生します。「無償化=完全無料」と誤解しないことが大切です。
さらに注意したいのが、補助金の支給タイミングです。
補助金は後日振り込まれるため、入学時などにかかる費用は、まず保護者が立て替える必要があります。制度を正しく理解し、「一時的にでもどのくらいの出費があるのか」を把握したうえで資金計画を立てておくことが大切です。
「高校授業料無償化」で学校選びはどう変わる?

ーー 無償化により、高校選びにどのような影響があると考えられますか。私立高校の人気が高まるのでしょうか。
以前から私立高校に通う生徒が4~6割の東京都や大阪府と、私立高校の数が少ない地方では事情が異なります。無償化が先行した東京都と大阪府では私立高校への進学者が増えましたが、全国的に見た場合には経済的負担が軽減するからといって、単純に私立の希望者が増えるとは言い切れません。しかし、学校選択の在り方が変わっていくことは間違いないでしょう。
まず、無償化によって進路選択における費用負担の不安が減ることから、「行きたい学校に行く」という意識がより高まることが考えられます。人気のある学校に志望者がさらに集まり、倍率が上がるでしょう。人気を集める学校の特長としては、進学実績だけではなく、教育内容、通いやすさ、施設や環境の良さなどが挙げられます。
こうした動きに合わせて、学校側も自校の魅力や教育内容の特色をより積極的にアピールするようになると考えられます。グローバル教育、探究的な学び、デジタル活用などで、特色を打ち出す学校が増えるでしょう。だからこそ、保護者のかたには、お子さまの個性や興味関心に合った学校を見極めて選ぶ視点が、これまで以上に求められるようになります。
近年は、進学実績や偏差値だけでなく、教育内容に注目した学校選択が増えています。通信制高校を選ぶ生徒が1割に達するなど、学び方の多様化も進んでいます。「何ができる学校か」「どんな学びがあるか」といった視点を持ち、お子さまの個性やニーズに合う学校を見つけることが何より大切になるでしょう。
子どもに合った学校を選ぶために、保護者ができることは?
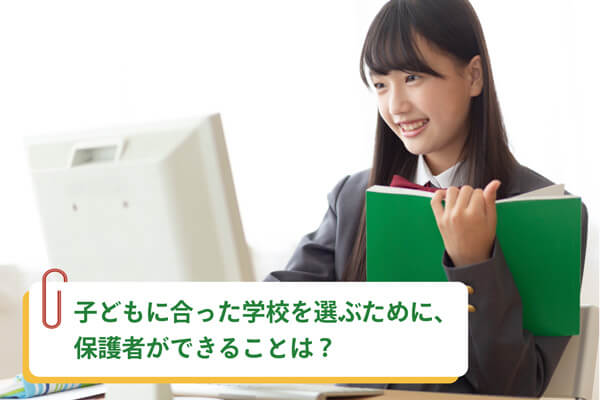
ーー 子どもに合った学校を選ぶといっても、何をどう見ればいいのかとまどってしまいそうです。どう見極めていけばいいのでしょうか。
まず大切なのは、「保護者世代の学校選択」とは大きく変わっていることを自覚することです。大学入試では年内入試と呼ばれる学校推薦型選抜や総合型選抜が増え、高校での教育内容も大きく変わりました。偏差値や進学実績だけに注目していては、ミスマッチが起きる可能性もあります。教育内容や学校の特色をつかむためには、学校サイトの情報や学校見学の機会を活用することがポイントです。次のような観点を参考にしてみてください。
<学校の特色をチェックするポイント>
グローバル教育
- 海外大学への進学実績(欧米だけでなく、アジアの大学等も)
- 短期・交換留学などの実施例
- 英語の資格・検定試験など、語学力に関する具体的な到達目標の有無
デジタル活用
- 授業や宿題でデジタル端末の活用が推奨されているか
- 生成AIなど最新のテクノロジーを取り入れた授業が行われているか
研究・探究的な学び
- 学校内外で研究発表の機会があるか(他校も参加する発表会を主催しているか)
- 第一線で活躍する大学・企業・NPOなどのエキスパートと連携する学びの機会があるか
- カリキュラムや学校ニュースにSTEAM教育(Science<科学>、 Technology<技術>、 Engineering<工学>、Arts<リベラルアーツ>、Mathematics<数学>)の取り組みが紹介されているか
これらの特色を読み解くうえで重要なのが、いかに「外部とつながっているか」という視点です。近年、学校経営のトレンドは《自前主義》から《外部連携》へと変わりつつあります。教育内容が高度化・多様化していくなかで、学校だけでできることには限りがあります。よりよい教育を志向する学校は、さまざまな形で外部の力を活用しようとします。
私立・公立を問わず、よい学校には明確な校風があり、比較的、似たような家庭環境で育った生徒が多く集まる傾向があります。だからこそ、よりよい教育をめざす学校は外部と連携し、生徒が多様な価値観に触れたり、新しい出会いの機会をつくったりすることを考えています。
学校を起点に、「出会ったことのない人や価値観に触れられるか」。
この視点で教育の質を見極めることが、今後ますます重要になっていくでしょう。
ーー 学校見学などでは、どのような点を見ればいいのでしょうか。
学校見学は、実際の教育現場を見て、直接質問ができる機会です。以下のような質問をしてみると、学校の教育姿勢や文化がより具体的に見えてくるかもしれません。
- 卒業生の教員(OB)はいますか?
- → 文化祭に卒業生が顔を出す学校は、母校愛を持った卒業生が育つ学校であり、魅力的な学校といえるでしょう。同じように卒業生が母校に教員として戻ってくる学校も魅力ある学校です。よりよい教育を行うための柱となる教員がいる学校といえます。近年は優れた教員が他校に移籍することは珍しくありませんが、母校で働く教員は長年にわたってその学校を支える傾向があるからです。
- 博士号を持つ教員はいますか?
- → 高度な研究や探究を進めるためには、自前主義に拘らず大学や企業等と連携していくことが不可欠です。その場合でも、学校内に博士号を持つ教員がいると、日常的に生徒の活動をしっかりと支援したり、大学や企業との連携も効果的に進められる可能性が高いといえます。
- 教員どうしで授業を見学・意見交換する機会はありますか?
- → 教員どうしが腕を磨きあう文化がある学校は、生徒どうしが活発に交流し、お互いを高める文化を持っている可能性が高いです。特に教員どうしがお互いの授業を見学しあう学校は、学校内の風通しがよく、チームでの教育力を高めようとしているといえます。
- 教員の校外での活動には、どのようなものがありますか?
- → 講演・研究・論文執筆といった対外的な活動は、教員の学び続ける姿勢を裏付けるもの。学び続ける姿勢は生徒にも大きな影響を与えます。「生徒に〇〇させる」ではなく教員自らが活動することで、生徒が学校内外で自然に手を挙げ、挑戦するようになります。
- 校則はどのように決められていますか?
- → 校則の有無ではなく、生徒が学校運営やルールづくりにどう関わっているかが重要です。生徒が学校にあわせるのでも、学校が生徒にあわせるのでもなく、生徒や教員が一緒に学校をよりよくするために活動しているかどうか。それが民主主義社会を支える根幹となる資質・能力を育むことになるのではないでしょうか。
高校は、さまざまなステークホルダーが関わり、子どもの可能性や選択肢、視野を広げる学びのコミュニティとも考えられます。高校授業料の無償化によって選択肢が広がるからこそ「この学校で何が学べるか」「どんな出会いがあるか」といった視点で、お子さまに合った学校選びをしてみてください。
編集協力/岡 聡子
- 高校受験
















