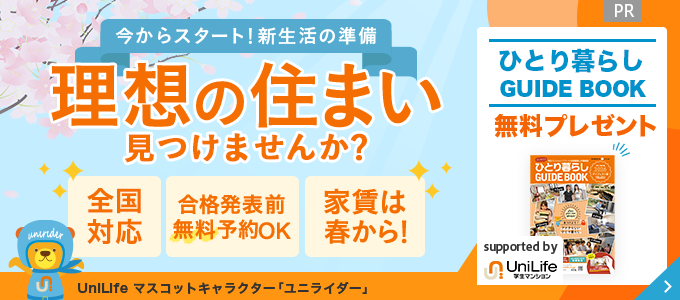4年目を終えた大学入学共通テストの傾向と対策【まとめ】
- 大学受験

センター試験から大学入学共通テストにかわり、はや4年目の実施を終えました。
昨年に引き続き「共通テストらしい」問題が出題されましたが、来年度は「情報I」などの新科目が出題される新しい教育課程での入試となります。
そこでこれまでの共通テストを振り返りながら、来年度の共通テストの見通しについてご紹介します。
センター試験と比べて問題のページ数が増加
大学入学共通テスト(以下、共通テスト)の出題ではまず問題ページ数の増加が特徴としてあげられます。
次の表はセンター試験の最終年度と今年の共通テストの問題ページ数を比較したものですが、英語、数学、現代社会などで10ページ程度増加しています。
試験時間が変わらないなかで問題ページ数が増加し、「最後の問題までたどりつけなかった」という受験生が少なくなかったことからも、共通テストの対策として情報処理力の向上があげられていました。

このように問題ページ数が増加した要因として、共通テストの特徴である【さまざまな資料】を扱う出題の増加があげられます。
図やグラフなどの【さまざまな資料】だけでなく、【さまざまな資料】をもとにした【会話文】も増えたことで、全体的に問題ページ数が増えています。
- センター試験と比べて問題ページ数が増加
- ページ数増加の要因には【さまざまな資料】を扱う出題があげられる
多くの科目で高校生の学習場面と多様な資料を扱う出題が定着
共通テストでは多くの科目で、問題の導入で授業や高校生の日常生活での「問い」を起点に【さまざまな資料】を扱いながら探究活動をおこなうという場面設定がみられ、科目によっては場面設定の説明に【会話文】が用いられています。
共通テストの【会話文】は、生徒と高校・大学の先生、海外からの留学生など、多様な登場人物が対話するなかで、異なる立場・背景を持つ登場人物と多面的な見方・考え方、立場の違いによる多角的な意見を交えつつ、「問い」に対する探究活動を進めていくような出題構成が多くみられました。
また共通テストの特徴である【さまざまな資料】が【会話文】のなかでも取り上げられ、そこでの高校生の発言やその後の考察に対して「資料をもとにした考察として適切か?」を問うような出題も多くみられました。
センター試験では「これは何か?」という用語・概念の知識・理解が、ストレートに問われる傾向にありました。
しかし共通テストではこうした出題に加え、教科書レベルの知識・理解を前提としつつ、初めて見るような【さまざまな資料】に対し「このような解釈・見解は適切か?」という思考力・判断力も問われるようになりました。
高校で2022年度から始まった新しい学習指導要領では「主体的・対話的で深い学び」を重視する方針が示されています。
実施4年目を終えた共通テストは、新しい学習指導要領の方針を先取りするような出題傾向ともいえます。
- 共通テストは学習場面での「会話文」「さまざまな資料」を扱う出題に特徴
- 会話文で示される多面的・多角的な見方・考え方の考察を求める出題も
- 来年度からの新しい学習指導要領を先取りするような出題もみられた
共通テストの正答率はおよそ6割で推移
では共通テストの平均点がどのように推移したかを、最後のセンター試験から2024年実施の共通テストまでの平均点を次の表に示しました。
前年比で5点以上の変動があったところを色分けしていますが、共通テスト1年目は平均点が5点以上高くなった科目が多めで、共通テスト2年目では多くの科目で平均点ダウンなどの変動はみられますが、正答率はセンター試験と同様におよそ6割となっています。

- 「情報I」「地理総合」「歴史総合」「公共」が新しく受験科目に
- 試験時間が「国語」80→90分、「数学Ⅱ・数学B・数学C」60→70分に変更
新しく受験科目となる「情報I」「地理総合」「歴史総合」「公共」は、大学入試センターが2021年3月にサンプル問題、2022年11月に試作問題を公表しています。
サンプル問題と試作問題を比べても、出題形式などが必ずしも一定ではないことから、これらの問題はあくまでも参考程度に考えたほうがよいかもしれません。
むしろこれまでの共通テストでは高校生の学習場面での【さまざまな資料】【会話文】を用いて思考力・判断力を求める出題が定着しており、新しい学習指導要領が重視する「主体的・対話的で深い学び」とも方向性が合致していることからも、新しい教育課程での共通テストは「昨年までと同じ出題傾向であった」という結果も十分にありえます。
これらのことから新しい学習指導要領での入試であっても、共通テストの対策はこれまでと同様、教科書レベルの知識・理解の定着と、知識・理解を活用して【さまざまな資料】を読み解く力の向上が必要と考えられます。
また高校生の探究活動の過程を問うような出題も継続していることから、授業冒頭での教師からの発問、それを受けての生徒同士の対話、対話の結果をノートにまとめる—というような、日々の授業に主体的に参加することも共通テストの対策になると考えられます。
- 教科書レベルの知識・理解の定着が第一
- 多様な資料、文章などを的確に読み解く情報処理力の向上
- 日々の授業に主体的に参加し、「学びの過程」を意識する
まとめ & 実践 TIPS
4年目の実施を終えた共通テストは、「共通テストらしい」出題傾向が定着しました。
来年は新しい教育課程での入試となりますが、まずは教科書レベルの知識・理解を定着させ、その知識・理解を活用した学習活動が共通テスト対策になると考えられます。
株式会社プランディット 社会課 十河(そごう)
編集プロダクションの株式会社プランディットで、進研ゼミを中心に、小学校から高校向けの社会(地歴公民)の教材編集を担当。
- 大学受験