【中学入試】2022年度教科別問題傾向分析(理科・社会編)
- 中学受験
2022年2月18日に森上教育研究所が主催する「2022年入試 首都圏中学入試の結果と分析」セミナーがオンラインで行われました。今回は、セミナーで発表された今年の教科別の入試傾向分析と必要な対策についてお伝えします。今回は理科と社会です。
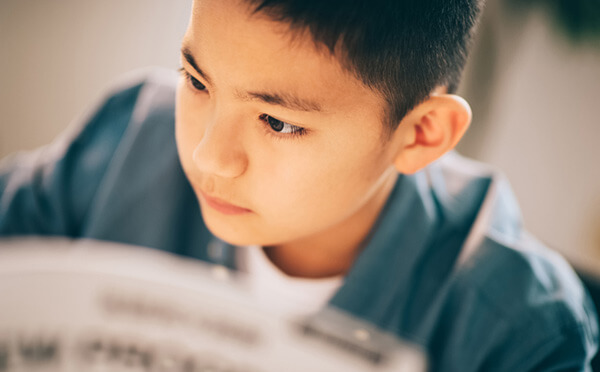
理科、社会においても新学習指導要領に沿った出題が増加へ
新学習指導要領に沿った教科横断的な問いが増加
国語、算数だけではなく理科、社会の両教科の入試問題においても、高校での新学習指導要領の実施、大学入学共通テストの開始の影響を受けた出題が増加傾向にあります。たとえば、教科別の出題であっても、理科の中に社会的な問題、社会の中に理科的な問題が含まれるといった教科横断的に多方面から物事の本質に迫ろうとする出題形式が増えてきています。
また時事問題を題材とした出題は、数年前から理科、社会とも頻出であり、これも現実的な問題を理科や社会の知識を活用して読み解かせようとする新学習指導要領に沿った思考力を問う問題といえます。塾の教材はこうした新たな傾向に沿ったものに変わりつつあるので、特別な対策を加える必要はありませんが、より本質的な思考力が問われるようになっていることは意識しておいたほうがよいでしょう。
時事問題対策は6年生の夏くらいから本格的に対策することになりますが、それまでは1週間のニュースのまとめのようなテレビ番組などを親子で見てニュースについて親子で印象的な会話を行っておけば、記憶に残るでしょう。
図表を読み取る問題に対応できる基礎力を養う
理科と社会で共通していえる傾向として、図や表を読み解き、それを活用して考えていく問題が多いということが挙げられます。この図表を読み解く力を支えるのが、各単元の基礎的な知識です。
4年生、5年生では各単元の基礎的な知識を丁寧に学習し、社会であれば世の中の社会事象はどのような理屈で動いているのか、理科であれば自然現象はどのような理屈で動いているのか、に関心を持てるようにできるといいでしょう。実際に入試に出てくるような図表を読み取る練習をするのは6年生の夏以降で大丈夫です。
理科:時事的な話題に関連した分野が出題される傾向に
「新型コロナウイルス」「自然災害や環境問題」に関連した出題も
教科ごとに詳しく2022年度の出題の特徴を見ていきます。進学研究社の冨山篤先生の分析によれば、理科では塾で普通に学習する理科の問題に加えて「新型コロナウイルス」「自然災害や環境問題」に関連した出題が2022年度も見られました。
こうした時事的な問題に関連した出題では、問題文をしっかりと読み、限られた時間のなかで資料からわかることを考え、これまでの学習の成果と照らし合わせて正解を導くことが求められます。
「起こったこと」を単に時事的な出来事で終わらせることなく、その出来事の中身について理科的な知識を総動員して自分なりにきちんと説明できるようにしておくことが大事です。
4分野均等に出題されるが時事的な話題に引きずられがち
各分野での2022年度の出題傾向は以下の通りです。多くの中学では4分野均等に出題されていますが、その年の時事的な話題に引きずられる傾向があるため注意が必要です。
①生物分野…植物、動物、人体、生物と環境
キーワード:発芽、呼吸と光合成、蒸散、心臓と肺、マイクロプラスチック
②化学分野…気体、水溶液の性質、溶解、金属、燃焼
キーワード:溶解度、二酸化炭素、アルコール、ガスバーナー、メスシリンダー
③物理分野…力のつり合い、浮力と密度、光・音・熱、電気、運動とエネルギー
キーワード:電熱線、光電池
④地学分野…天体、気象、地形
キーワード:皆既月食、スーパームーン、警報、線状降水帯、地質柱状図
社会:現代の日本や世界が抱えている諸問題が頻出
記述問題の出題が増加、資料の読解問題も9割の学校で出題
社会は、文教大学の早川明夫先生の分析によれば、全体的には例年より易化し、難問・奇問はほとんどみられませんでした。記述問題の出題は増加し、昨年は77%の学校で出題されましたが、2022年度は約90%の学校で出題されています。記述問題で問われる内容は、原因・理由が最も多く、資料の読み取り、用語の意味が後に続いています。
資料の読解問題は、約90%の学校で出題されました。資料の種類は、表、グラフ、雨温図、分布図、地形、史料、絵画、写真などがありますが、特に多いのはグラフ、統計、表問題であり、こうした資料を読み解き、情報処理できる分析力、考察力が求められます。
例年8〜9割の学校で時事問題の出題
時事問題は例年8〜9割の学校で出題されており、現代の日本や世界が抱えている諸問題が取り上げられます。2022年度の時事問題の出題傾向は以下の通りです。国内外の出来事に関心を持ち、社会科のアンテナを張ることが大事です。
①新型コロナウイルス感染症の拡大
パンデミック、ロックダウン、影響、感染症の歴史、医学(医療)の変化
②地球環境問題
地球温暖化、温室効果ガス、温暖化の影響、自然災害
国際的な環境保全、取り組み…温暖化、COP(京都議定書、パリ協定)
生物多様性の減少(ラムサール条約、ワシントン条約)
世界遺産条約
③資源・エネルギー問題 再生可能エネルギー、原子力発電の課題
④難民・移民問題 多様性と異文化理解
⑤少子高齢化 社会保障費、外国人労働者
⑥核兵器 核兵器禁止条約、核の傘
⑦SDGs 17の目標と取り組み、ジェンダー
まとめ & 実践 TIPS
理科、社会では、教科横断的な出題形式や、時事問題を題材として思考力を問う問題が増加傾向にあります。図表問題も頻出ですから、各単元の基礎的な知識を丁寧に学習しておくことが大事です。時事問題では理科、社会とも「新型コロナウイルス」「自然災害や環境問題」が取り上げられました。理科は理科的な知識を総動員して時事問題をきちんと説明できるようにしておくこと、社会は国内外の出来事に関心を持ち、社会科のアンテナを張ることが大事です。
- 中学受験













