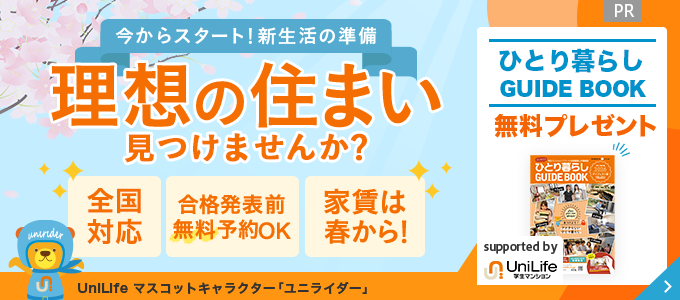【中学受験】塾通いが始まる前の小学2、3年生のうちに取り組んでおきたいことは?
- 中学受験
中学受験をめざす場合、小学4年生ごろから塾通いをスタートさせるのが一般的です。小学2、3年生は塾通い前で時間の余裕がある貴重な時期。中学受験を意識しているご家庭でこの時期に取り組んでおくとよいのはどんなことか、森上教育研究所がお伝えします。

時間のある低学年のうちに「遊びながら学ぶ」体験を
五感を使う体験を数多く取り入れて
塾通いを始める前の小学2、3年生の時期というのは、お子さんに時間的な余裕のある時期です。中学受験を意識して準備をスタートしたいのであれば、時間のあるこの時期にしかできない「遊びながら学ぶ」体験をぜひ取り入れてほしいと思います。
まず取り組みたいのは、直接五感を使う学びです。たとえば、自分の手を動かす折り紙、保護者のかたと対話しながらの本の読み聞かせ、手と頭を働かせる算数パズルやそろばんなど、目や耳や肌などで直接感じる「遊びながらの学び」がおすすめです。
現在はコロナ禍の影響もあり、オンラインの体験が主流になりがちです。しかし、小学2、3年生は運動神経が発達する時期ですから、画面を眺めるだけでなくぜひお子さん自身の感覚を鍛えておきたいところです。一見難しいけれど「できそう!」とお子さんが思えることに挑戦して、できた時の達成感は、お子さんの学びへの意欲、挑戦心をはぐくんでくれるでしょう。
人と競うことで自分の「得意」を見つける
また、どこまでが遊びで、どこからが学習かあいまいなものや、勉強に必ずしもつながらないような遊びの要素が多いことに時間を十分使えるのもこの時期の特長です。そこで取り入れたいのは、ボードゲーム、囲碁や将棋など、誰かと対面で競い合う遊びです。
人と競い合うと悔しい思いをしたりケンカになったりということもありますが、自分の「得意」を見つけたり「弱み」を自覚したりすることができます。そうした自覚は、お子さんが自分自身を知り、やりたいことを見つけていくことにもつながります。保護者のかたはなるべく一人遊びのためのゲームだけでなく、お友達や家族と一緒に競い合いながら遊べるものについてもたくさん用意してあげてください。
子どもの興味をかきたてる体験ができる場所へ出かける
塾通いを始めると土日も勉強で忙しくなりますから、低学年のうちに旅行を兼ねてお子さんが興味を持ちそうな場所に出かけるのもおすすめです。たとえば、昆虫が好きなお子さんであれば昆虫館に行って見学したり、学芸員のかたに話をうかがったりするのもいいでしょう。そうした専門家のかたとお話しできる機会があるとお子さんの知的好奇心がぐっと高まります。
また、とくに興味があるというわけでなくとも、きれいな景色の場所や名勝などに家族で行ってさまざまな体験をすると、お子さんの興味の幅を広げることにもつながります。たとえば地形に着目して「ここはデルタ地帯だね」「これが河岸段丘だよ」と教えると理科に興味を持つお子さんもいるでしょう。
普段と違う場所に出かけて新たな体験をすることで、普段は気に留めていなかった石に興味を持ったり、空に興味を持ったりと、お子さんの新たな興味の芽を育てることにもなります。そうした体験を積むことが、高学年になってからの理科や社会の学習に生きてきます。
短い時間でよいので低学年のうちに「学習」の習慣付けを
「遊び」とは区別した「学習」の時間も必要
低学年のうちに必ずやっておきたいのが「学習」の習慣付けです。中学年、高学年になってくると、保護者のかたが「勉強しなさい」と言っても素直に勉強しなくなってしまいます。毎日の生活リズムの中に「勉強の時間」を組み込み、「勉強は毎日するものだ」と習慣付けをするためには、保護者のかたの声かけに素直にしたがう小学2、3年生のうちがチャンスなのです。
たとえば「○時になったらこれをやろうね」とあらかじめ学習の時間を決めておいて、短い時間でいいので「遊び」とは区別した「学習」の時間を設けます。取り組むのは、学校の宿題でもいいですし、算数や漢字のパズルでもいいでしょう。遊びの要素が強いものは遊びの時間に自由に取り組ませたほうがよいので、ここでは学習の要素が強いものを決まった時間に決まった量を取り組みます。
時間が来たら保護者のかたも一緒に学習に取り組んで、「ここまでやったらおしまい」という区切りをしっかりとつけると達成感が持てます。能力を付けるのは大変ですが、習慣を付けるのは比較的簡単です。そして習慣付けをすれば必ず能力も付いてきます。早いうちに学習の習慣付けを行って、塾通いをスムーズにスタートさせましょう。
まとめ & 実践 TIPS
時間的な余裕のある小学2、3年生の時期は、「遊びながら学ぶ」体験が大事です。
折り紙、本の読み聞かせ、算数パズルやそろばんなどの五感で直接感じる学びで感覚を鍛えましょう。ボードゲーム、囲碁や将棋などで人と対面で競い合う遊びも、お子さんが「得意」や「弱み」を自覚することにつながります。旅行を兼ねてお子さんが興味を持ちそうな場所に出かけるのも、この時期だからこそできることです。
あわせて、低学年のうちに短い時間でよいので「学習」の習慣付けをしておけば、塾通いをスムーズにスタートできるでしょう。
- 中学受験