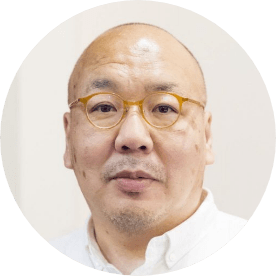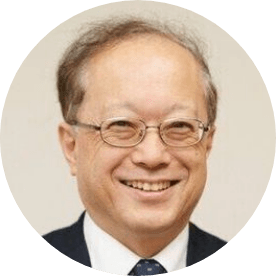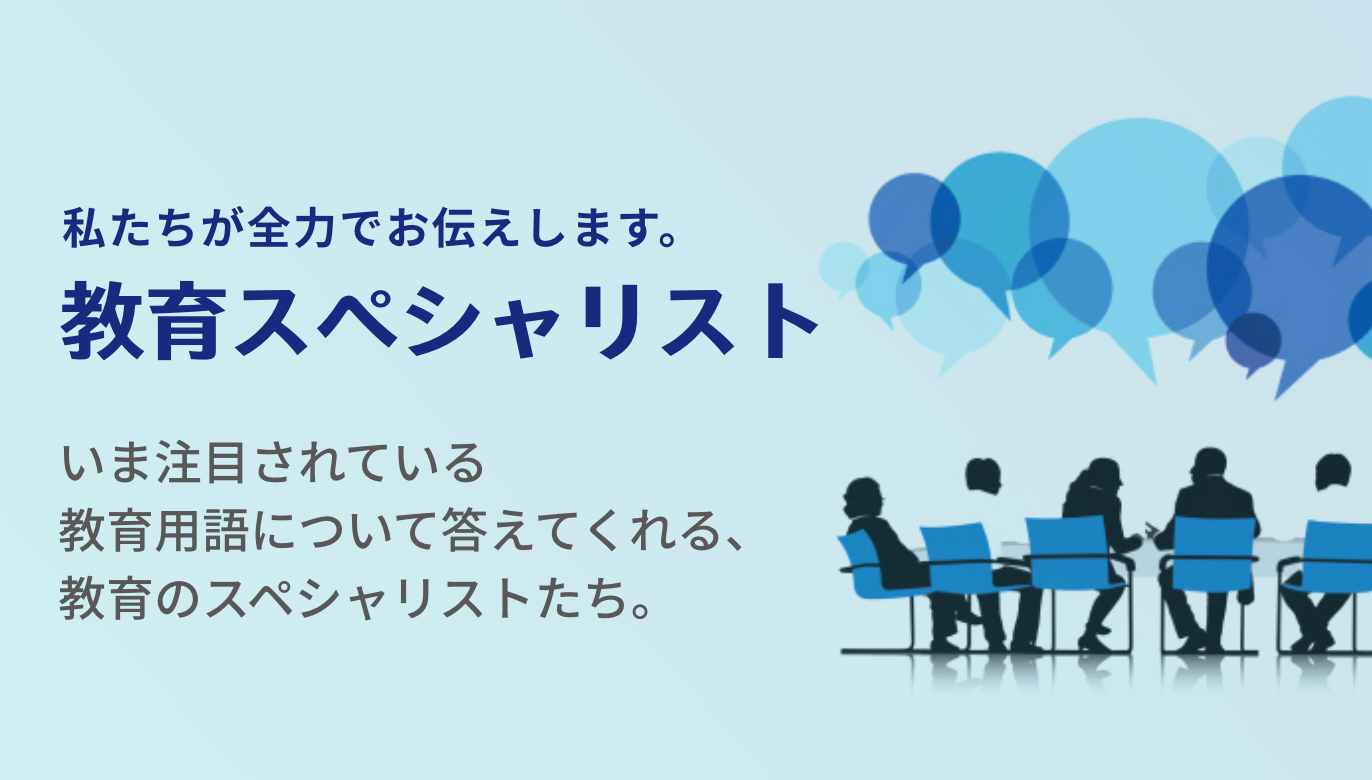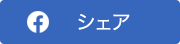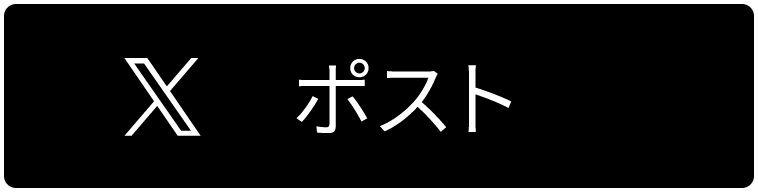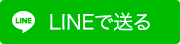教育用語解説
-
幼児期の終わり、つまり小学校に入学する前までに育ってほしい資質・能力を示した「10の姿」というキーワードをご存じですか? 遊びを中心とする幼稚園・保育園での生活や学びと、大半の時間は机で勉強する小学校での学びをつなぐカギにもなっている、とても大切な内容です。全国すべての幼稚園や保育園などでは、この「10の姿」を意識した教育・保育を行うこととされていますが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。

-
「GIGAスクール構想」という言葉、ニュースや学校からのお知らせなどで触れたことがある人も多いと思います。2019年2月に文部科学省が打ち出したもので、簡単に言うと、「これから必要とされる学びの環境を、ICTをもっと活用してこのように実現していく」と目指す姿を示したものです。GIGAスクール構想の概要と併せて、ICTを活用した学びが、なぜ、どのように必要なのかを改めて解説します。

-
2016年に、「小学校」「中学校」などと同様、学校の種類の一つとして制度化された「義務教育学校」。背景にあるのは、社会や子どもたちの変化や、それにともない求められる教育の変化です。子どもへの影響、義務教育学校の実例とあわせて解説します。

-
「STEAM教育」という言葉、聞いたことはあるものの、いま一つ分からないと感じるかたは多いようです。STEAM教育とは、さまざまな学問領域を土台にしつつ、特に理数系の学びを中心に多様な知識を活用しながらそれを統合して、社会の問題を発見・解決してい

-
「VUCA」(ブーカ)とは、「これからはVUCAの時代だ」のように、現在や将来の社会の様子を示す際に使われる、英語由来のビジネス用語です。近年は教育の世界でもよく用いられるようになりました。そもそもVUCAとは何でしょうか。教育との関連や、学校や家庭とのつながりでおさえておきたいポイントも含めて解説します。

-
直訳すると「幸福」「健康」という意味の「well-being(ウェルビーイング)」。幸せで、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。人の生き方全体に関わるキーワードですが、教育においても、世界的に非常に重視されている考え方です。

-
生まれ育った環境によって、子どもが獲得する学力に差がつくことを「学力格差」と言います。日本の法律には、生まれや育ちに関係なく、すべての子どもは等しく教育を受け必要な学力をつけるべきとの基本的な考えがあります。しかし、子ども自身が好むかどうか
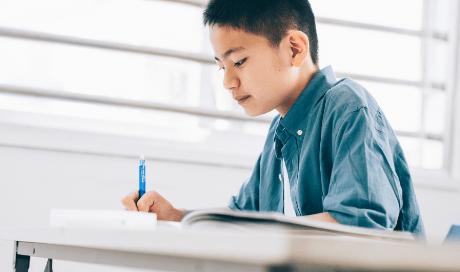
-
大学入試の選抜方式には、①一般選抜、②総合型選抜、③学校推薦型選抜、の3種類があります。以前は、それぞれ、一般入試、AO入試、推薦入試、と言われていましたが、2021年度入試(2年前の高校3年生の受験年)から現在の呼び方に変更されました。このうち学校推薦型選抜は、高校の推薦を受けることで出願できる方式で、「その大学でこんなことを学びたい」という意欲や入学後の目標が特に重視されます。総合型選抜と似ている部分はありますが、学校推薦型選抜ならではの特徴や注意点がありますので、それらを含めて説明します。

-
学校教育をよりよいものにしていくためには、子どもと学校と社会をつなぐ視点を持ちながら、学校全体で教育活動の改善を進めていく「カリキュラム・マネジメント」が必要不可欠だと言われています。これからの教育の方向性を提言した国の報告書※にも、子ども一人ひとりに応じた学びのあり方や、ICTの活用、高校の改革、STEAM教育などの重要なキーワードには「カリキュラム・マネジメント」の充実がセットで記されています。 具体的にはどのようなもので、カリキュラム・マネジメントによって学校の教育がどのように変わるのでしょうか。

-
就学期のお子さまがいるご家庭で、学年末や大きな行事のあとに、感想や振り返りが書かれた用紙を持ち帰り、保護者欄へのコメントを求められたことはありませんか? それは、2020年度からすべての小中高校で始まった「キャリア・パスポート」のことかもしれません。社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら自分らしく生きる力を育むキャリア教育活動の一環として行われているのが、「キャリア・パスポート」の作成と活用です。その概要や家庭での活用例をお伝えします。

-
先生のなり手が少ない、先生の離職率が高まっているなど、教員不足に関する残念な報道を目にしますよね。実際の教員不足の状況と理由、改善のためのポイントを、2022年度まで小学校教諭として教壇に立ち、現在も、教育や教師の働き方に関する情報発信を行っているベネッセ総合教育研究所の庄子寛之が解説します。
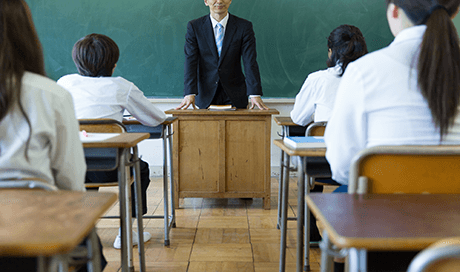
-
公立小学校の授業の一部を、学級担任以外の教員が受け持つ「教科担任制」が、2022年度から本格的に導入されました。教科担任制とはどのようなものか、その特徴やメリット、これからの方向性について、小学校での教科担任制を中心に説明します。

-
高校は義務教育ではないため、たとえ公立でも授業料などのお金がかかります。しかし、ほぼ100%の子どもが高校に進学している現状*1も踏まえ、子どもの教育機会の公平性を確保し、少子化にも歯止めをかけるために設けられた制度がいわゆる「高校無償化」です。その概要や条件、利用する際のポイントをお伝えします。

-
ここ数年、「英語が学べて世界中の大学への入学資格を得られる」などの理由から、保護者の間で「国際バカロレア」への関心が集まっています。グローバルな人材育成に力を入れる国の方針と相まって、国際バカロレアの考え方や教育プログラムを導入する学校も増えています。大変魅力的なプログラムである半面、英語力アップや海外大学への進学といった、局所的な視点からみた特色に目が行きがちなことも事実です。国際バカロレアの教育プログラムの概要や、目指す人材像、日本での課題などについて解説します。

-
地域と学校が共によりよい学校をつくるための「コミュニティ・スクール」を導入する学校の割合が、全国の公立学校の4割以上を占めるようになりました。※学習指導要領の考え方と相まって、学校が地域とともにあり、そのなかで子どもを育てるという流れは今後も強まっていく見込みです。その中心的な役割を期待されている「コミュニティ・スクール」とは、どのようなものでしょうか?

-
子どもの考える力を育むことは誰もが大切だと思っていることでしょう。しかし、ただ「考えなさい」と言われても、子どもはどう考えればよいのか、なかなかわからないものです。そこで現在の学習指導要領では、どのように考えればよいかという「考えるための技法=思考スキル」を身につけることを重視しています。その手段として、思考ツール(シンキングツール)と言われるものが使われます。具体的にはどのようなものでしょうか。

-
2025年度から、全国すべての小6・中3生を対象に毎年行われる「全国学力・学習状況調査」の一部で、新たなテスト方式「CBT」が導入されたことをご存じですか?CBTは、お子さまがこれから将来にわたって受けるテストの主流になるとされています。その概要や今後の動きを解説します。

-
教育の世界でも、「多様化」や「個性の尊重」が言われるようになり、我が子に合った勉強スタイルって何だろう?と悩んでいる方もいるかもしれません。学校においても、子ども一人ひとりに合った授業のあり方を試行錯誤する動きが見られます。そこで注目を集めているのが「自由進度学習」です。

-
高校への進学率は、ほぼ100%という状況です。だからこそ、高校にはよりよい教育活動を行い、より魅力的であってほしいと願います。そうした願いが実現するように、学校教育法施行規則改正により「スクール・ミッション」を前提として、「スクール・ポリシー」の策定と公表を高校は求められるようになりました。今回は、このスクール・ミッションとスクール・ポリシーの概要や、子どもや保護者にどのような関係があるのかを説明します。
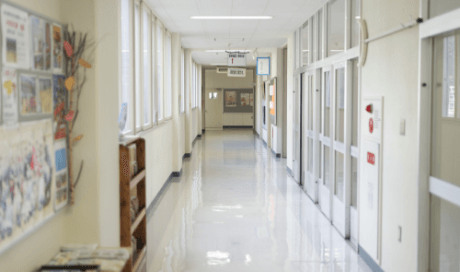
-
大学入試には、①一般選抜、②総合型選抜、③学校推薦型選抜、の3種類があります。以前は、一般入試、AO入試、推薦入試、と言われていましたが、2021年度入試(2年前の高校3年生の受験年)から現在の呼び方に変更されました。このうち総合型選抜は、「その

-
2020年から、大学などに関する新しい修学支援制度がスタートしたことをご存じですか?一般には「大学無償化」と言われていますが、正しくは「高等教育の修学支援新制度」といい、大学や短大だけでなく、高等専門学校や専門学校などへの修学も対象となります。制度の中身や申請条件などを確認しておきましょう。

-
今、高校はもちろん、幼・小・中学校も含めた学校教育の目玉となっているのが「探究学習(探究的な学び)」です。小・中・高校では「総合的な学習(探究)の時間」という科目が必修となり、それ以外の教科・科目、各種活動においても探究学習が行われるようになりました。「探究学習」の概要や重視されるようになった背景、子どもたちがどうなることを目標にしているのかなどについて解説します。

-
「調査書」とは、受験生がどのような高校生活を過ごしたのかを記した書類のことです。学業成績を点数化した内申点(評定)が記載されていることから、内申書ともいわれます。学校の先生が作成し、ほかの出願書類と同時に志望校へ提出します。中学入試から大学

-
中学校や高校で学期ごとに行われる定期テスト(定期考査)。最近は定期テストを廃止したり、実施回数を減らしたりする学校が増えています。なぜ、そのような動きが見られるのでしょうか。定期テストがなくなると、成績評価はどのように行われるのでしょうか。保護者世代には当然の存在だった定期テスト。その意義や課題を改めて考えてみましょう。

-
改訂版の新しい教科書の使用が予定されている2024年度から、学習者用デジタル教科書(以下、デジタル教科書)が本格導入される見通しです。まず小中学英語で、デジタル教科書が紙の教科書と同じ扱いで併用されます。その後も算数、数学への導入を検討し、段階的に導入を拡大していく考えです。デジタル教科書で学校教育はどのように変わるのでしょうか。

-
「認定こども園」とはどんな園なのだろうかと、疑問に感じているかたもいるでしょう。お子さまや保護者のかたにとってどのようなよい点があるのか、どのような基準で認定されているのか、園選びをするときの違いは何か……。認定こども園の利用を考えている保護者のかたが知りたい情報をご紹介します。

-
これからますます進化するネット社会を生きる子どもたちにとって、インターネットとどう向き合い、活用していくかは大切な課題です。学校でも情報活用能力の指導が行われていますが、限られた時間や環境の中で、必要なことをすべて学べるわけではありません。とりわけ「ネットリテラシー」と言われるスキルは、保護者のかたのサポートにより早いうちから家庭で取り組むことが重要になります。

-
子どもの障害には、大きく分けて身体障害(肢体不自由)、知的障害、視聴覚障害、発達障害などがあります。これらのうち8割以上の症例を占めるのが発達障害です。国の調査結果*1によると、全国の公立小中学校の通常学級に通う子どもの約9%(1クラスに3名前後)に発達障害の可能性があり、そのうち約4割が授業中に丁寧な指導を受けられるような配慮・支援を受けていなかったそうです。発達障害の有無は外見からはわかりにくく、その症状や困りごとは十人十色です。そのため、子どもの特性や周囲の状況を踏まえたサポートがとても大切です。

-
近年、世界の教育現場で重視されているのが「非認知能力」の育成です。非認知能力とは人間が大切にすべき複数の力をまとめた概念で、最近ではその中の1つである「グリット(grit:やり抜く力)」が、社会で活躍できる人の共通点の1つであるという米国の研究発表をきっかけに話題を呼びました。非認知能力とは、具体的にどのような力で、どのように伸ばすことができるのでしょうか。

-
「評定平均」とは、高校3年間の成績を数字で表したものです。内申点とも言われ、評定平均を記した「調査書」(いわゆる内申書)にも記載される、大学入試とは切っても切り離せない存在です。特に、学校推薦型選抜では、一定以上の評定平均値を出願条件とするなど、非常に重要な数字となっています。では、具体的な計算方法や、学校推薦型選抜でどのように関係するのかを見てみましょう。

-
世界の15歳はどんな学力を身に付けている?日本の15歳は世界と比べてどんな強み・弱みがあって、ランキングでいうと世界で何位?——そんなことがわかる国際調査「PISA」の結果が12月5日*に発表されます。世界中がその結果を注目する「PISA」とはどのような調査なのでしょうか。

-
お子さまが中学校入学で最も楽しみにしていることの1つが、部活動です。その部活動が、保護者世代の頃とは事情が変わってきています。少子化や教員の働き方改革の影響を見据えて、部活動を学校の外、つまり地域での活動に変えようとする動きが国主導で進みつつあります。部活動の地域移行でお子さまや保護者のかたにとってどんな影響があるのでしょうか。

-
「勉強する時間が長いほど成績が上がる」は本当?——半分は合っています。成績を上げるためには、まず机に向かう習慣をつけることから始め、一定量の勉強時間を確保することが必要です。しかし、やみくもに勉強時間を延ばしても効果は限定的で、勉強時間
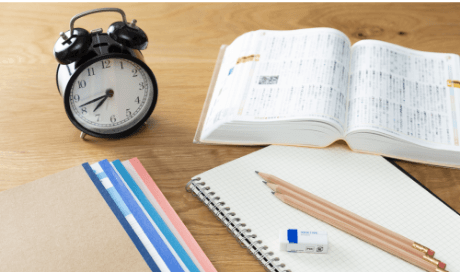
-
子どもが自分を客観視できるようになると、主体的に学習に向かう態度が身に付き、成績アップにつながりやすくなると言われています。自分を客観視する力を「メタ認知」といいます。なぜ、自分を客観視できると学習によい影響があるのでしょうか。学校・家庭でできるメタ認知の育み方とともにお伝えします。

-
一部の自治体や学校で「ラーケーション」を取り入れる動きが始まっています。新たな学びのスタイルとして注目を集める「ラーケーション」とはどのようなものでしょうか。今注目を集める背景や、取り組むメリット、そして現在の課題を解説します。

-
理工系の学問を学んだり、理工系の分野で仕事をしたりする女性、「理工系女子」が増えています。大学入試でも、理工系の学部で「女子枠」を設ける動きが急速に拡大中です。大学入試や社会の様子、これからの課題について、山田進太郎D&I財団の大洲 早生李さんに解説していただきます。

-
2020年、宇宙飛行士の野口聡一さんが、自身が搭乗する宇宙船の名前を「レジリエンス」と名付けたことが話題になりました。レジリエンス(resilience)=困難から回復する力、という意味の通り、コロナ禍に負けない、という願いを込めたそうです。教育においても、このレジリエンスという力の重要性が注目を集めています。なぜ、レジリエンスが重視されるのか、その背景や意味などを説明します。