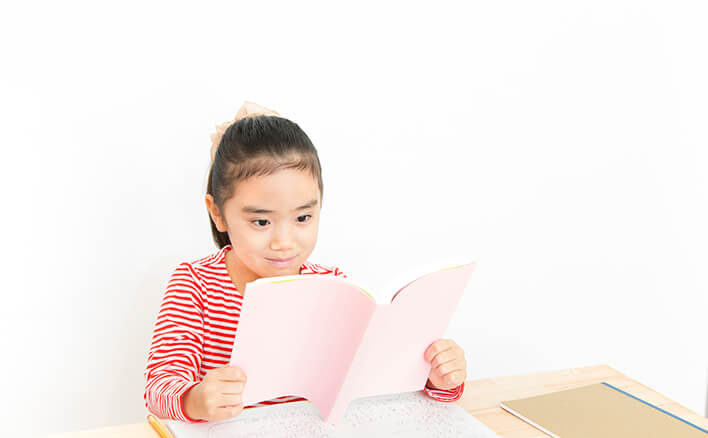音読からワンステップアップ!「朗読」で読解力を身に付けよう
お気に入りに登録
国語の宿題でもおなじみの音読とは、声に出して読むこと。朗読も似ていると思われがちですが、聞いてくれる人がいて、その人に伝わりやすいように工夫して読むことがいちばんの違いです。
エリアベネッセ青山では、この朗読を通して読解力を身に付けることで、お子さまが本好きになるのを応援するためのイベントが行なわれました。講師は朗読家として子どもたちに朗読の楽しさを伝える活動をしているほか、朗読のプロを育成する講師としてもご活躍中の葉月のりこさん。朗読で読解力を身に付ける秘訣とは一体どんなものなのでしょうか。

なぜ、朗読をすると読解力がつくの?
なぜ朗読をすると読解力がつくのでしょうか。たとえば下のような文章があるとします。
(1)「私は、昨日とった魚を食べました」
(2)「私は昨日、とった魚を食べました」
(3)「私は昨日とった魚を食べました」
日本語は読点の位置によって意味が変わることがあります。(1)は、魚を「とったのが」昨日、(2)は魚を「食べたのが」昨日という意味になりますが、(3)はどうでしょうか? この文章だけでは昨日「とった」のか「食べた」のか、どちらの意味なのかわかりませんから、前後の文章をヒントに自分で考えなくてはなりません。ところが、お子さまの場合、黙読など目で読むだけではそこまでは考えず、流してしまうことがほとんどです。
一方、「人に伝わりやすように工夫する」朗読ではどうでしょう。声は発するだけではなく、その声を自分でも聞くことになりますから、「これで伝わるかな?」と客観的に考えることができるのです。これが、どの言葉が大切か、作者が伝えたいことを読み解くにつながります。
また、小説を読んでいると、知らない言葉や漢字が出てくることもあります。人に伝えるためには、まず自分が意味を知らなければなりませんから、こうしたことを調べる過程がうまれます。音読が【1】目で読む【2】声に出す、だけの2ステップで成り立っているとしたら、朗読は、【1】目で読む【2】考える・調べる・想像する【3】聞き手にわかりやすいように工夫して声に出して読む、という3ステップで成り立っているのです。
わからないことを知る喜びを、共に味わう
ご家庭で朗読にチャレンジするときに、お子さまの知らないことや言葉が出てきたら、ぜひ保護者のかたも一緒に調べてあげてください。そうして調べたことはずっと覚えているもの。時間のある休日に物語に登場した動物や昔の道具などを実際に見に行っても、親子で知る喜びを味わうことができます。
また、朗読の時だけでなく、普段の会話でも「この人は、ちょっと寂しかったのかも。どう思う?」「一面の雪で、何時間も外で遊んでいたら、手が痛くなってしまうね」などと、想像することを取り入れていくことが、お子さまが読解力を身に付ける礎となります。
みんなが読んでる!おすすめ記事
- 朗読で読解力アップ!登場人物になりきって親子で楽しもう
- いよいよ小学生。入学前にお子さまの目線から通学路の安全をチェックしよう!
- 国語の読解問題が苦手な小学生 読解力をアップするには?
- 合格前に予約もアリ!今知っておきたい、受験生のひとり暮らしの「部屋探し」事情 《ガイドブック無料プレゼント中》【PR】
- 正確に話せなきゃダメ?小学校英語の「パフォーマンステスト」を成功させるカギとは
- 「情報の整理」と「知識のネットワーク化」で、読解力を高めよう!
- 学童保育って、どんなところ? | 小学校入学準備 ベネッセ教育情報サイト
- 「英語による授業」でいいの? 学術会議が批判
- 読解力を付けるのに役立つのは、どのような分野の本でしょうか?[中学受験]