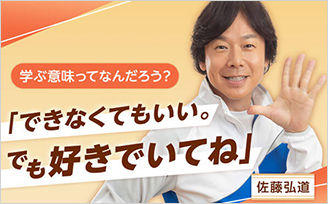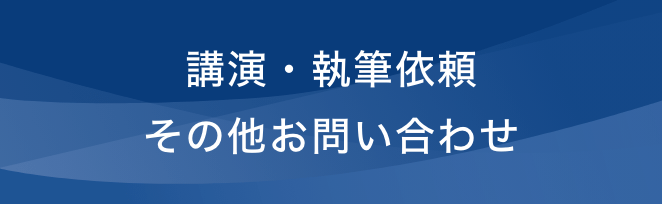View More
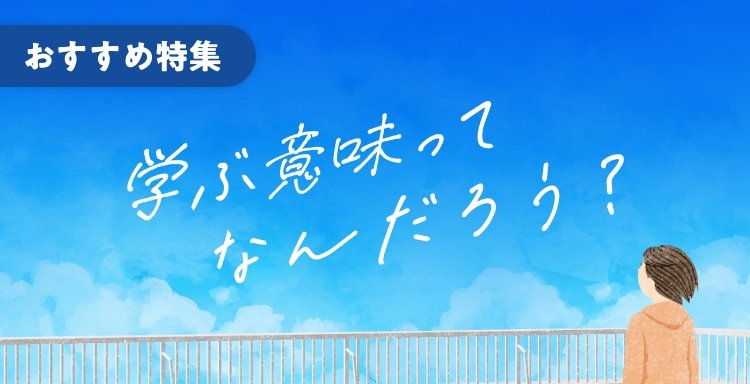
【特集】学ぶ意味ってなんだろう?
「なぜ学ぶの?」その答えは、人それぞれです。この特集では「勉強やる気タイプ診断」をはじめ、全国の保護者のかたの声、そして《あの人》へのインタビューを掲載中。あなたやお子さまにとっての「学ぶ意味」が見つける手がかりをお届けします。
トピックス
View More
View More
+
オンラインセミナー
教育用語解説
-
#認定こども園
「認定こども園」とはどんな園なのだろうかと、疑問に...
-
#定期テスト廃止
中学校や高校で学期ごとに行われる定期テスト...
-
#理工系学部「女子枠」
理工系の学問を学んだり、理工系の分野で仕事をしたりする女性...
-
#ラーケーション
一部の自治体や学校で「ラーケーション」を取り入れる動きが...
-
#自由進度学習
教育の世界でも、「多様化」や「個性の尊重」が言われるようになり...