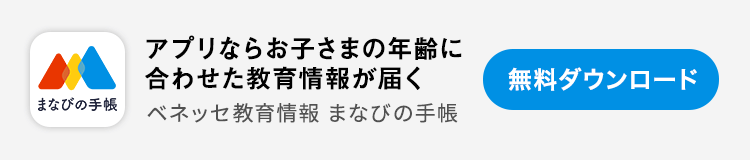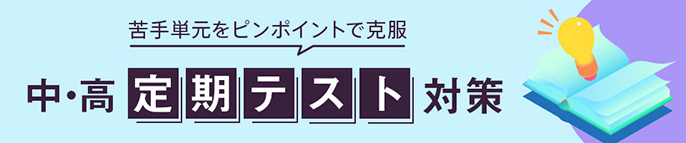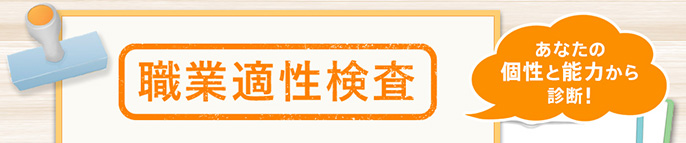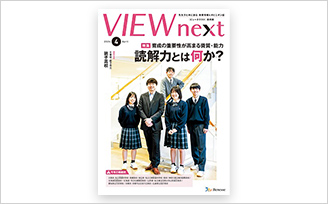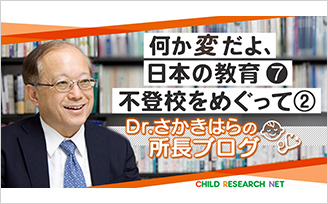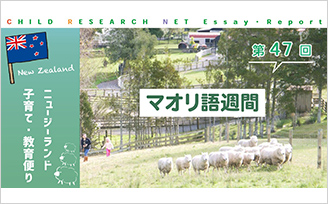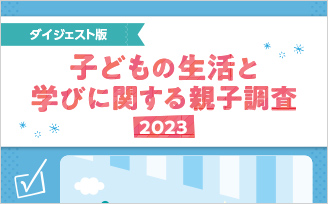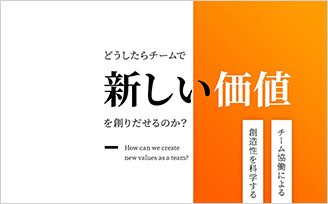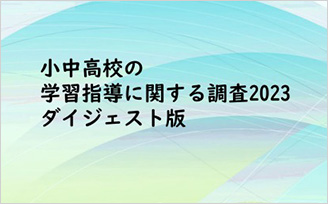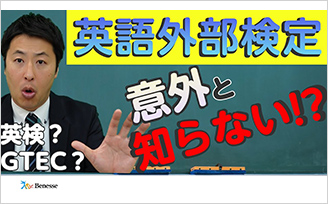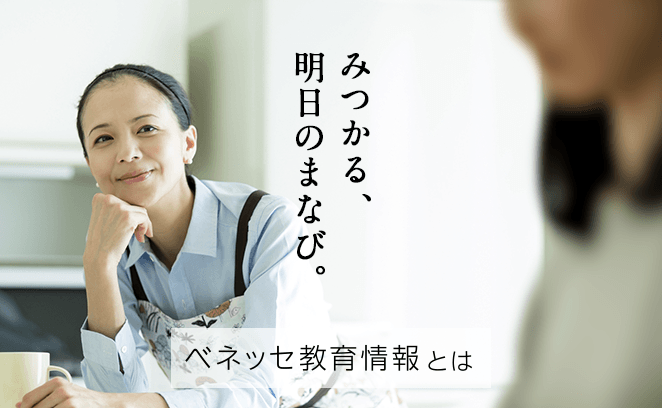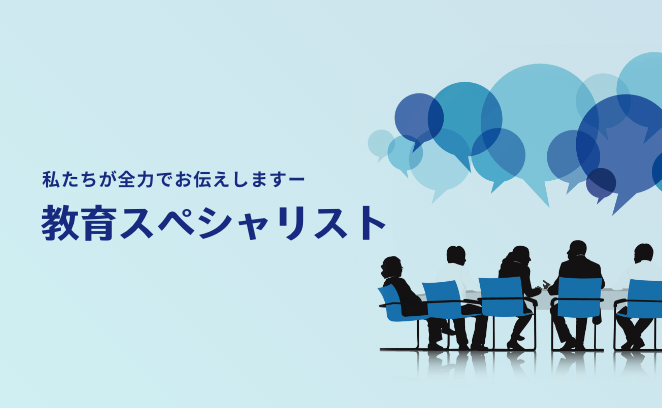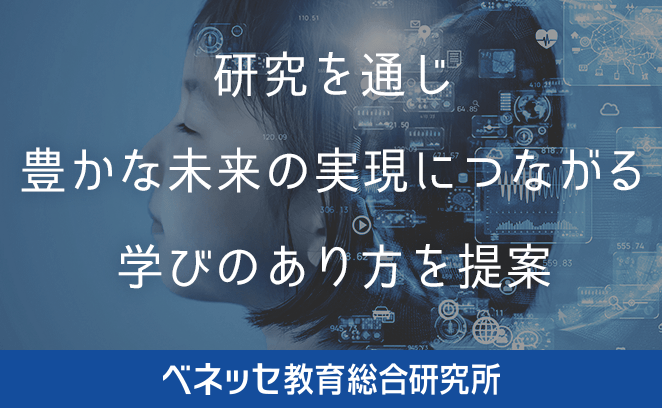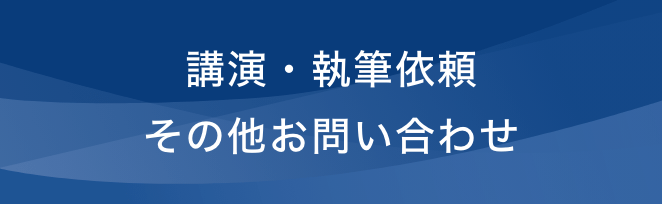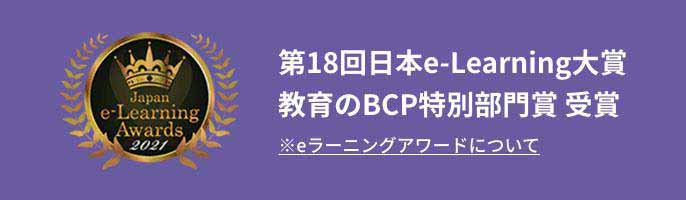View More

世界で注目が高まる「ウェルビーイング」とは?教育における重要性と課題を専門家が解説
直訳すると「幸福」「健康」という意味の「well-being(ウェルビーイング)」。幸せで、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることを言います。
ここでは、特にウェルビーイングと教育の関係に焦点を当てて解説します。
トピックス
View More
View More
+
データ&レポート
View More
オンラインセミナー
教育用語解説