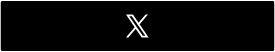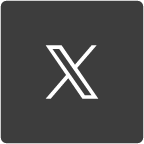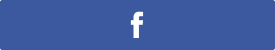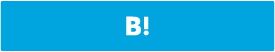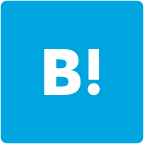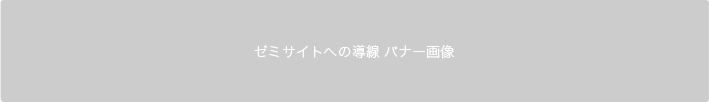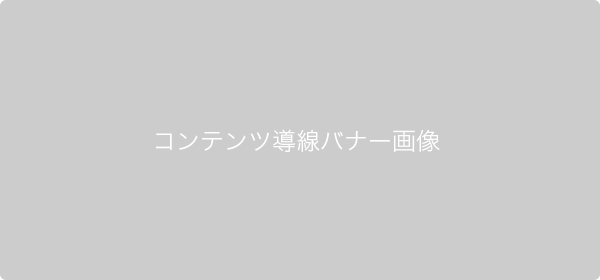ニッポンの教育をどう考えるべきか --苅谷剛彦・オックスフォード大学教授に聞く(2)
苅谷剛彦・オックスフォード大学教授と木村治生・ベネッセ教育総合研究所室長の対談の第2回は、「学び」について考えた前回に引き続き、グローバル化と英語教育の課題を深めます。
※この記事は2015年4月に東京都内で行われた対談を、教育ジャーナリストの渡辺敦司氏がまとめたものです。
グローバル化しても基本は日本語での思考
木村 社会のグローバル化が進む中で、子どもたちも自分たちの世界の中だけで自己完結していてはいられず、さまざまな背景を持った人たちと交流し、課題を解決していかなければならない場面が増えてくることと思います。苅谷先生は英国で教えていて、どのように感じていらっしゃるのでしょうか。 苅谷 僕はフルブライト奨学生として米国のノースウェスタン大学大学院に留学した時、TOEFLの成績がギリギリだったんですよ(笑)。帰国してからは日本の大学で、日本語で教えていました。だから50代で英国に渡って英語で仕事をするようになっても、ずっと欧米で生まれ育った人に英語でかなうわけがない。
苅谷 僕はフルブライト奨学生として米国のノースウェスタン大学大学院に留学した時、TOEFLの成績がギリギリだったんですよ(笑)。帰国してからは日本の大学で、日本語で教えていました。だから50代で英国に渡って英語で仕事をするようになっても、ずっと欧米で生まれ育った人に英語でかなうわけがない。
英語ができるから海外に渡れるわけではなく、必要に迫られるから英語ができるようになるのです。逆に言えば、英語ができるからといって英語以外の「何か」ができるとは限りません。日本では「教育をグローバル化しよう」と言っていますが、英語圏の国では、学んだ成果がそのままグローバルなものとして通用します。英語を基本に世界は動いていますからね。だから彼らは、グローバル化しようという意識すら持たずに済みます。
それに対して日本は、意図的にグローバル化を進めなければなりません。「スーパーグローバル」というのも変な英語ですが、そんな和製英語を使わなければいけないところに、日本というコップの中だけでグローバル化政策を進めなければならない現実が象徴されています。
でも、悲観的になることはありません。日本語だけで学問や思考ができるということは、実はものすごいことなのです。世界には外国語ができる人しか学問にアクセスできず、自分たちの文化を母語で語れない国もたくさんあるのですから。使用言語は違ってもビジネスや教育など社会制度は近いというアドバンテージを生かすことのほうが、むしろ日本がグローバル社会に貢献できる道だと思っています。
小学校時代から英語ができるようになったとしても、日本語で考える力が落ちてしまったら、このアドバンテージを生かすことはできませんし、永遠に西洋に追いつくことなどできません。むしろそういう追いつこうという発想自体を切り替えなければならない。
木村 最低限の基礎としての英語力と、グローバル化への対応は違うということですね。その時に、保護者は何をすればいいのでしょう。
苅谷 できるだけ異質な文化に触れさせ、それに対し抵抗を持たないようにすることです。必ずしも外国語を習得させたり、海外旅行に連れて行ったりするだけでなく、国内にも外国人はたくさんいますよね。
小さい時から英語を準備したからといって、グローバルな人材になれるわけではありません。僕も思考言語としての日本語がしっかりしているからこそ、英語で表現することができるのです。