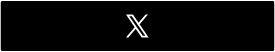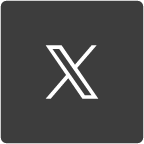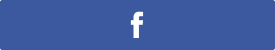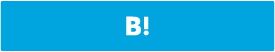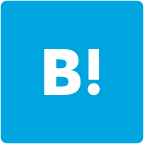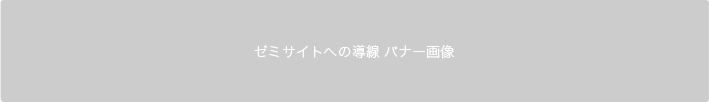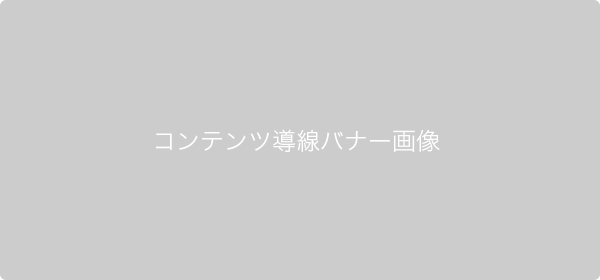「使える英語」をめぐり異論も 学校の英語教育はどこまで可能か‐斎藤剛史‐
 文部科学省が小学校高学年で英語を教科化するなど英語教育の改革を進めようとしていることは、以前の本コーナーでもお伝えしました。英語教育の改革によりこれからの日本人全部が英語を使えるようになれば、素晴らしいことです。しかし、現在の改革について英語教育関係者の一部には根強い批判があります。その背景を探ると、高校までの英語教育とは何かという根本的な問題が絡んでいるようです。
文部科学省が小学校高学年で英語を教科化するなど英語教育の改革を進めようとしていることは、以前の本コーナーでもお伝えしました。英語教育の改革によりこれからの日本人全部が英語を使えるようになれば、素晴らしいことです。しかし、現在の改革について英語教育関係者の一部には根強い批判があります。その背景を探ると、高校までの英語教育とは何かという根本的な問題が絡んでいるようです。
高校までの学校教育における英語教育には、やや乱暴に分ければ「コミュニケーション重視」と「文法重視」の二つの考え方があります。現在の学習指導要領は、英語について「読む・書く・聞く・話す」の4要素をバランスよく教えるとしながらも、最終的には情報や考えを理解したり伝えたりできるコミュニケーション能力を養うことを目標とする「コミュニケーション重視」の立場を取っています。中学校で英語の授業を原則として英語のみで実施したり、小学校高学年で英語を教科化したりするという文科省の英語教育改革は、グローバル化に対応するためコミュニケーション重視の英語教育をさらに進めようというものです。文科省の英語教育改革実施計画や有識者会議報告が求めているのは、実践的英語力つまり「使える英語」ということになるでしょう。一方、このような改革に批判的な英語教育関係者らは、学校教育では英語は文法を中心に教えるべきだと強く反対しています。
ここまではよく聞く話ですが、この議論の背景にはもっと根本的な問題が隠されているようです。それは、高校までの英語教育で実践的英語力を本当に身に付けさせることができるのかということです。もちろん政府や文科省は、高校卒業までに実践的英語力を身に付けることは可能だという立場です。これに対して英語教育の専門家である斎藤兆史東京大学教授などは著書などの中で「(学校教育で)高度な英語の運用能力など身に付くものではない」と断言しています。日本語とまったく構造が異なる英語という言語を習得するのは日本人にとって実は大変難しいことであり、意欲や学力の多様な子どもたちが40人も教室に集まっている学校で、高校卒業までに週数時間学習した程度では、とても実践的英語力を身に付けることはできないというのが一部の英語教育関係者の本音のようです。
グローバル社会では国民の多くが英語を話せるようになる必要があり、それは高校までの学校教育で可能だとする政府や文科省。逆に、高校までの教育で実践的英語力を身に付けさせるのは困難であるという前提に立って、学校教育では文法など将来のための基礎となる力を教えるべきだとする一部の英語教育関係者。言い換えれば、意思疎通が可能な程度の「使える英語」を身に付けるべきなのか、それともビジネスなどで通用するきちんとした「使える英語」を将来身に付ける際の基礎となる力を培うべきなのか、実践的英語力をめぐる英語教育改革の議論には、このような考え方の違いが根底にあると言えそうです。
子どもの英語教育を考える場合、なぜ英語を学ぶのかということを子どもと一緒に保護者のかたも考えてみてはいかがでしょうか。
2019年11月1日、文部科学省より2020年度(令和2年度)の大学入試における英語民間試験活用のための「大学入試英語成績提供システム」の導入を見送ることが発表されました。