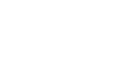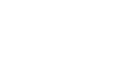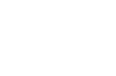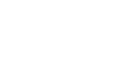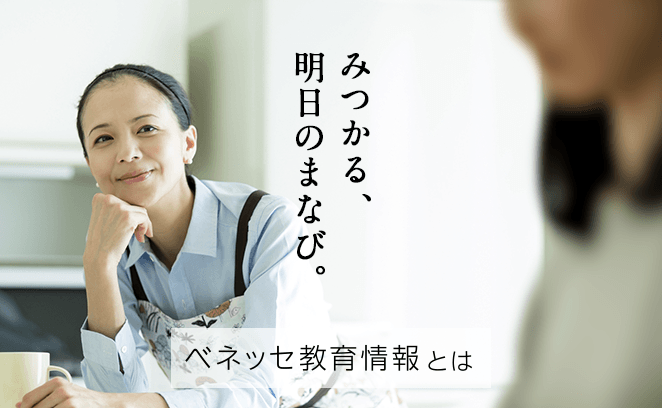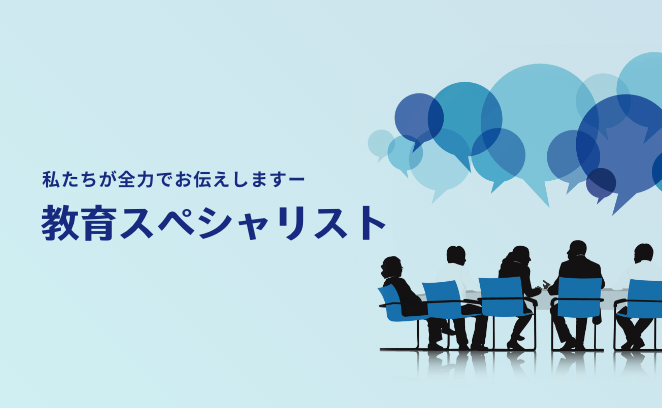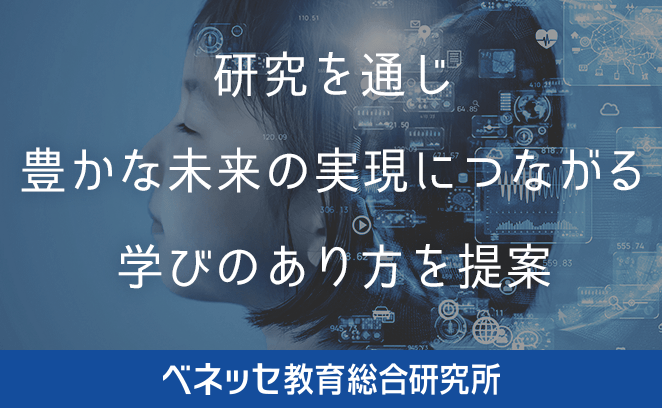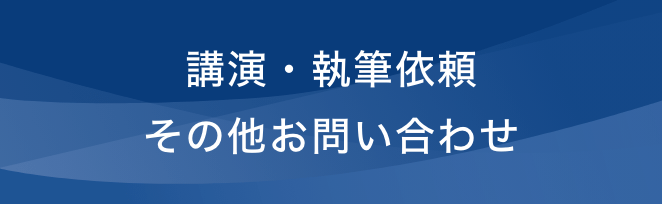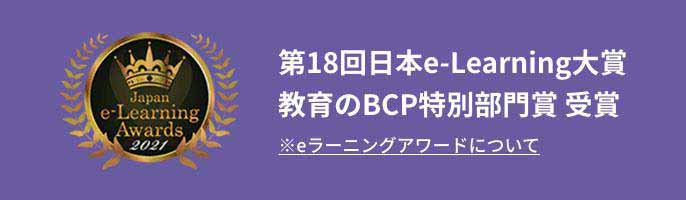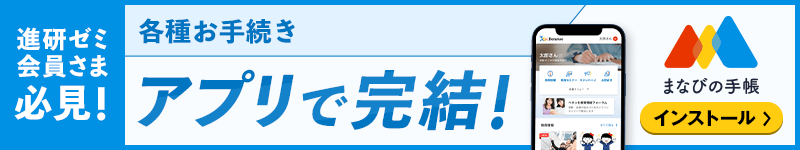高校生は部活や勉強で忙しく、やりたいことよりもやらなければいけないことのほうが多いという様子のお子さまもいらっしゃるかもしれません。
一方で、大学は自分がやりたいことを主体的に選択できる場所です。
授業にも課外活動にも豊富な選択肢が用意され、自由で幅広い学びができます。
そんな大学での学びを通じて、自身にどんな変化・成長があるのか、早稲田大学の在学生にお話を聞いてみました。
好奇心旺盛な自分にぴったりの
学びの制度が魅力で早稲田大学へ
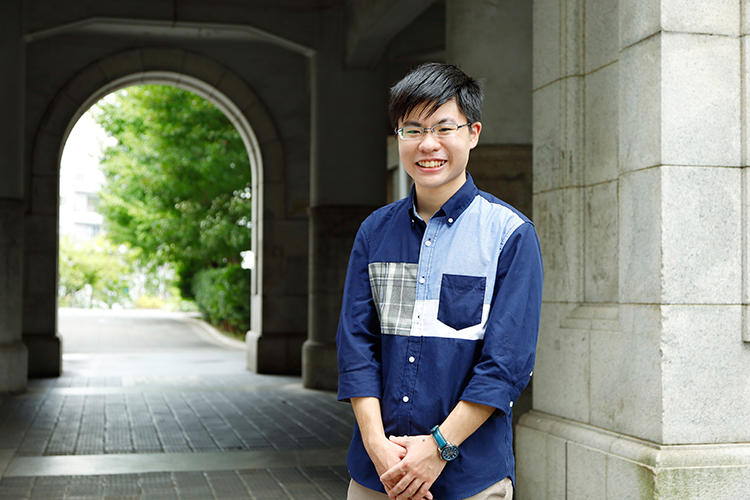
お話いただく大学生
青栁 孝信さん
教育学部 英語英文学科 3年
(千葉県立薬園台高等学校 出身)
Q.大学でやりたいと思っていたことは?
私が受験生だったとき、大学入試改革の一環で英語民間試験活用の議論がスタートし、公平性などの観点から、大学入学共通テストにおいてはその導入を断念することを文部科学省が発表しました。
たしかに英語民間試験は、会場の都市部偏在や検定料などの問題から、受験生の居住地や経済状況によって不公平が生じる可能性があります。
このことが報じられたとき、私は地域や経済による教育格差に着目し、そこから教育問題に関心を抱くようになり、教育学部を志望しました。
Q.どんな高校時代だった?早稲田大学を志望した理由は?
高校では、文化祭で上演する演劇の脚本制作や演出に取り組んだり、読売新聞社が運営する「ヨミウリ・ジュニア・プレス」の記者として取材・記事作成を行ったり、さまざまなことにチャレンジしました。
そんな中、早稲田大学の全学副専攻制度を知り、好奇心旺盛な自分にぴったりだと感じました。
全学副専攻は、所属する学部で主専攻を学びながら、そのほかの学問分野も学部を超えて学ぶことができる、自分が興味を覚えたことすべてを深められる制度です。
それが決め手になって早稲田大学を選びました。
全学副専攻制度
学部の専攻分野を問わず、特定のテーマを追求できる制度。
専攻分野を補強・応用する分野を学ぶ、第二の強みをつくるべく新たな分野に挑戦する等、活用方法はさまざま。
それぞれの「学びへの動機」や「キャリアプラン」に基づいて、興味・関心のあるテーマにチャレンジすることができる。
全学副専攻や学生参画活動をはじめ
やりたいことをすべてできる環境
Q.大学に入ってチャレンジしたことは?
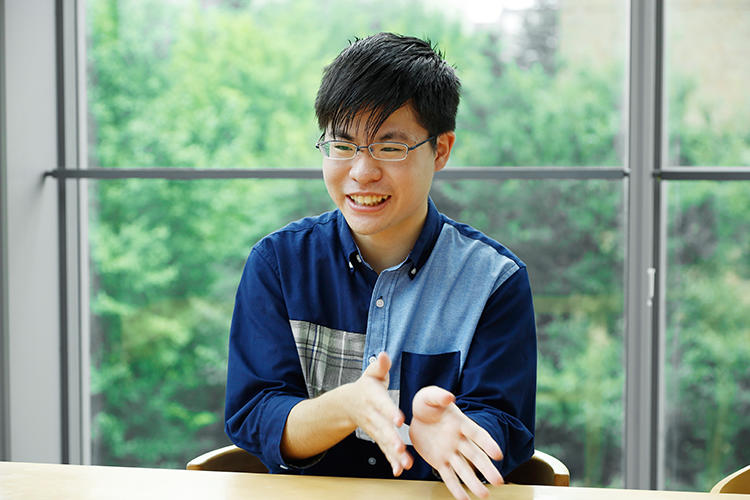
全学副専攻で、「都市・地域研究」「社会イノベーション」「政治学」「ことばの科学」を選択し、各分野の科目を履修しています。
いずれのテーマも興味のおもむくままに選んだものですが、複数分野の知識を身につけることによって、自分の引き出しが増えたことを実感する場面が何度もありました。
例えば、旅行会社のインターンシップで企画立案のワークに取り組んだ際、「都市・地域研究」で学んだ知識が活きたり、ゼミのディスカッションでは「政治学」で養った視点を基に話ができたりと、大学での学びを通じて自分も変化・成長していると感じます。
Q.学び以外で力を入れていることは?
「学生参画・ジョブセンター(SJC)」の学生スタッフとしての活動です。
その主な役割は、学生の声を取り入れながら、大学をより良くするための活動や、学生にとって有意義な体験となる企画を検討・実施すること。
オープンキャンパスのイベント、在学生に大学をもっと知ってもらうためのイベント、広く健康に関する取り組み、障がい者スポーツの普及を目的としたイベントなど、多種多様な企画を実施しています。

こうして主体的に大学運営に関わることで、自ら進んで他に働きかける力が高まったと感じています。
また、組織運営の仕組みを学ぶこともできました。この経験は社会に出たときにも必ず役に立つと思います。
Check!>> 学生がWASEDAを創る、動かす。【早稲田大学 学生参画・ジョブセンターについてはコチラ】
Q.早稲田大学の魅力を教えて!
一番は、「学生の主体的な姿勢」だと思います。
自ら考え、その内容を積極的に発信できる人が多く、それはゼミという普段の学びの場でも感じることです。
私が所属するゼミでは、様々な映画を通して文化や異なる角度からのテーマの分析を行っています。
毎回さまざまなテーマで学生が主体となってプレゼンテーションを行い、ディスカッションでさらに考えを深めていきます。
その中で、自分とは違う意見を聞いて新しいものの見方を獲得したり、固定観念を捨てて物事を多面的に考えられるようになったり、私の世界は大きく広がりました。
こうした自由に考えを発信し、意見を活発に交わすことのできる機会に満ちたキャンパスが大好きです。
自分が好きなこと、興味のあることも、
大学選びをする際の大切な基準
Q.今後の目標や卒業後の進路は?
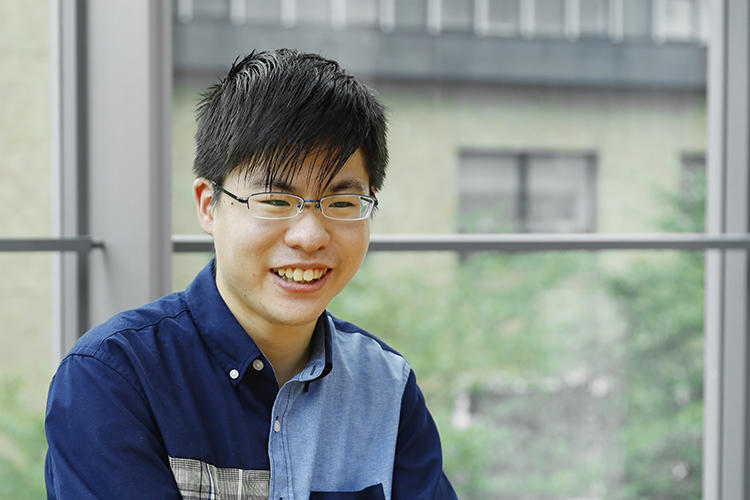
入学当初はひたすら英語教員を目指していましたが、インターンシップや就職活動を経験する中で一般企業にも興味が湧いてきました。
そのため、まずは企業に就職して社会人経験を積んでから、教員になるのがよいのではと考えています。
理想は、生徒からの一つの問いに対して、いくつもの選択肢や可能性を示してあげることのできる先生です。
学ぶべきことはまだまだ山積みですが、全学副専攻、SJC、ゼミ...大学での多様な学びや活動を通して自分の引き出しが増えたぶん、理想に少し近づけたのではと感じています。
Q.高校生へのメッセージをお願いします。
大学選びをするとき、自分が好きなことを軸に考えてみるのはどうでしょうか。
"好き"だけでなく、たとえば私が教育格差の問題が気になったように、自分が問題意識を持った事柄もヒントになると思います。
世界各国・全国各地から学生が集まってくる大学には、あなたと共通する"好き"を持つ仲間が大勢いるはずです。
そんな仲間と一緒に取り組むことで相乗効果が生まれ、学びがより深まったり、経験がさらに広がったりして、その積み重ねが素晴らしい未来をつくるのだと思います。
大学は、やりたいことに何でもチャレンジできる場所。
そこにはさまざまな選択肢があるので、やりたいことを一つに絞る必要もありません。
好きなことや興味のあることなど、今の自分の「軸」を大切に、大学選びを考えることが大切です。
保護者の皆様も、お子さまの"好き"だけでなく、日常生活の中で示したちょっとした興味について声掛けをすることで、それが進路を考えるヒントになることもあります。
お子さま自身がまだ気づいていない可能性がひらかれ、素敵な未来に出会えるようサポートしましょう。
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。