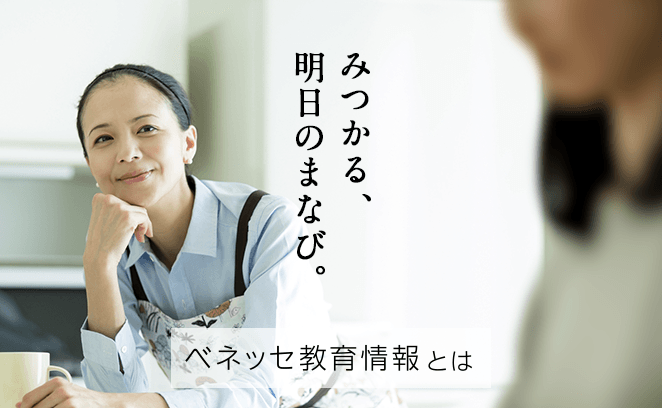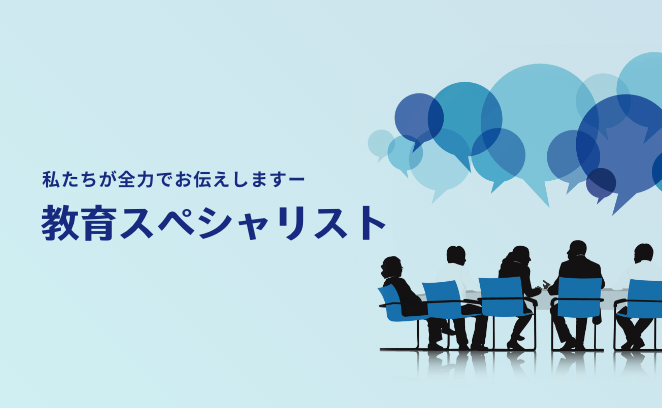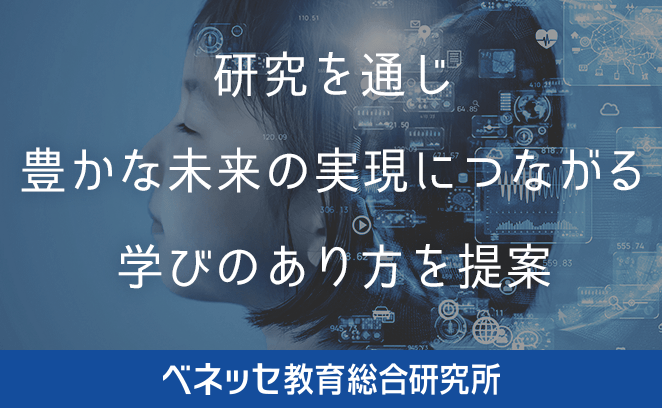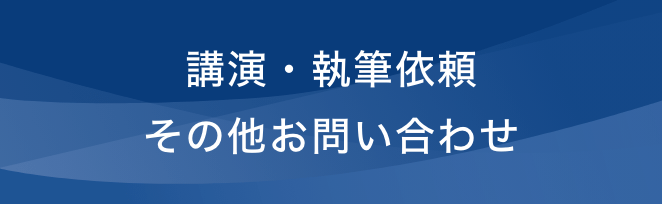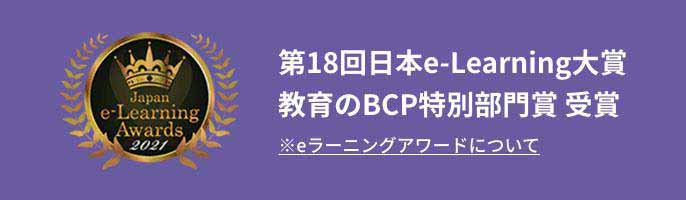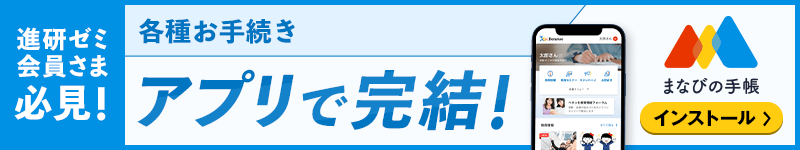「ゼミ」卒業生が語る!添削課題活用術
お子さまがこんな状況にあてはまる場合は要チェック!
□ 高校生に求められる記述力をつけてもらいたい。
□ 子ども本人は勉強しているというが、しっかり理解できていない気がする、または、定期テストや模試の成績があがらない。
□ 勉強した取り組みを実は見たい。
高校の定期テストや模試、そして大学入試では、中学生のとき以上に「記述する力」が求められます。
しかし、
記述問題は自分で採点するのも難しいうえ、自分で採点するとどうしても甘くなりがち。
また、小学生のころの宿題のように保護者のかたがみてあげるわけにもいかないのが高校生の学習ですよね。
そんなときにぜひ使っていただきたいのが高校講座の「添削課題」。
志望大に合格した「進研ゼミ」の卒業生が、「添削課題」を出して役立ったポイントをお伝えします。
最後には、「お子さまにどのように声をかけたらいいか」のアドバイスも。
ぜひお子さまへの声かけにご活用ください。
■先輩おすすめポイント1:【できたつもり】から脱却できた
自分で添削するとどうしても甘くなりがちで、テストの記述問題でなかなか点数が伸びにくい。添削課題を活用することで、自分では書けたと思っていても、より点数を延ばすためのアドバイスをしてもらえる。
(名古屋大 医学部 ねこのすけ先輩)
自分では解答に盛り込むべきポイントは全て書いたつもりだったが、赤ペン先生からのアドバイスで説明の文章が足りなかったことに気付けた。このことを踏まえて模試を受験したところ、解答不足で満点を逃すことが減った。
(東京理科大 経営学部 ゆっぽ先輩)
自分で丸付けをするときには「ニュアンスが同じだから正解。」と甘い採点になりがちだったが、赤ペン先生の添削により採点のシビアさを知り、定型文的な訳し方は正確に覚えるように改心することができた。
(明治大 法学部 くるみぱん先輩)
一人ひとりに応じた指導をしてもらえる「添削課題」ですが、記述ならではの【できたつもり】に対して効果大。
高校講座の「赤ペン先生」の平均指導年数は20年超と、長年高校生を指導し続けている先生なので、確かな教科指導力だけでなく、高校生が迷いやすいところや、ミスをしやすいところも熟知していて、一人ひとりにあった声かけをしてくれます。
■先輩おすすめポイント2:味方がいると思い心強く感じた
国語の問題で、文字数制限の記述問題で、見当外れの回答をしてしまうことがよくあった。また、選択肢の問題も、2択までは絞れても、そこから確定できないということがよくあった。そのためコメント欄で、「どのように対策すればよいのか」を書いたら、詳しい対策方法を教えてもらえた。勉強内容だけでなく、勉強全般を支えてもらえるため、味方がいると思い、心強く感じた。
(中央大 法学部 なべ先輩)
自分一人で勉強していくのはかなりメンタル面でもつらいので、このように誰かが採点してくれたり自分の弱みを知ることができるというのは非常に良かった。
(東洋大 国際学部 ハニー先輩)
「添削課題」では、答えを教えてもらえるだけではありません!
式や解いた手順のメモ、計算の跡や会員からの「ひと言」など、解答用紙に書かれたことを隅々まで確認し、一人ひとりの考えたプロセスやクセを読みとり、指導を行います。
疑問に思ったことについても教えてくれるほか、気持ちの受け止めも。
添削課題が心の支えとして役立ったという声が上がっています。
また、保護者からの声を素直に聞くのが難しい年ごろでも、赤ペン先生のアドバイスは素直に聞き入れることはできた!という声も。
親でも友達でもない、第三者である『赤ペン先生』だからこその距離感がいいのかもしれません。
■先輩おすすめポイント3:自分なりの使い方ができた
小学生、中学生のころに添削課題をご活用いただいているかたからすると、その月の仕上げやまとめとしてのイメージがある、という声を多くいただきます。
もちろん、月の仕上げやペースメイクとして活用いただくことも多い添削課題ですが、定期テスト前に単元の定着確認のためにまとめて提出するかたや、夏休み・冬休みにじっくり取り組むかた、ほかにもこんな使い方をされている卒業生もいます。
テスト前活用派
とにかく定期テスト1週間前までにそれを全部解いて提出することにはしていました。3日ほどで返却されるので、テスト1週間前ぐらいに提出すればテストの日までには答案を復習できます。例えば数学なら証明などで気をつけたいことを思い出せました。自分で問題集を解いているときは証明で何を書き忘れているか分からないけれど、添削課題で自分以外の人に見てもらえれば書き忘れを教えてもらえます。返却された添削課題を確認した日からテストがある日までがそんなに時間が空かないので、添削課題で抜けていたところを補完してテストを受ける事ができ、テストの点数の減点を抑えられて嬉しかったです!
(愛知大 文学部 しゃお先輩)
わからない箇所の指導希望派
「ここ何書けばいいかわからない~!」と書いて送って、そもそもの書き方から教えてもらったことがあります…
(愛知大 文学部 しゃお先輩)
お読みいただいてお気づきかもしれませんが、「添削課題」は「テスト」ではないのです!
そのため、そのため、解答以外にも、「ここがわからない」「ここを教えて」と書いて教えてもらう、という使い方もできます。
■お子さまへのおすすめ声かけ
お子さまに「添削課題を出したら?」なんて言ってももう素直に聞く年ではない、という声もききます。
そんなときには、ぜひ今回の「先輩の声」をもとに
「解けなくてもだしていいらしいよ」
「こうやって定期テストや模試の成績があがった「ゼミ」の先輩がいるらしいよ」
など、体験談をもとにぜひお声かけをしてみてくださいね。
■返却された添削課題は保護者のかたもご覧いただけます!
高校講座で子どもが学習している様子がよくわからない、というお問い合わせをいただくことがありますが、実は返却された添削課題は会員ページから確認が可能です。
ぜひ保護者のかたもご確認くださいね。
※お子さまの会員番号でのログインが必要です。
※郵送返却を選ばれた場合を除く。
この夏,お子さまの添削課題への取り組みをお待ちしております。
※この記事は、公開日時点の情報に基づいて制作しております。