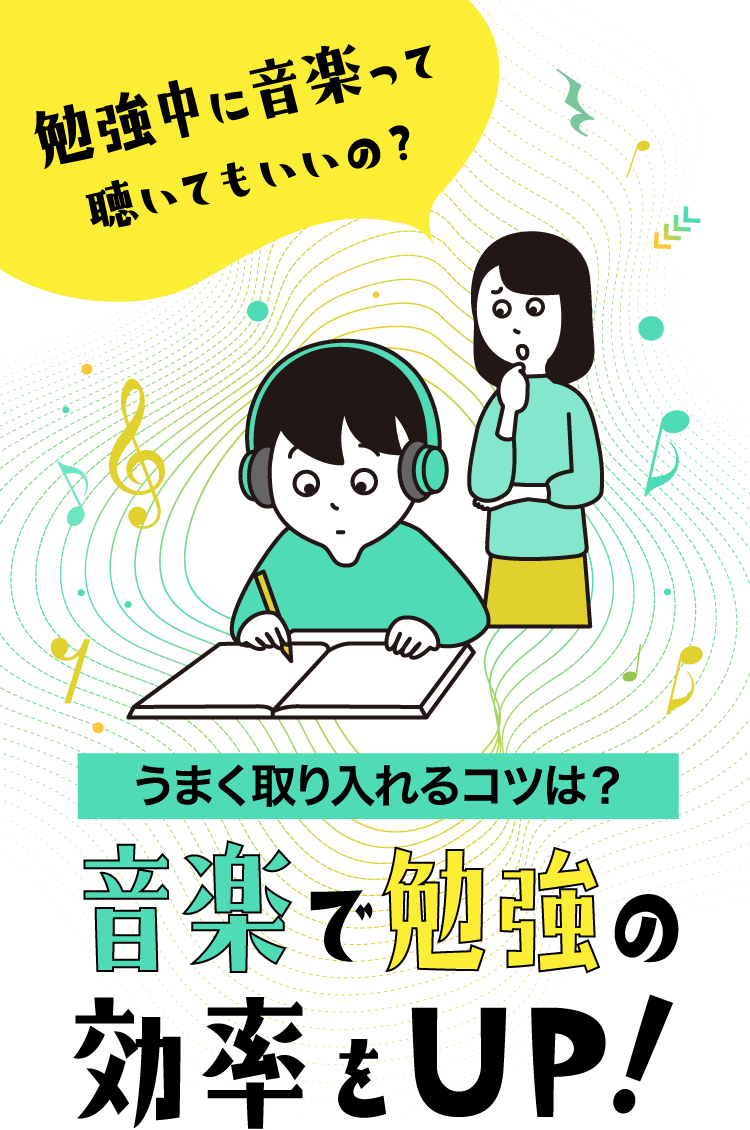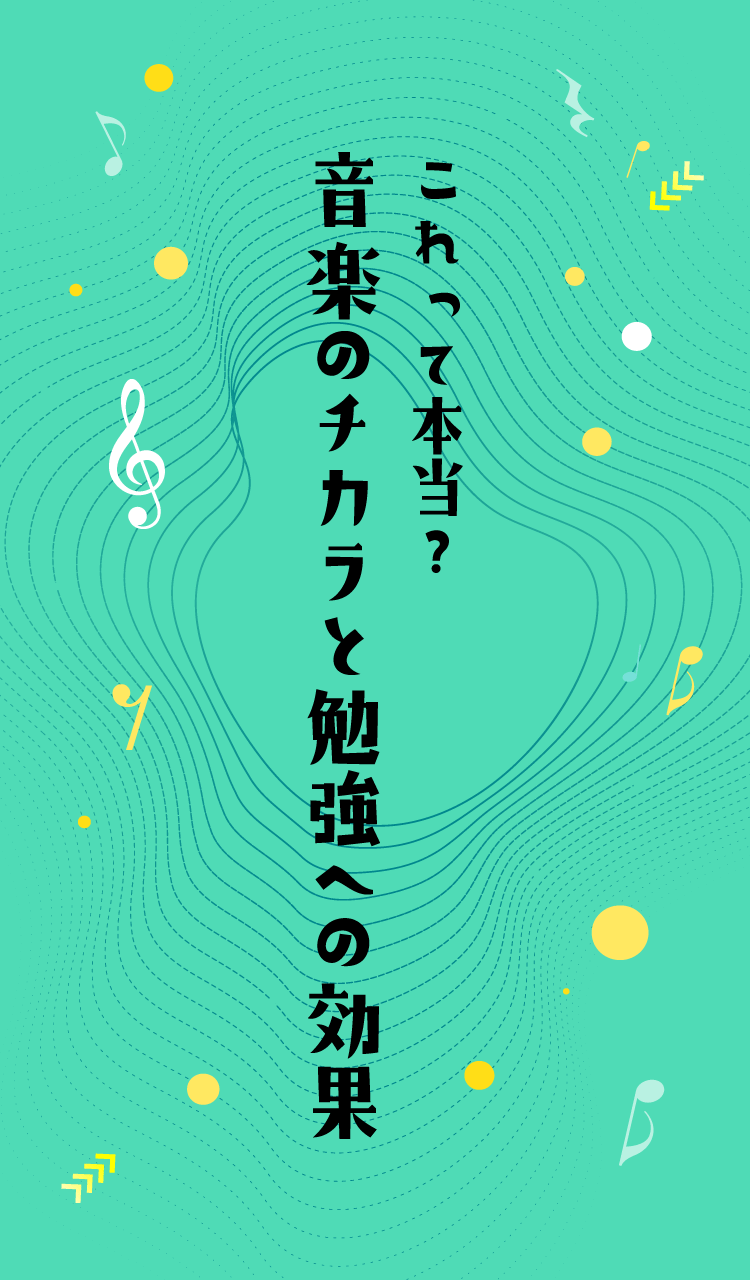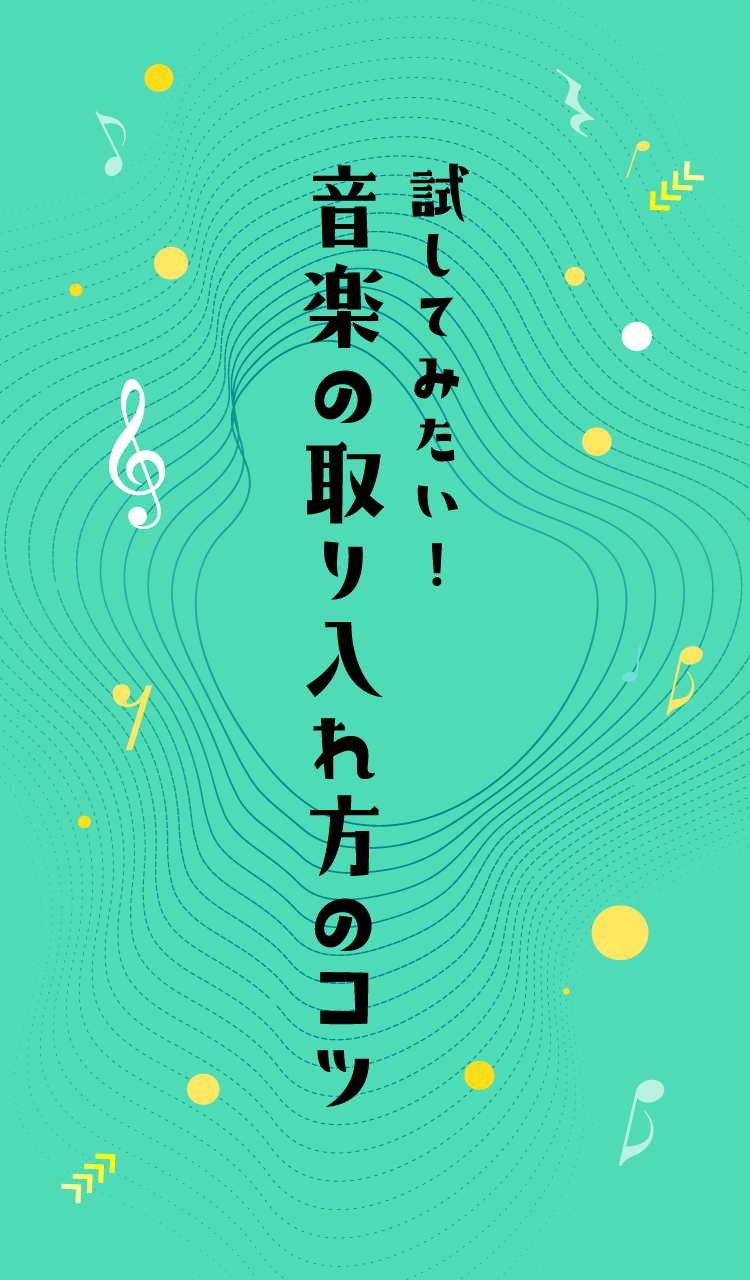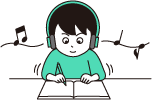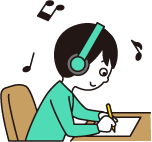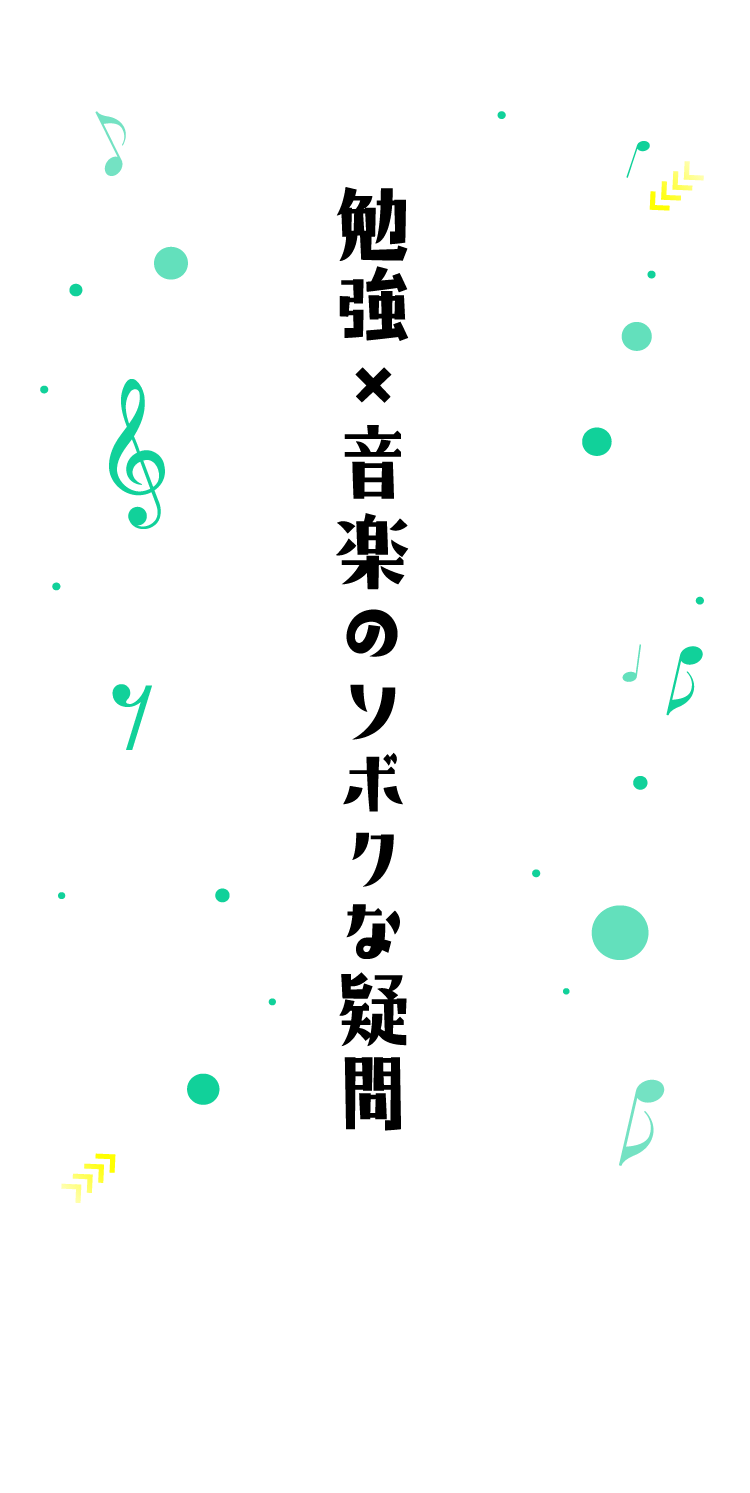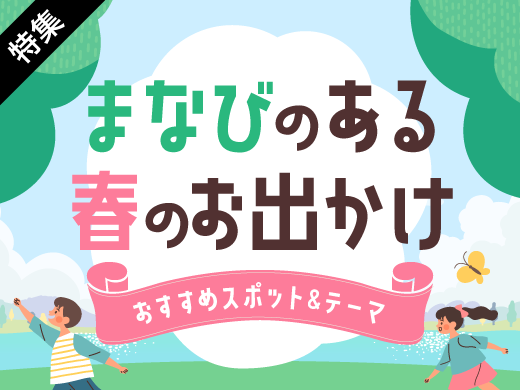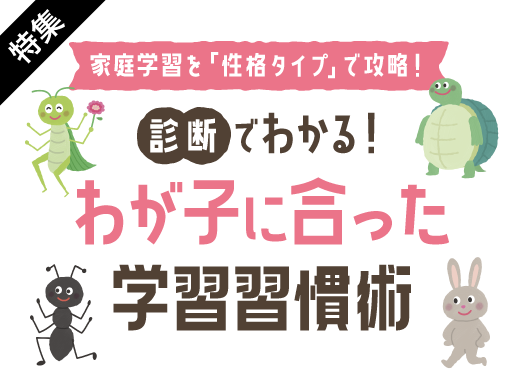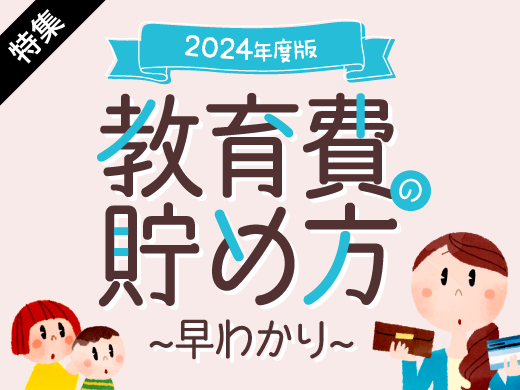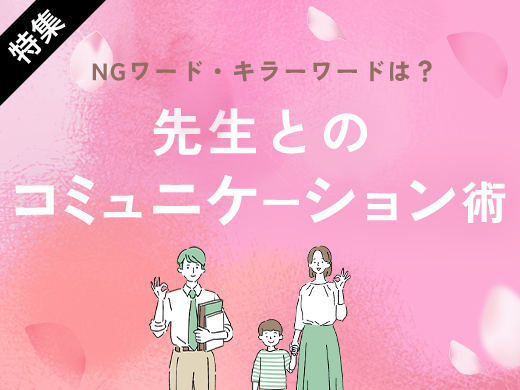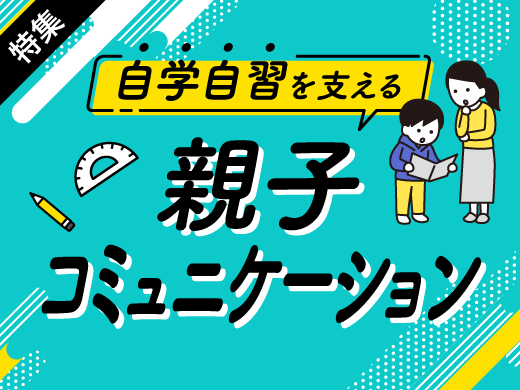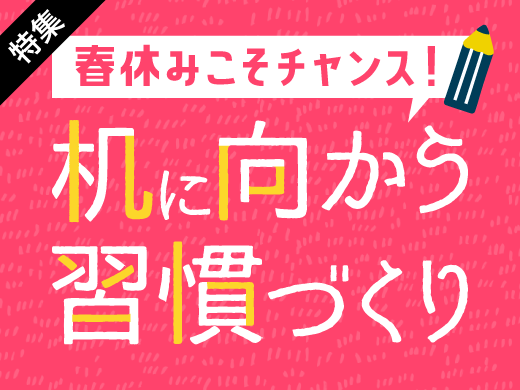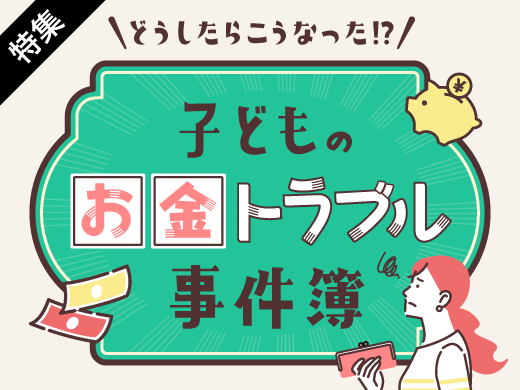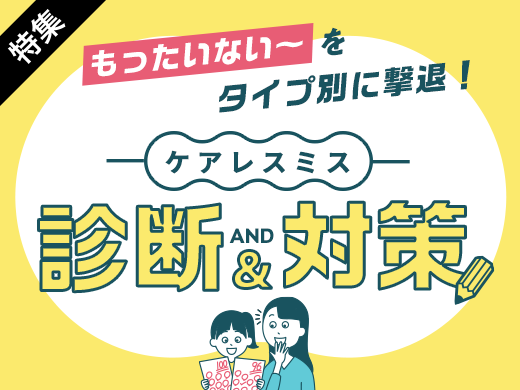今週の特集![]()

勉強のきっかけに音楽は有効?
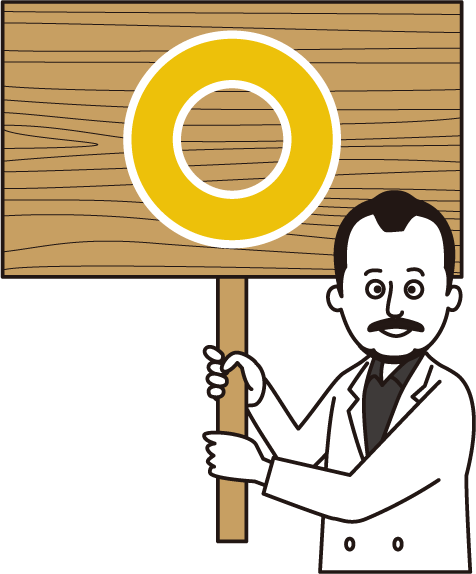
心地よいリズムが体を動かし始める後押しをする
心地よい、ウキウキするようなリズムを持つ音楽は、一般的に体が動き出すイメージを喚起しやすいことが知られています。諸説ありますが、音楽は、鳥のさえずりにルーツがあるという説が有力です。オスの鳥が美しいさえずりでメスを自分のもとに飛んでくる気持ちにさせるように、音楽を聴くと体が動き出す脳の働きが生じると考えられているのです。

音楽はパフォーマンスを上げる?
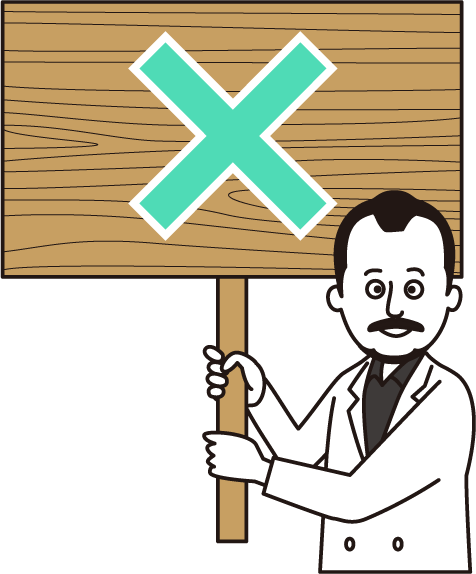
人ごとに脳が自主的に「この音楽は自分のパフォーマンスを上げる」と判断している
スポーツ選手が練習や試合前のルーティンとして音楽を取り入れるという話を聞いたことはないでしょうか。これは、その音楽が自動的に集中させたり調子を上げさせたりするわけではなく、脳が「この音楽を聴くと集中できる」と判断し、自分で条件付けをしているのです。
特に、一度「この曲を聴いたら調子が上がった」という経験があると、同じ音楽を聴くことで調子がよかった時の自分の心理状態が思い出され、パフォーマンスが引き出されやすくなります。

勉強には落ち着いた曲を選ぶべき?
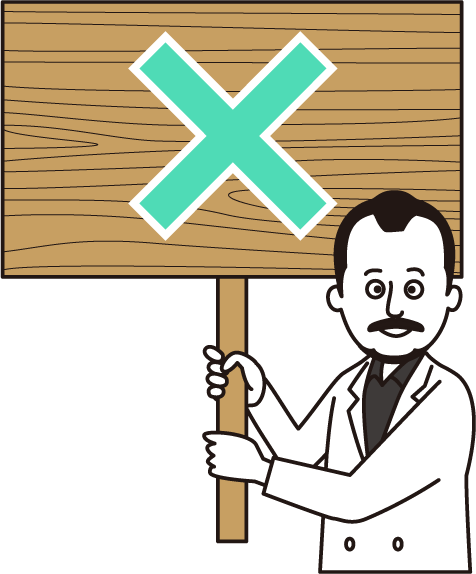
誰にでも効く音楽はない
AIの研究開発の進歩によって、脳は外の世界から与えられる刺激をそのまま受け取るのではなく、自分なりに判断して反応していることがわかってきました。一般的に集中しやすい音楽・やる気が起こりやすい音楽があるとしても、それは他と比べると統計的にそうした脳の反応をする人が多いという傾向の話なのです。
脳の反応は人それぞれで、激しい音楽を聴いて気持ちが落ち着いていく人や、テンポのよい曲で寝付ける人もいます。学習は自分のためのものなので、効果につなげるなら自分の感覚を大切にしましょう。
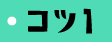 勉強を始める時の「気持ちが上がる曲」「落ち着く曲」
勉強を始める時の「気持ちが上がる曲」「落ち着く曲」

気持ちが上がる曲や元気が出る曲は、身体的なスイッチを入れる効果があります。体が動き出すと、脳の線条体という部分が活性化してやる気のもとになるドーパミンを放出し始めます。嫌なことばかり考えてしまう時も、気分を変えてくれるでしょう。
いろいろなことが頭に浮かんでくる時、何かに興奮して落ち着かない時は、自分がリラックスできる音楽を選ぶとよいでしょう。いったん脳全体を沈静化させることで、勉強に向かいやすくなり、勉強に必要な部位を集中的に活性化させやすくなります。
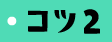 勉強中の音楽は臨機応変に使い分け
勉強中の音楽は臨機応変に使い分け

脳は、一度行動を始めると、それを続けられるようにできています。集中し始めたら音楽はなくてもよいでしょう。ただ、邪魔になっていなければ、消すべきというほどでもありません。集中が途切れる時に音楽があることで落ち着きや気持ちをキープできることがあるからです。
単純作業や難易度低めの課題は音楽で効率が上がりやすい
勉強中、脳はいろいろな情報をメモしながら処理しています。脳内に必要なメモのスペースが少ないと、余ったところに他の情報が入り込み、気が散りやすくなります。ここを音楽で埋めることで、集中を維持して効率を上げる効果があると考えられています。
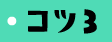 「継続は力」と「去るものは追わず」
「継続は力」と「去るものは追わず」
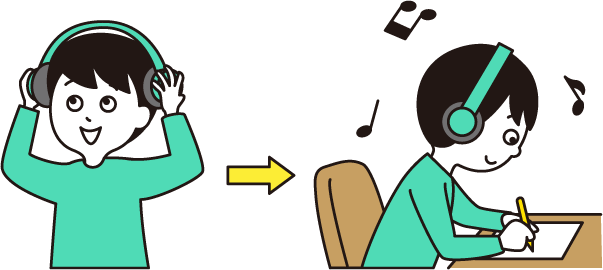
「この音楽を聴いて勉強すると、いい感じだな」と思ったら、その効果を信じてくり返してみましょう。ルーティンになるほど、脳が予測的に音楽に反応するようになって、スムーズに勉強できるようになります。
一方で、同じ刺激に対する脳の感度は次第に弱くなってくるという特徴があり、効果は永遠には続きません。実際の調子には波があり、思うようにいかないことでも効果は薄れます。うまくいっている時はその方法を信じ、ダメなら固執せずに次の方法を探すという柔軟性を持っておくことが、脳とうまく付き合うコツです。
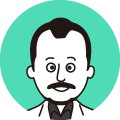
歌詞がある曲は勉強に向かない?
そうとは限りません。
歌詞の有無よりも、自分の脳が歌詞にどう反応するかがポイントです。歌詞に耳を傾けてしまう、言葉を聞き取ろうとしてしまう場合は、脳の言語野が活動を始めるため勉強の邪魔になります。歌詞のある曲でも、歌詞を覚えてしまって聞き流せるようなら影響は少ないでしょう。
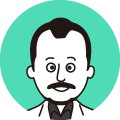
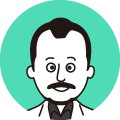
「集中できる曲」を聴いても集中できません。どうして?
「すべての人が集中できる曲」ではないからです。
たとえば「アップテンポな音楽」は、統計的に元気に・前向きな気持ちになる効果を感じる人が多いということはいえますが、効果の有無や程度は人それぞれです。自分が「この曲は集中できる」と思えれば、それが「集中できる曲」です。
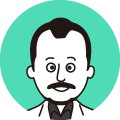
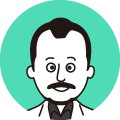
周囲の雑音が多い環境は勉強に向かないですか?
自分にとって雑音かどうかが大事です。
私たちの周囲には常に多少の音があり、どの程度の音を雑音と感じるかは人により異なります。加えて、脳には聞きたい音以外の音を排除するコントロール機能もあります。ただし、普段聞いたことがない音には注意が向きやすいので集中しづらくなるでしょう。別の視点では、雑音に人の気配を感じ、安心感から気持ちが落ち着き、作業が進むということもあります。
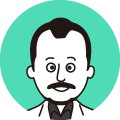
脳は周囲の情報や刺激にただコントロールされるのではなく、自分で判断して反応しています。自分に合った音楽を見つけたらどんどん活用を。効果がなくなってもガッカリせずに、上手に音楽の力を借りましょう。