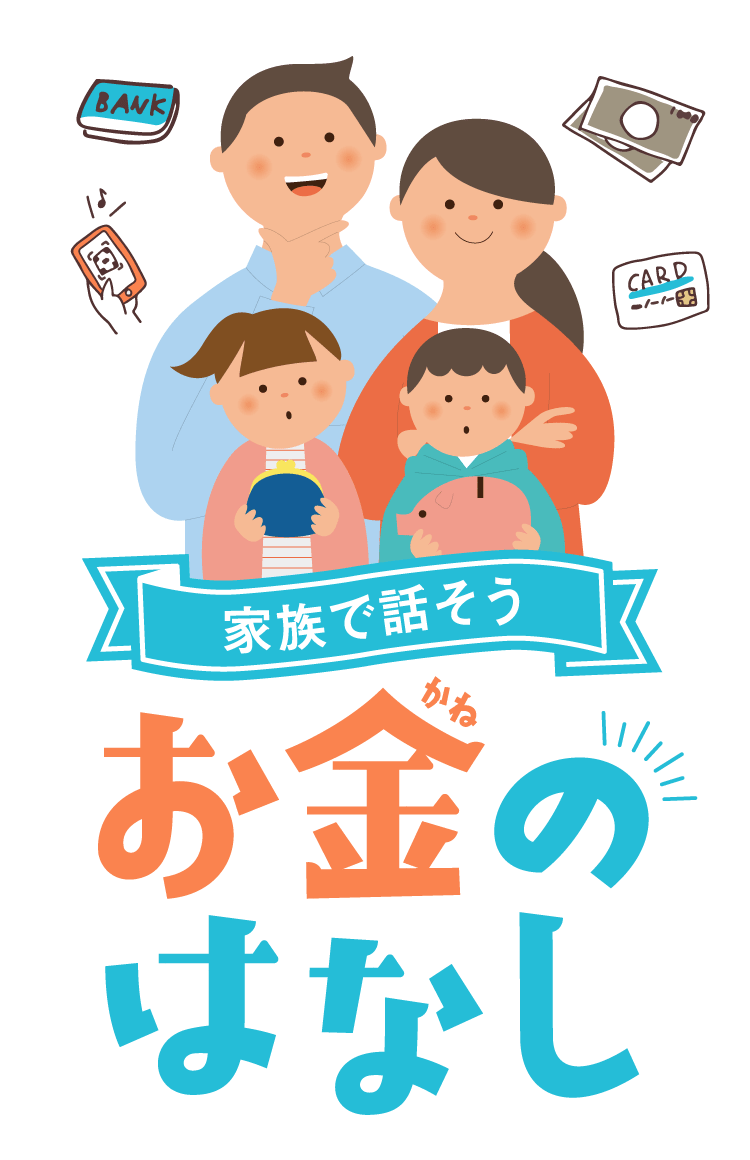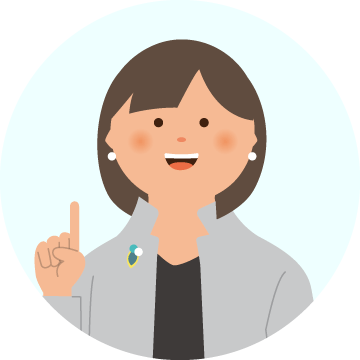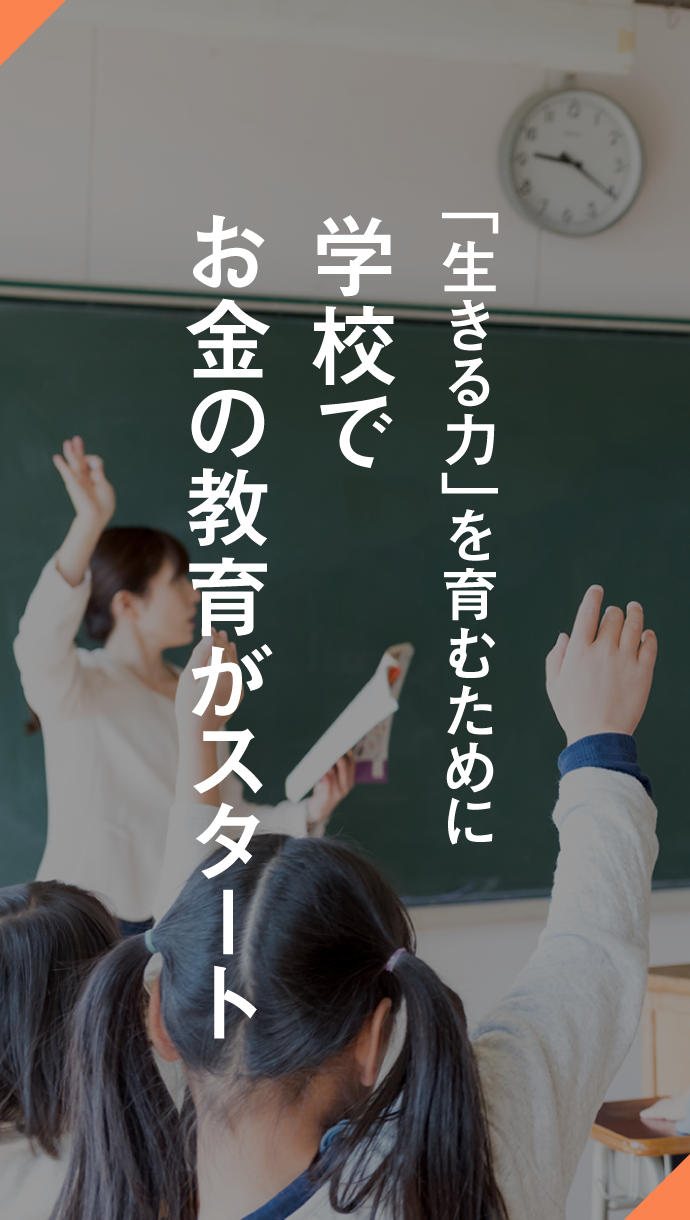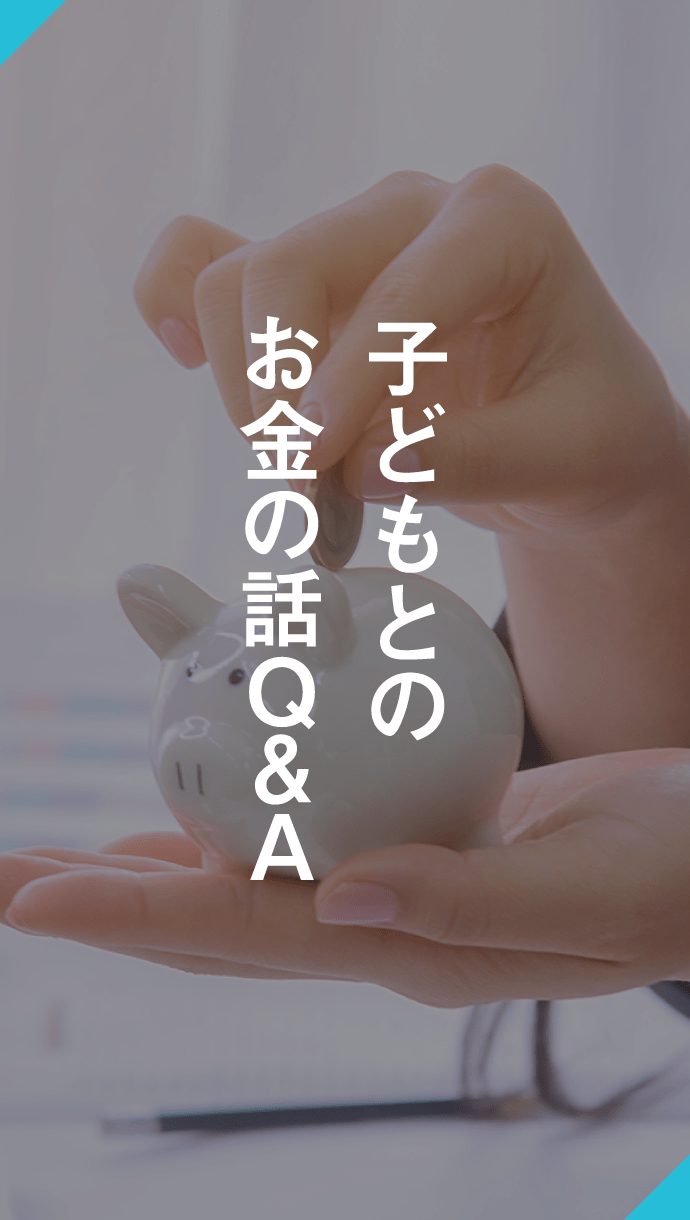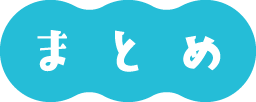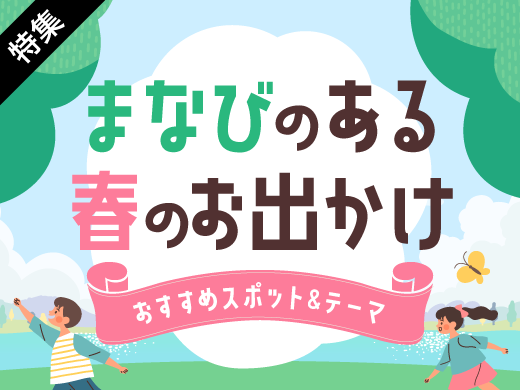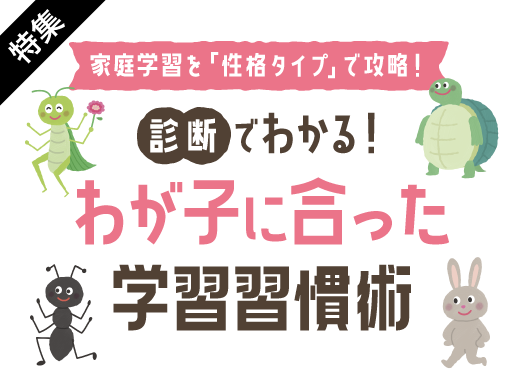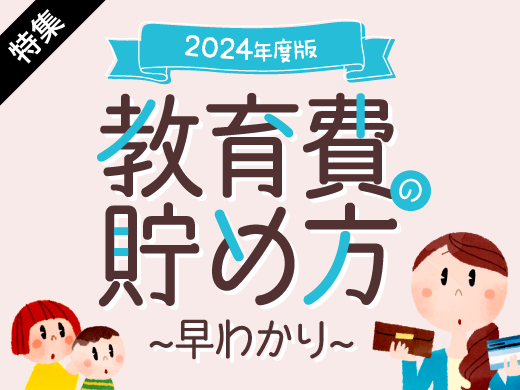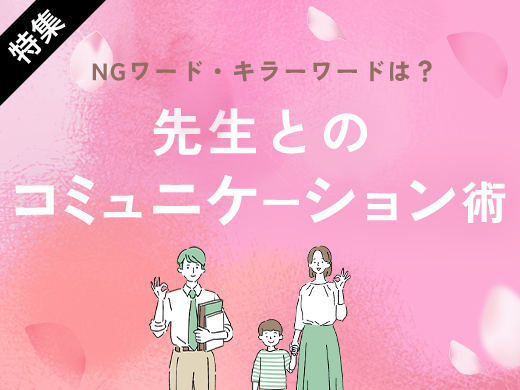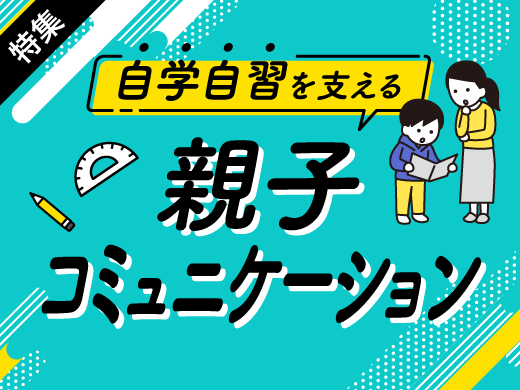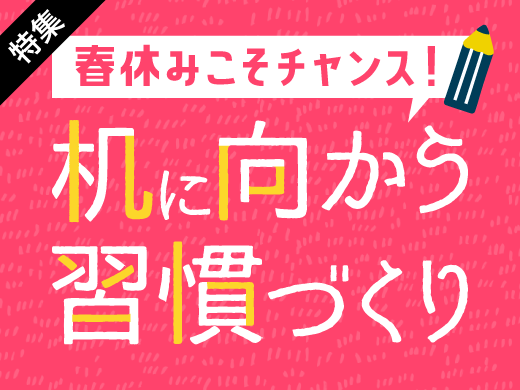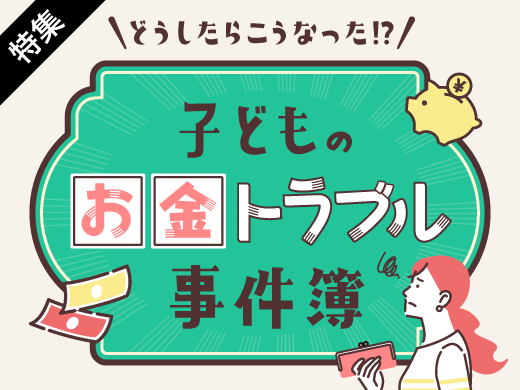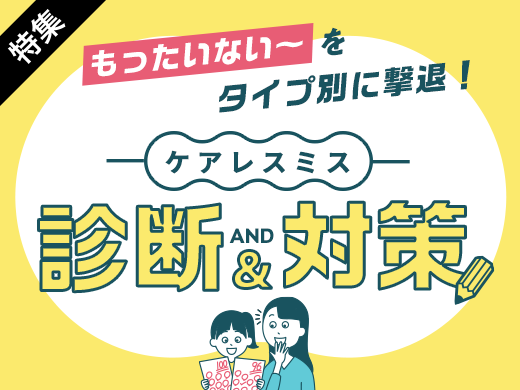今週の特集
学校でお金の教育が始まっています
学習指導要領の改訂により、小・中・高校ではお金の教育がスタートしています。しかし、なぜ始まったのか、授業はどんな内容なのか、家庭では子どもにどんな話をすればいいのか、わからない保護者のかたも多いことでしょう。始まりつつある学校でのお金の教育の現状と、親として子どもに伝えておきたいお金の話について、解説します。
2022年度からスタートした学習指導要領(小学校:2020年度〜、中学校2021年度〜、高等学校2022年度〜)では、「生きる力」を育むことを重要なポイントとしています。それは、変化が激しい現代の社会の中では、自分で目的や課題を見つけ、達成していく力がより求められるからです。その一つとして、生きるために必要不可欠なお金について理解しておくことが重要であるということで、学校で金融教育が始まりました。
小学校では総合、中学校では家庭科、高校では公共・家庭科の授業で、お金について学ぶ授業が導入されていますが、内容は自治体や学校によってさまざまです。例を挙げると、中学校では「情報を活用した上手な購入の仕方」や「売買契約」のこと、また「家庭における収入と支出」、収支バランス(赤字、黒字)や計画性などについて学んだり、社会科(公民)では、アクティブラーニングとして企業の企画書作成や、国際社会での貧困問題も扱ったりしています。
保護者の皆さまの世代では、「お金のことを人に話してはいけない」「子どもがお金のことに口を出すのはよくない」という風潮であったかと思います。しかし今は、将来子どもが社会に出て自分の力で生きていくためには、お金についての正しい知識を持ち、必要に応じて家族でもお金のことを話し合うことが重要であると考えられるようになってきました。
保護者の方々からよく相談されることをまとめました。
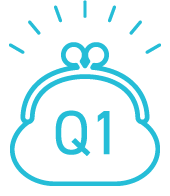 金銭感覚を
金銭感覚を
身に付ける方法って?
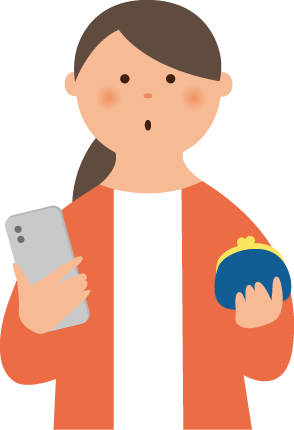
キャッシュレスが普及した今、子どもが正しい金銭感覚を身に付けられるのか心配です。
交通系ICカードなどにお金をチャージして支払いをするのは、とても便利なしくみです。がその一方、何と何をいくらで買い、自分の残高がどのくらい残っているのかが感覚的に把握しづらい面があります。たとえば子どもだけでコンビニエンスストアに行き、お菓子を2つ買った場合、意図せずお友達の分も購入したままになってしまい、保護者もそれを把握できないなどの状況が起こり得ます。
子どもに社会性が出てきた時、このようなことがもめごとのきっかけとなるリスクもあるため、まずは現金を使ってお金の使い方を練習することをおすすめします。
たとえば同じように手元に500円があった場合、現金のほうが、お菓子を買うために200円使ったら、手元には300円残るといったことが実感できますし、子どもが「お金とは、欲しいものを手に入れるために交換するものである」ということを理解しやすく、金銭感覚が身に付きます。
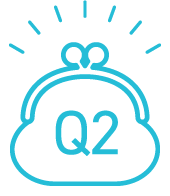 子どもには、おこづかい制と、
子どもには、おこづかい制と、
都度お金を渡す制度、
どちらがいいのでしょうか?
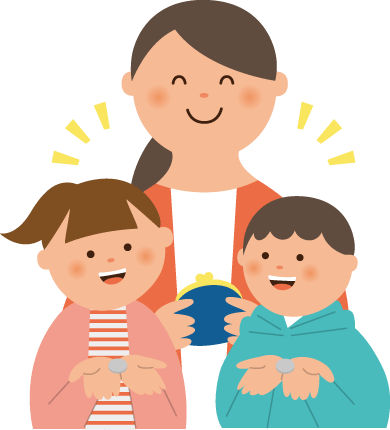
お金を使う練習としては、「お金を予算制約の中で使わせる」ということが大事なので、おこづかい制のほうが適しています。
その月にもらう一定額のお金で、次の月までやりくりする必要がありますし、すぐに使い切ってしまったとしても、その失敗により、次は工夫してやりくりしようと考えられるようになります。また、自分の欲しいものや、誰かにプレゼントを買いたいなど、未来の目標に向かって、おこづかいを全部使わずにためる楽しみを学ぶこともできます。
毎月3か月先まで見えるようなおこづかい管理帳を作り、子どもが「ここでこのくらいお金を使いたい」と記入して計画を立てるのもおすすめです。このような習慣が身に付くと、将来的に自分で家計を管理することにも役立ちます。
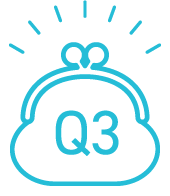 子どもに親の給料を聞かれたら
子どもに親の給料を聞かれたら
答えるべきでしょうか?
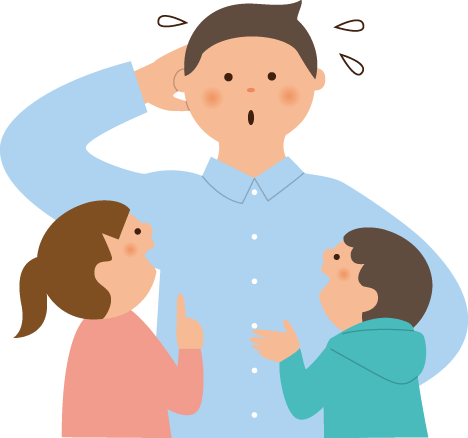
お給料の金額を教えるのではなく、生活するために得るお金は給料だけではない場合もあること、お給料のもらい方にも、毎月定額をもらう場合だけでなく、時給・日給制や、年俸制、成果物に対してお金を得る方法などがあり、職業や働き方によって、異なることなどを話してあげるといいでしょう。
お金の稼ぎ方も、今の時代は本当にさまざまです。会社で働きながら副業も行ったり、投資やフリマアプリなどでの売買、動画の再生回数でもお金を得ることができたりします。
もし子どもが興味のあることや、将来なりたい職業があるならば、そのことを題材として、その職業で働くことで見込める収入や、現実的には一部の人しか高収入を得られない世界があることなど、お金について親子で話し合うこともできると思います。
また、お給料として入ってくるお金はすべて使えるわけではなく、税金などが引かれ、そこから生活必需品や光熱費、家賃など、優先順位の高いものから支払っていく必要があることなども伝えていけるとよいでしょう。
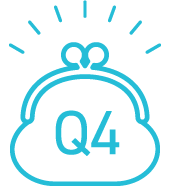 親子でお金を学ぶのに
親子でお金を学ぶのに
便利なツールはありますか?

金融庁などのHPでは、小学生から大人まで、さまざまな年代に向けたお金についてのガイドが紹介されています。ゲーム感覚でできるもの、ライフプラン・家計管理、資産形成・借金のシミュレーションができるものなど、楽しみながら学べるものがありますから、お子さまと一緒にやってみて、家族で話し合いながらお金への理解を深めていきましょう。
金融庁
小学生、中高生、社会人になる人向けのパンフレットや教材があります。
知るぽると
暮らしに役立つ身近なお金の知恵・知識情報を知ることができます。
ひと口にお金について学ぶと言っても、使う、ためるだけではなく、家計管理や生活設計、投資、借りるなど、非常に多岐に渡ります。お金について気になることがあったら、子どもと一緒にいろいろと調べてみて、日常的にお金の話をどんどんしていきましょう。