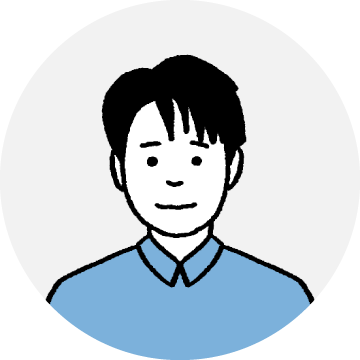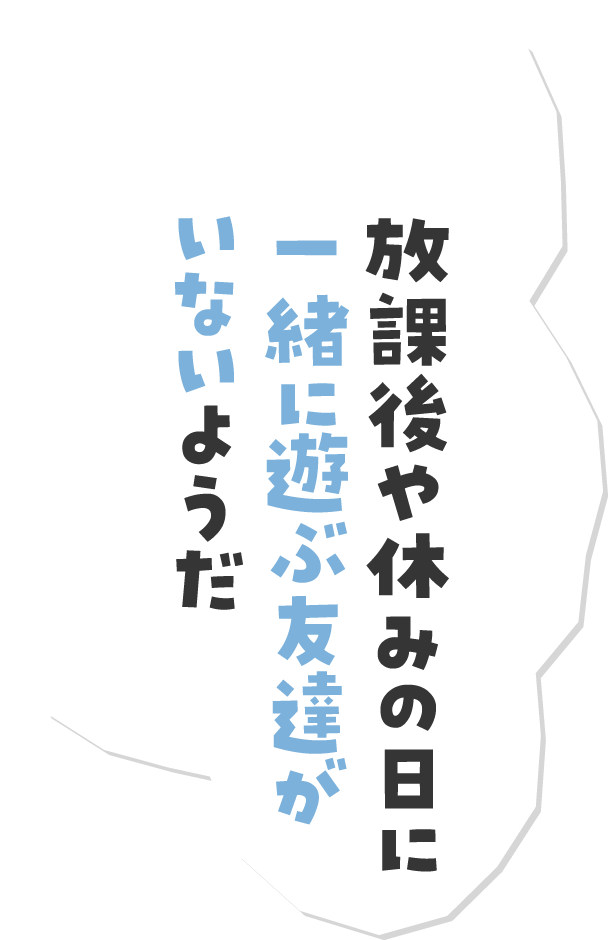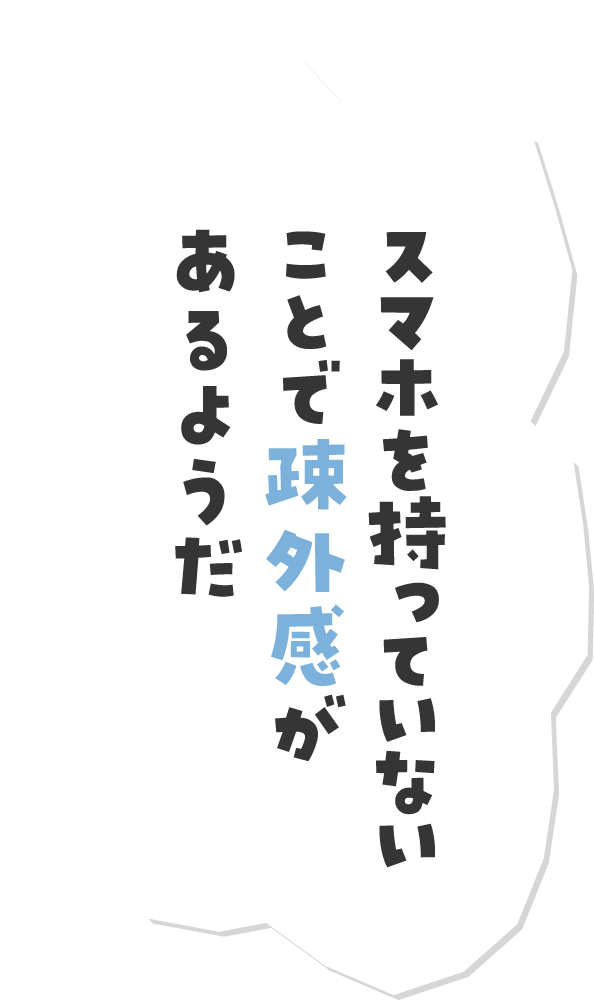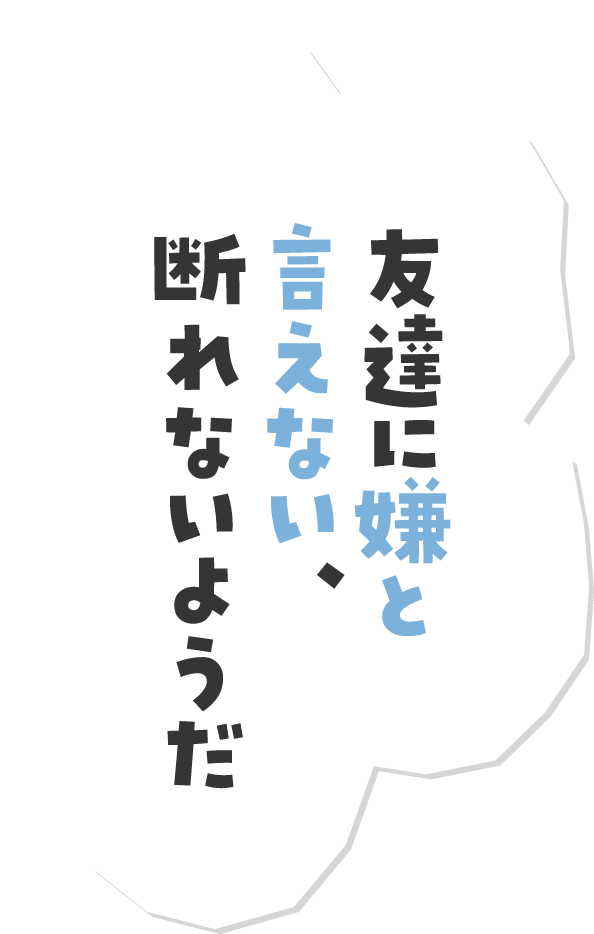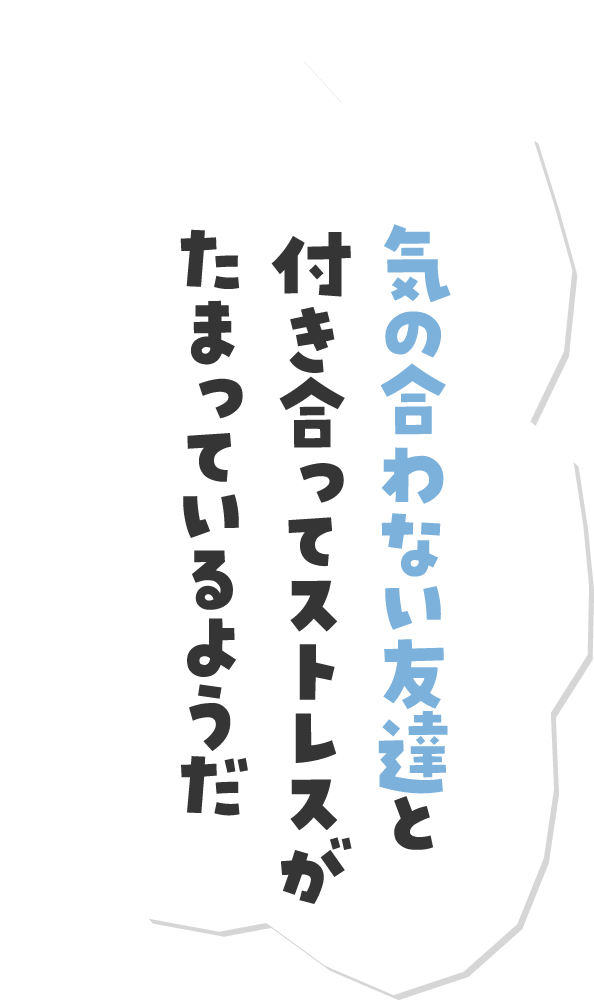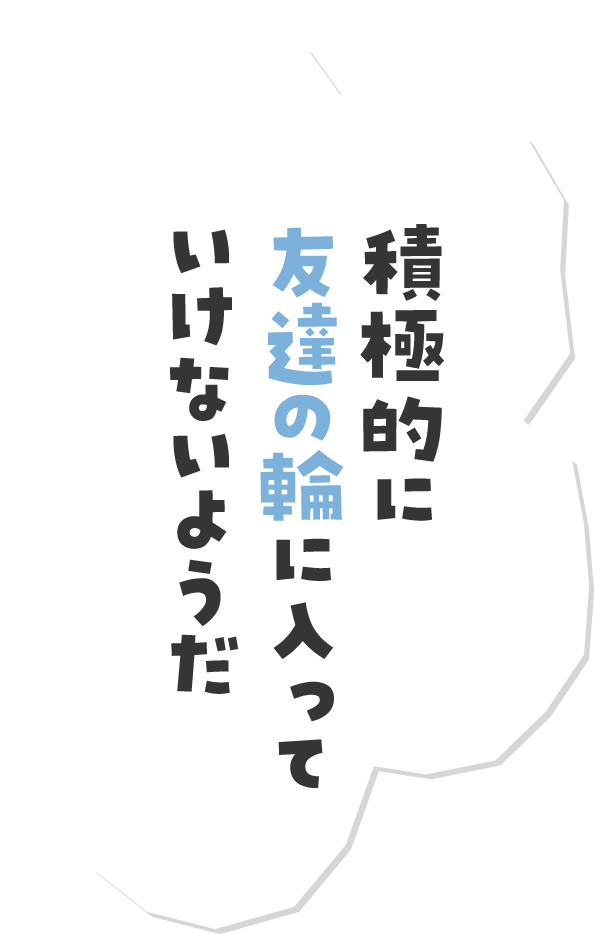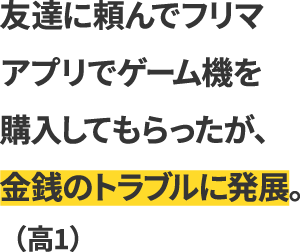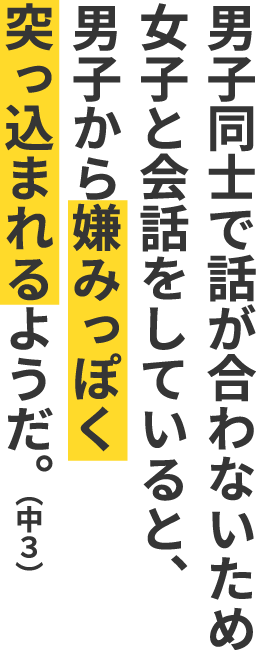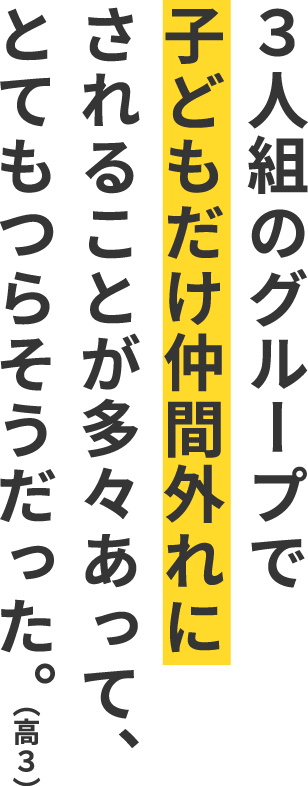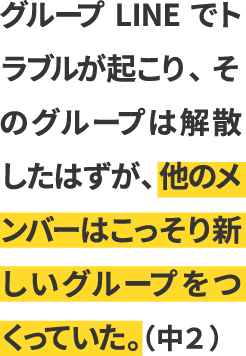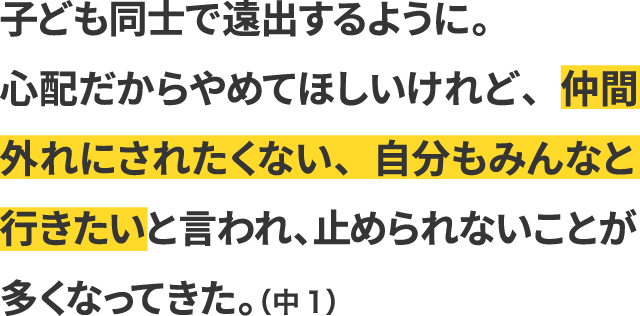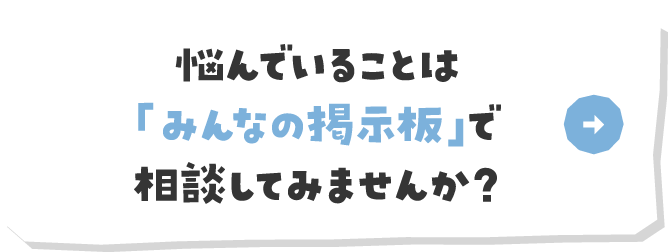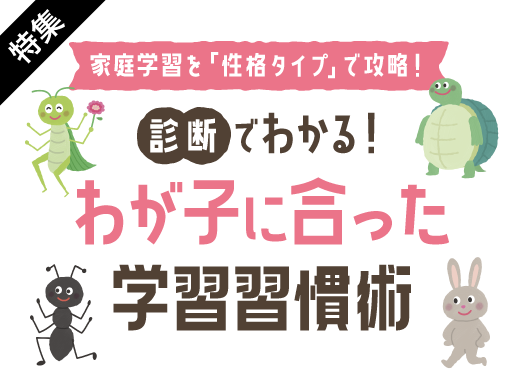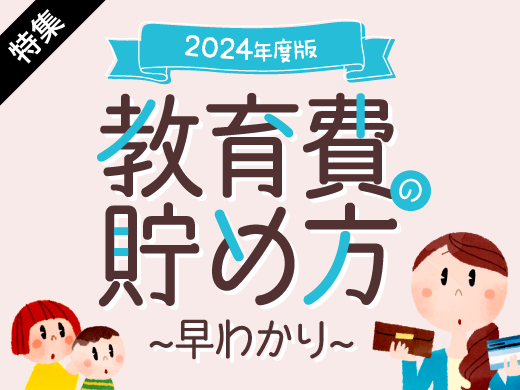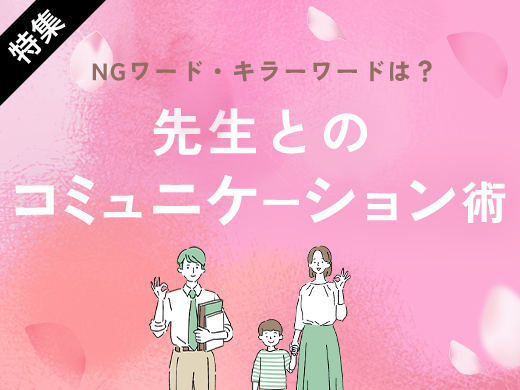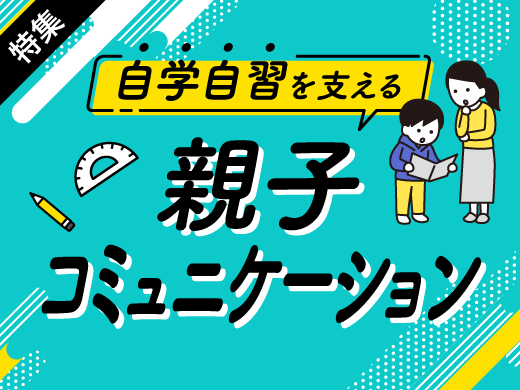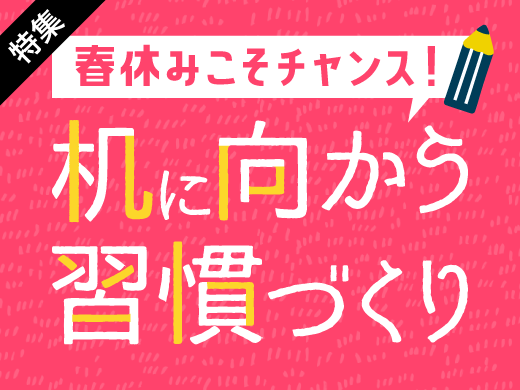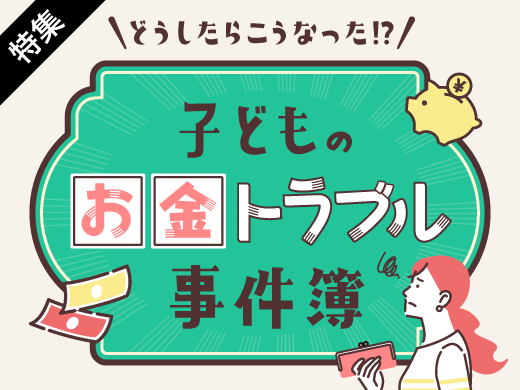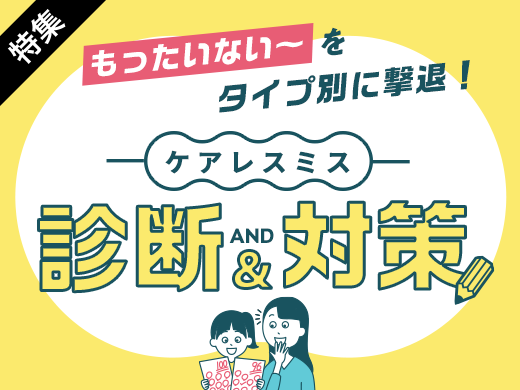今週の特集
新年度開始から約1か月が過ぎ、新しい友達にも慣れてきた頃でしょうか。子どもの友達付き合いが心配だったり、よそのご家庭はどんなふうだろう……と気になったりすることはありませんか? 保護者の皆さまに行ったアンケート結果について、公認心理師、臨床心理士、学校心理士として活躍する松尾直博先生に解説していただきました。少しでも参考になれば幸いです。
時間を持て余す日にも友達を誘うこともまったくなく、母と一緒に買い物。
(中1)
学校外で友達との交流がない。学校生活でも特定の誰かといるよりも、我が道を行っているようだ。
(中3)
コロナ禍で遊ぶ習慣がなくなった。部活に入っていないため、春休みを持て余している。
(高3)
部活や塾などで予定が合わない、仲のよい友達が遠方に住んでいる、おこづかいが足りないなど物理的な理由で遊べないことも。また中高生になると、実は部屋の中でSNSやオンラインゲームを通じて友達交流している、という場合もあります。お子さまが家にいるのが苦ではないようなら、家族で楽しく過ごせればよし、と発想を転換してみるといいかもしれません。
クラスメートの8割強がスマホを持っている。クラスのグループLINEでどのようなやりとりがされているのか気になるようだ。
(中2)
クラス、学年などでトークグループがつくられているようで、スマホをまだ持っていない我が子は、みんなの会話に入っていけない、と訴えている。
(中2)
スマホを持っていないことで話の輪に入れないことがよくあるようです。部活ではうちの子以外の全員がスマホを持っているため、会話に加わろうとしても無視されることがあるようです。
(中2)
中学生のスマートフォンの所持率は8割近くとなり、持っていない子は少数派です。友達との交流に不利であるのは確かですが、その分学校での会話を楽しむなど、お子さまが別の方法でコミュニケーションを深めているようであれば、家の方針を無理に変えなくてもよいでしょう。
ただ、お子さまが困っているのなら、使い方のルールを決めつつ、スマートフォンを持たせることを検討するのもよいと思います。
自分が嫌なことなのに、頼まれると引き受けてしまい、帰宅後、泣きながら文句を言っていたことがありました。
(中1)
嫌と言えず、かといって断り方がわからなかった子どもは、結局避ける形で友達と距離を置いた。
(中1)
「友達でしょ」と言われると、何でも聞いてしまうようだ。
(高1)
大人のようにさりげなく友達と距離をとることが難しい年頃です。大人の視点からいくつかアドバイスを出し、お子さま自身に対応を考えてもらうといいかもしれません。具体的には「そういうことをされると嫌だ」と自己主張する、部活や委員会では一緒に過ごすけれどフリーな時間は離れる、友達に対しては「ノー」だけではなく相手のよい面を伝えると自己主張をしやすくなる……などです。
ただ、うまく断れず、渋々ながらも友達の要望に応え続けるのも、その子の優しさでもあります。いずれの方法でもお子さまを否定せず、受け止めてあげましょう。
初めは優しかった友達が、だんだん我が子にだけきつい態度をとるようになってきたそうで、嫌がっている。
(中1)
思いやりに欠ける言葉を発する友達がいるが、同じ部活なのでどうしても関わることになってしまう。
(中3)
親しくしていた子が他の友達の悪口を言うのが嫌で、距離を置きたがっている。どちらとも仲よくしたいけれど、うまくいかないようだ。
(高2)
同率2位の「友達に嫌と言えない、断れないようだ」の場合と同じように、嫌なことを言われたりされたら断る、気の合わない友達とはできるだけ離れる、他の人と仲良くするなどの選択肢があることを伝え、お子さまにとって一番よい方法を考えてもらいます。
意外と友達のほうはお子さまが嫌がっていることに気付いていない場合もあるようです。「こういうことをされると嫌な気持ちになる」と穏便に伝えれば、そんなに悪い結果にならないことも多いです。
自分がいわゆる「コミュ障」だと自覚している。会話がつながらないと思っているので、友達が少ないとのこと。
(高1)
小5くらいから人見知りが強くなり、基本的に受け身。本人も気にしている。
(高1)
話しかけられるとうれしいけど、態度に表せないようだ。家では弟に自分の意見を言ったりして楽しそうに笑っているのに、学校では違うと思うと心配。
(中1)
友達の前では、面白いことを言ったりなめらかに会話をしないといけないのでは……といった思い込みをしている場合があります。ですが中高生のグループを見ていると、おしゃべりな子もいれば、あまり話さずニコニコして聞き役になっている子もいます。
口数が少なくても大丈夫、無理に話さなくても心地よく過ごせる友達はいるのだということを伝えてあげましょう。コミュニケーション能力に敏感になっている本人の意識を少し変えられると、気持ちが楽になるかもしれません。
子どもは無邪気で素直な分、人間関係は改善しやすい面があります。一方で、学校が生活の中心になりやすく、人間関係が固定されてしまうので大人以上に大変なことも多いです。お子さま自身に問題を乗り越える力を付けさせることは大事ですが、こじれてしまった場合は保護者のかたの助けが必要になります。お子さまが悩んだ時に相談してもらえるように、日頃からよい関係を築いておきたいですね。