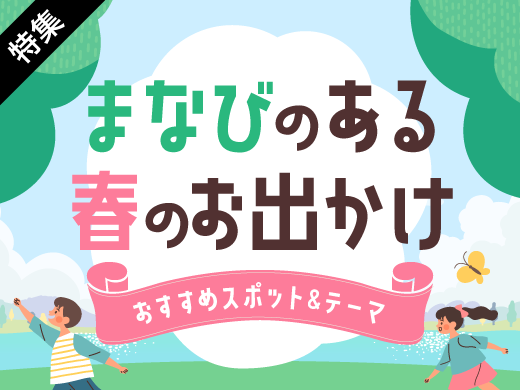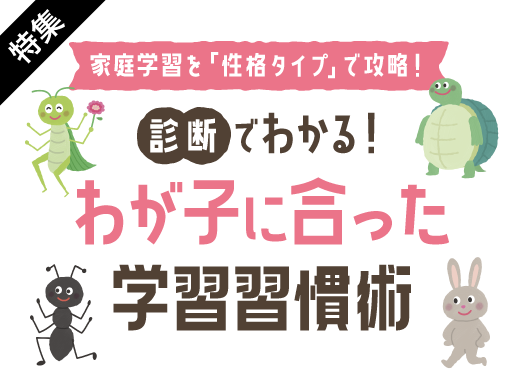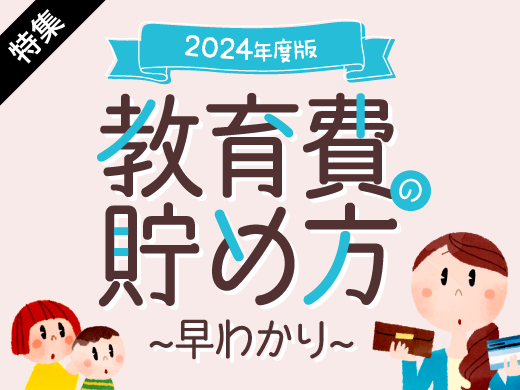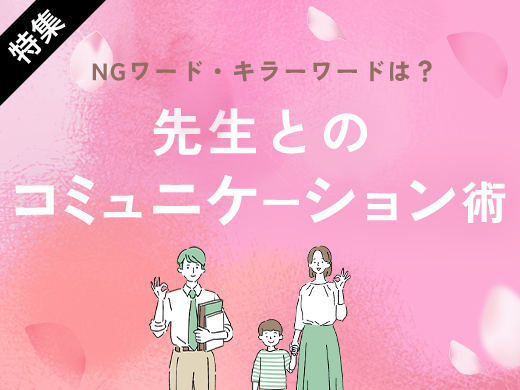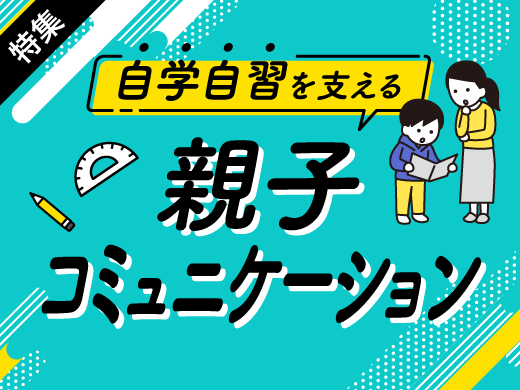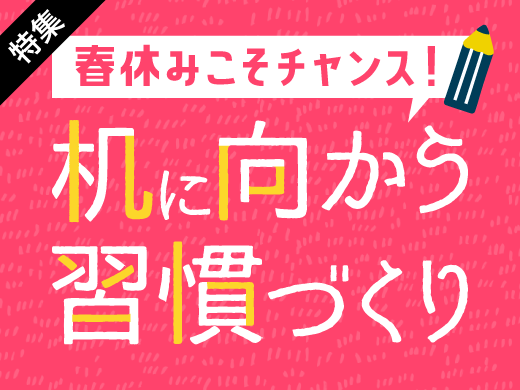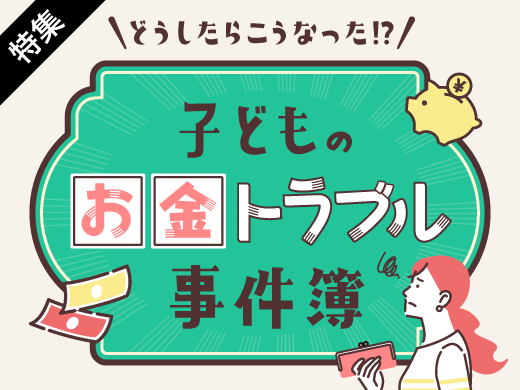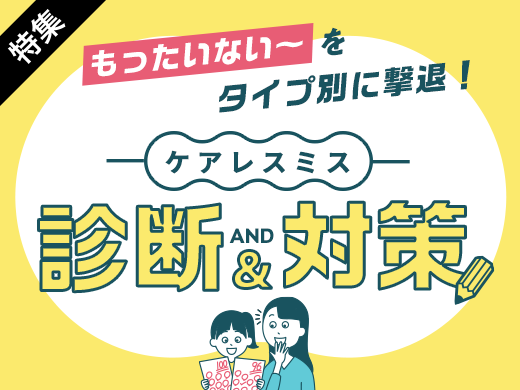今週の特集
「うちの子のケアレスミス、もったいない~」とはがゆく思う保護者のかたは多いもの。とはいえ「気をつけなさい」と言っても、なかなか解決は難しい…。そこで今回は、ミスのタイプを分析して、タイプ別に効率的な対策をお届けします。

- 監修
- 親野智可等先生
繰り返すケアレスミスにはポイントをしぼった対策が効果的。まずはお子さまとミスのタイプをチェックしてみましょう!
「はい」か「いいえ」で答えてください。
※迷った時は直感で答えてください。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
「答え方」を間違える

- 小学生のケアレスミス例
- ・「記号で答える」問題に、ことばで答えてしまう
- 中高生のケアレスミス例
- ・分数で答える問題に、小数で答えてしまう
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
書く文字が「雑」で
間違いになる

- 小学生のケアレスミス例
- ・漢字のトメハネで×になる
- ・「0」と「6」など自分の書いた数字を読み間違える
- ・筆算の桁が乱れて間違える
- 中高生のケアレスミス例
- ・漢字やアルファベットのクセで×になる
- ・余白の計算がきたなく(小さく)て見間違える
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
「勘違い・思い込み」
で間違える

- 小学生のケアレスミス例
- ・「〜しないのはどれ?」という問題で、する方を選んでしまう
- 中高生のケアレスミス例
- ・あてはまるものをすべて選びなさいという問題に対し、1つだけ選んでしまう
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
「まだ途中」なのに
答えてしまう

- 小学生のケアレスミス例
- ・約分がまだ途中なのに解答してしまう
- 中高生のケアレスミス例
- ・記述問題で必要な文字数を満たしていない
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
「時間配分」を間違える

- 小学生・中高生のケアレスミス例
- ・最後まで解けない
- ・最後の方の問題は焦って適当になりがち
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
「解き方」を間違える

- 小学生のケアレスミス例
- ・最近習った公式をつい使ってしまう
- ・速さ・時間・距離がごちゃごちゃになる
- 中高生のケアレスミス例
- ・図・表・グラフの読み取りミス
- ・問題の条件や手順を読み飛ばしている
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
「書き忘れ・書きすぎ」
でバツや減点になる

- 小学生・中高生のケアレスミス例
- ・単位を間違える
- ・単位を付け忘れる
- ・主語がない
- ・不要な送り仮名をつける
ウィークポイント1
計算して答えの「数」がわかったり、文章題で書き出す場所がわかったりすると安心して問題の指示を忘れがち。
小学生はまずは単位の書き忘れや書き間違いから、中高生は語尾や漢字、解答欄の入れ違いなどから、指示と合わせて見直すクセをつけて。

- 問題をもう一度読み、「記号で」「文中の言葉を使って~」など、答え方の指示まで確認する習慣をつける。
- 単位の書き忘れや書き間違いに注意する。
- 解答欄に記載された記号や書き出し・文末などの文字にも気をつける。
答えと答え方を区別させることで、最後にもう一度見直す意識をもたせましょう。
ウィークポイント2
漢字の問題だけでなく、計算問題でも、書き方のクセは思った以上に点数にひびきます。丁寧に書くことはもちろん、間違えやすいところを意識して練習したり、間違えにくい書き方を決めて。

- 数字の書き方のクセを見つけて直す。
- 筆算や計算は余白を使って大きく書く。小さな文字は見間違いの原因に。
- 鉛筆をきちんと削っておく。
名前や書き始めを丁寧にすると、しばらくは丁寧に書けます。だんだん雑になりがちですが、全体にきれいな文字になります。
ウィークポイント3
この問題はこう解くんだ!と最初に思い込んでしまうと、途中で軌道修正するのが難しくなります。あれ?と思っても強引に答えてしまうことも。初めに問題を正しく理解することがすべてのカギに。

- 答え方の指示の言葉にアンダーラインを引く。
- 問題のキーワードを囲む。
- 問題は2回読む。解いてから問題を読み返す。
慣れないと面倒に感じることもあるので、点数に直結する一手間だと意識させましょう。
ウィークポイント4
ペース配分を意識しないと、最後まで解ききれなくなりがちです。いい加減に解いているわけではなく、不安や焦りも原因に。急いで全問解くよりも、できる問題を正しく答えることが大切と気づかせて。

- 大きく深呼吸してから、ゆっくり名前を書く。
- ざっとすべての問題を見て、できそうな問題から解く。
- 残りの時間を意識する。
- ※一問に時間をかけすぎるとき
- 残りの時間を気にしない。
- ※焦って落ち着かないとき
自分の気持ちを管理するために深呼吸は効果的。あわせて、解けそうな問題を探すことを習慣に。
間違いや減点の原因は知識や理解の不足かも。自覚のない隠れケアレスミスの可能性もあるので、この後に紹介する見直し方法を試してウィークポイントを確認しましょう。

テストが戻ってきたときは、ケアレスミス対策の大チャンス!
小学生の保護者のかたは、今までのテストが残っていたら、何枚か親子で見てみるのもおすすめ。絶対にやってほしいことを4ステップで紹介します。
- ※中高生の保護者のかたは、「STEP1」をぜひお試しくださいね。お子さま本人が「テストの見直しをしよう」と思える環境づくりが、ケアレスミス撲滅のヒケツです。

常に大切。嬉しい気持ちを刺激すると前向きになる
点数が低くても、できている部分を探しましょう。字が丁寧に書けていたり、前回間違えた問題ができていたり、途中までは合っていたという問題でも「ここまではできていたね!」「この科目はがんばったね」とほめてあげて。
子どもなりの努力や成長を見つけて言葉にすることで、自信がついて、やる気がわいてきます。反対に、いきなり間違いを指摘されると、気持ちも沈んでしまいますし、保護者のかたに対して反発してしまうことも。
1科目でも「ほめられた!トクイだ」と思える科目があると、他の科目にもいい影響がありますよ。

これでできたらケアレスミス撲滅の可能性大
正しい答えを見る前に、間違えた問題をいくつか解き直してみましょう。落ち着いて問題を読んだり考えたりすると正しい答えが出せることも。つまりケアレスミスによる失点です。
ケアレスミスは「伸びしろ」。失敗を確認するという辛い作業ではなく、気をつければ点数が上がる問題を探す宝探しのような気持ちでやってみて。
- ※中高生の保護者の方は、STEP2以降は方法だけ伝えてお子さまに任せて大丈夫。ケアレスミスで落ち込んでいたら、「ケアレスミスは、『伸びしろ』だよ」と声をかけてあげると〇。

どこがウィークポイントなのかが見えてくる
正しい答えや解き方を見て、どこで間違えたのかを確認しましょう。同じようなケアレスミスを繰り返していることも多いので、見直し時間を作る、書き方のクセを見直すなど、紹介した解決策を参考に対策を考えて。
ウィークポイントを自覚できると、やる気も効率もアップします。知識がない、理解できていないなどケアレスミスでない場合は、あらためて復習を。
- 見直しを すれば 百点 近づくぞ
- 検算を すれば 十点 増えるかも
- 単位ミス 答え合っても 点が減る
- 0と6 2と3などは はっきりと
- 繰り上がり しっかり書けば ミスが減る

もったいない、次は気をつけたいという意識がぐんとアップする!
ケアレスミスが多かったテストは、その問題に正解していた場合の点数を計算してみましょう。もったいないな、と自分で思えると、自然とミスをしないように気を付けるようになります。
また、頑張ればこのくらいの点数がとれるんだ、という自信にもなります。本人が残念に思うことが大事なので、保護者のかたは「やればできるんだね」と背中を押す言葉かけを。
- また間違えてる!/この前も言ったのに…

次は解けそう?/もう1回解いてみようか/いまの話、覚えちゃおう
いそがしい毎日で、お子さまの言動に「イラッ」としてしまうことは、誰しもあります。テストを見返すときは、保護者のかたが前向きに向き合える時間をえらぶのがオススメです。


そもそもケアレスミスは繰り返しやすいもの。性格やクセによるものも多く、一朝一夕で直せるわけではありません。だからこそ、できていることで自信をつけて、もう少しがんばればもっと良くなると思わせることが大切。
漢字は間違っているけれどトメはできている、答えは違ったけれど考え方は合っているなど、小さなことでもよいのでほめる部分を探しましょう。そのあとやり直したいものを少しだけ直させれば叱らなくても積み重ねられます。

ケアレスミスは本人が自覚して、無くしたいと思わなければ減りません。テストで結果を出せれば、喜びから次も注意深く解くようになります。
中学・高校なら定期テストの予定がわかりますし、小学校では単元の終わりにまとめのテストがあるので、進み具合に気を配ってテストの気配を察知したら対策を確認するようにしましょう。

ケアレスミスは本人が一番くやしいのです。勉強の先に将来の明確な目的が見えてくると、さらに注意力も上がってきます。家庭では「大丈夫!そこがのびしろだよ」と明るくサポートを。
監修/親野 智可等 先生
長年の教師経験をもとに勉強法・家庭教育・親子関係などについて具体的に提案。
Instagram、Twitter、Voicy、YouTube「親力チャンネル」、Blog「親力講座」、メルマガなどで発信中。ドラゴン桜の指南役としても著名。最新刊「子育て365日」などベストセラー多数。全国各地の教育講演会でも大人気。詳細は「親力」で検索