【分析2】中学1年生にとっての「テスト」と「主体的な学び」[1/3]
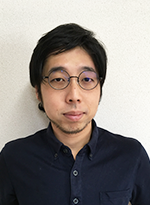
前馬 優策●まえば・ゆうさく
大阪大学大学院人間科学研究科講師。大阪府茨木市生まれ。大阪大学人間科学部卒業後、大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得退学。甲子園大学総合教育研究機構助教を経て、現職。専門は教育社会学。学力格差の発生プロセスや、格差社会における学校文化論に主要な関心がある。共編著に『福井県の学力・体力がトップクラスの秘密』(中央公論新社)、論文に「日本における「言語コード論」の実証的検討」(『教育社会学研究』第88集)、「学力格差を縮小する学校」(『教育社会学研究』第80集、共著)など。
1.「主体的な学び」と子どもの現状
<「主体的な学び」とは>
現在、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善が求められている。これらが強調される背景には、そもそもこれまでの学校教育における学びが、「非主体的・非対話的で、浅い学び」であったという認識がある。本稿では、特に「主体的」という部分に焦点を当て、中学校の「テスト」から見る「主体的な学び」について検討していくが、そもそも、「主体的な学び」とはどんな学びであろうか。
文部科学省の定義を借りれば、「主体的な学び」とは、「学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しをもって粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる」学びのことである。理念的な定義であるため、これが果たされている学習者が本当にいるかどうかというと、そうそういるものではないと考えざるを得ない。
<子どもの現状>
国際的に見ても、日本の子どもは「主体的」とは言えない現状がある。2012年に実施されたPISA(日本では高校1年生が対象)では、「数学を学ぶ事柄に興味がある」という生徒がOECD平均の53%に比べて、日本では38%であり、かつてより増加しているものの、いまだに低水準であることがわかっている。また、いわゆる「問題解決」に対する意欲も、OECD平均より低い水準である(OECD 2013)。ただ、2015年の調査では、「科学」を学ぶことを楽しんでいる生徒は2006年よりも減少しOECD平均も大きく下回っているが、「将来設計に役立つ」と考える生徒は大幅に増えOECD平均と同水準になったという結果が見出されている(OECD 2016)。この調査は、高校1年生に対して行われたものであるが、義務教育を終えた子どもたちがどういった心持ちでいるかを、ある程度推測することができる。すなわち、国際的に見た日本の子どもたちは、学習の内容自体に興味や楽しみを覚えることは少ないが、「道具として役に立つから」という理由で学習の動機づけを行っているというわけである(ただし、それとて「強い」というわけではない)。
先の「主体的な学習」の定義に照らし合わせると、「学ぶことに興味や関心を持ち」という部分は低いが、「自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら」という部分はそれなりである、と言えるかもしれない。教師や保護者の目線に立つと、「役に立つ」という形で道具的な動機づけを行うことよりも、「楽しい、興味深い」といった内発的な動機づけを行うことはより難しいと見ることもできそうだ。
主体的に学ぶこともさることながら、「学ぶこと=勉強」と捉えたとき、学ぶことの魅力は年齢を経るごとに失われていると捉えられる現状がある。この図(「親子調査2016」速報版 図1-2-1)は、東京大学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所による「子どもの生活と学びに関する親子調査2016」の結果の一部である。下側の棒グラフが、勉強が「まったく好きではない」もしくは「あまり好きではない」と回答した子どもの割合を学年ごとに示したものであるが、小4~小6は3割程度だった数値が、中1で45.5%、中2で57.3%になり、中3~高3までは6割前後で推移している。ざっくりと見積もると、勉強が好きではない生徒は、小学校の時から中学1年生を経て、2倍近くまで増えることになる。
<中学校で何が起こっているのか>
ここで、ある疑問が浮かんでくる。「中学校に入ってから何が起こっているのか」という疑問だ。一般的には、こういった現象は「中1ギャップ」を原因として考えることができる。「中1ギャップ」とは、小学校から中学校へと移行するにあたって、中学校文化、教科担任制、部活動、新たな人間関係、学習方法の違いなど、生徒が感じるギャップのことであり、それによって生じる中学校への不適応のことを指す。
上記のグラフで見たような、中学校入学後に勉強が「好き」だった生徒が減ってしまうことも、「中1ギャップ」で説明することは可能だろう。しかし、そのプロセスについて詳しいことはあまりわかっていない。
筆者も参加した18組の親子に対するインタビュー調査は、中学1年生が1年間で「勉強」に対して何を感じていたのかを明らかにしたいというねらいを有するものであった。ここではそのすべてを検討することはできないが、インタビューを通じて見えてきたものの1つが、中1の生徒にとって「テスト」というものが大きな意味を持つのではないかということであった。
2.「テスト」の社会的機能
やや抽象的な話になるが、学校教育には3つの社会的機能があると言われている。1つ目は、「社会化機能」であり、学校が、子どもたちを社会の一員として生きていけるように「教育」していく機能である。2つ目は、「選抜・配分機能」であり、学校が、同学年の集団から子どもたちを選抜しながら、さまざまな社会的地位や社会的役割に配分していくという機能である。そして3つ目は、「正当化機能」であり、学校を通してさまざまな社会的地位に振り分けられた結果を、まさに学校教育を通じたがゆえに正当化してしまうという機能である。
これらの学校教育の3つの機能をもとに中学校の「学び」を捉えたとき、「テスト」が非常に重要な位置を占めていると考えることができる。まず、テストの実施前には「テスト勉強」をすることが求められ、これまでの学習内容を復習することが求められる。また、学習の仕方についても、計画的に、コツコツと勉強することが求められ、「提出物」を確実に出すことも求められる。そうやって、学びに関する態度や習慣を身に着けていくのである(学校教育の「社会化機能」)。一方、「テスト」は、これまでぼんやりとしか見えていなかった「学力」を数値化し、序列化するための道具でもある。それぞれの「テスト」が、高校の選択に直結するわけではないが、自らの相対的位置を知りながら進路選択の材料となっていく(学校教育の「選抜・配分機能」)。さらに、「テスト」はすべての生徒にある程度十分な準備期間を与えたうえで行われ、その結果は「個人の努力」を反映したものとして経験される(学校教育の「正当化機能」)。こうした意味で、「テスト」はまさに、学校教育の機能を凝縮したシステムなのだと言える。
そこで、以下では、中学1年生の生徒たちが、中学特有の「テスト」に対してどのような意味付けをし、「テスト」とどのように向き合っているかを検討していくことにする。その中で、生徒たちが「テスト」を契機として主体的に学ぶ/学ばない様子を描くことで、「主体的に学ぶ」ための道筋を考えるヒントを提示したい。









