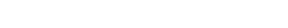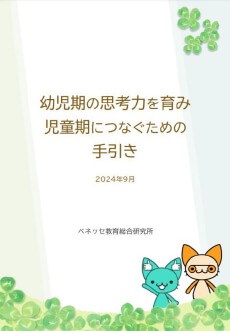【学会発表報告】「幼児期の思考力を育み児童期につなぐ手引きの開発」日本発達心理学会第36回大会 (会場:明星大学)
はじめに
ベネッセ教育総合研究所学習科学研究室 主任研究員の杉田美穂、小野塚若菜とベネッセ新横浜保育園の梅澤京子先生、ベネッセ川崎新町保育園の林舞子先生が、2025年3月4日から6日に行われた日本発達心理学会第36回大会(会場:明星大学)において研究発表を行いました。以下、内容を簡単にご紹介します。
▼発表ポスター(PDF)はこちらから
幼児期の思考力を育み児童期につなぐ手引きの開発_日本発達心理学会発表ポスター
幼児期の思考力を育み児童期につなぐ手引きの開発_日本発達心理学会発表ポスター
1. 問題と目的
子どもの発達や学びの連続性を保障するために、幼児期と児童期の教育の円滑な接続は極めて重要であり、幼小の資質・能力の育成につなぐカリキュラムの編成や実施が求められています(中央教育審議会, 2023)。杉田・小野塚(2024)は、5歳児の遊びの中で発揮を想定できる「比較する」「多面的にみる」など、小学校の学習指導要領から抽出した19の思考スキル(泰山ほか, 2014)について、それらの発揮を見とり促す保育者の具体的な環境構成と援助例を明らかにしています。
このことは、幼児期の遊びと児童期の学びはつながっていること、幼児の思考力を育むためには保育者の援助が重要であることを示しています。また、幼児期は遊びを通した多様な体験から小学校以降の生活や学習の基盤となる資質・能力を育むことが大切ですが、保護者や社会に十分に伝わっていないという課題があります(文部科学省, 2024)。
本研究では、5歳児の思考力を19の思考スキルの発揮と定義し、その発揮を遊びの中でどう見とり育むかを解説する「幼児期の思考力を育み児童期につなぐための手引き」(以下、手引き)を開発しました。手引きの整理が、保育者や小学校の先生、保護者に幼小接続期の思考力育成の援助や指導に生かす際の有用性を検討します。
このことは、幼児期の遊びと児童期の学びはつながっていること、幼児の思考力を育むためには保育者の援助が重要であることを示しています。また、幼児期は遊びを通した多様な体験から小学校以降の生活や学習の基盤となる資質・能力を育むことが大切ですが、保護者や社会に十分に伝わっていないという課題があります(文部科学省, 2024)。
本研究では、5歳児の思考力を19の思考スキルの発揮と定義し、その発揮を遊びの中でどう見とり育むかを解説する「幼児期の思考力を育み児童期につなぐための手引き」(以下、手引き)を開発しました。手引きの整理が、保育者や小学校の先生、保護者に幼小接続期の思考力育成の援助や指導に生かす際の有用性を検討します。
2. 手引きの概要
幼小共通の枠組みとして19の思考スキルを用い、各スキルについて5歳児の遊びに見られる具体的な姿と保育者の環境構成や援助例、小学校の学習活動例をまとめて解説しました。幼小双方から同じ枠組みで思考力を捉えることにより、幼児期から児童期の学習を見通し、児童期においては、幼児期の体験を通して育まれた資質・能力をふまえた援助や指導に活用することを目指しています(図1)。
《内容》
(1)幼小接続期の思考力について
(2)19の思考スキルと子どもの姿
(3)活用事例の紹介
(1)幼小接続期の思考力について
(2)19の思考スキルと子どもの姿
(3)活用事例の紹介
▼全ページのダウンロードはこちらから
https://benesse.jp/berd/jisedai/research/detail_240930-1.html
https://benesse.jp/berd/jisedai/research/detail_240930-1.html
3. 方法
保育における有用性を検討するため、関東近郊の民間保育所2園の協力を得て、手引きの枠組みを用いて4・5歳児を対象とした保育実践を次の手順で計5回行いました。
- 保育計画では活動を通して子どもが発揮する思考スキルを想定し、環境の準備を行いました。
- 保育のふりかえりでは、子どもがどのような思考を働かせているかを見とる観点として、思考スキルの枠組みを用いました。
- 実践後に手引きに示す枠組みを用いて保育計画や環境構成・援助を考える有用性や課題について、実践者と発表者が協議しまとめました。
4. 結果と考察
手引きの枠組みを用いる効用として、次のことが定性的に示されました。子どもの具体的な姿を基に、育まれている思考力と必要な環境構成や援助について、保育者、保護者、小学校の先生が共通の枠組みで理解する一助になることが期待されます。
-
保育者からの声
「子どもの思考力と経験を見とりやすくなる」「保育の価値が可視化され、援助が考えやすくなる」「保護者とともに子どもの成長を喜ぶ視点になる」 -
小学校の先生からの声
「幼児期にどのような遊びを通して学んでいるのか分かった」「幼児期の体験を想定することで、指導案を書く際に子どもの姿をより具体的にイメージできた」
5. 今後の課題
本研究は、幼児期に育まれた思考力を児童期につなぐことを目指しています。手引きの開発を通して整理した観点が、小学校入学期の指導や授業改善に生かせるか、幼小一貫した思考力育成に寄与できるかについて、さらなる実践と検証が必要と考えています。
【参考文献】
- ・中央教育審議会(2023)「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について~幼保小の協働による架け橋期の教育の充実~」
- ・杉田美穂・小野塚若菜(2024)「5歳児の思考力発揮を促す保育者の援助について」日本発達心理学会第35回大会
- ・泰山裕,小島亜華里,黒上晴夫(2014)「体系的な情報教育に向けた教科共通の思考スキルの検討:学習指導要領とその解説の分析から」日本教育工学会論文誌,37(4):375-386.
- ・文部科学省(2024)「今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会 最終報告」