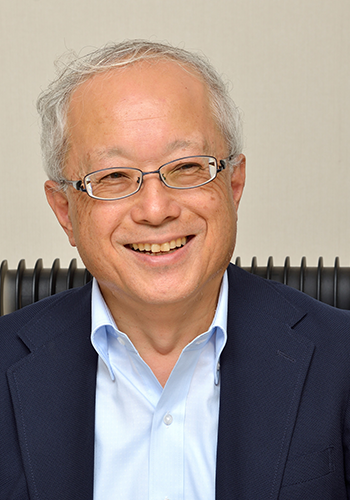学びが画一化している現在の学校教育
—日本の教育の現状と課題を、どのように捉えられているでしょうか。
榊原 小児科医である私は長年、発達障害の子どもたちと向き合ってきました。その経験から、学校教育について考えていることをお話ししたいと思います。
日本の学校教育制度では、特別支援学校や特別支援学級を設置し、通常学級では学ぶことが難しい、主に肢体障害や発達障害の子どもたちに特別支援教育が行われています。
通常学級のほかに学びの場所を設けるという点では、一見、学びが多様化しているように思えますが、実際にはその逆だと言えるのではないでしょうか。特別支援教育の根幹にあるインクルーシブ教育の理念からいえば、どのような子どもも一緒に学び、お互いにかかわり合いながら、一人ひとりが成長していく環境や支援を提供するのが、学校教育が目指すべき姿だと考えます。
子ども一人ひとりの可能性を伸ばすことが重要という意味で、私が今関心をよせているのは、「ギフテッド」と呼ばれる子どもたちです。ギフテッドには様々なタイプがいますが、中心となるのは知的能力が非常に高い子どもたちです。ギフテッドの子どもは、知的能力が高いために、あるいは高いにもかかわらず、様々な適応困難を起こしていることが分かっています。普通教育の先を進んでいるために授業から逸脱したり、教員との信頼関係が築けなかったりすることです。
ギフテッドの子どもは約5%、発達障害や知的障害の子どもは約10%いると言われていますから、現在の普通教育では、合わせて約15%の子どもが、それぞれの能力に合った教育が受けられていないと言わざるを得ません。
現在の普通教育は、子どもの学力を平均的に伸ばすことを目的として作られた、明治以降の教育制度を基本的には継続しています。その結果として、質の高い教育を提供し、国全体として学力の平均値を上げることができました。一方で、学校教育が、画一的になったとも言えます。
その負の側面の影響を強く受けているのが、発達障害の子どもたちです。発達障害の子どもの多くは、自尊感情が低く、学校に苦手意識を持っています。この問題は、現在の学校体制が作り出したことだと言えるでしょう。ギフテッドの子どもも、現在の普通教育でその力を伸ばし切れていません。例えば、アメリカなどの諸外国では、公立学校でもギフテッドのための教育プログラムを用意し、飛び級制度を設けていますし、家庭学習を正式な教育と認めるホームスクールのシステムがあります。
教育に必要な、教員、教育課程、評価のダイバーシティ
—すべての子どもそれぞれに合った教育を提供していくことが重要ということでしょうか。
榊原 私としては、多様性のある教育こそが、これから求められる教育の姿だと考えます。
それは、発達障害やギフテッドの子どもに限ったことではありません。新学習指導要領でも示されているとおり、これからの子どもたちには「答えが一つではない問題に答えを見いだす力」や「新たな価値を生み出す力(イノベーティブな力)」が必要になります。科学技術の発達、気候変動、超高齢社会など、これまで予想もしなかったことが起きており、それは今ある知識・技能だけでは決して解決できるものではありません。2018年にノーベル賞を受賞した本庶佑氏は、研究者にとって大事なことの一つに、「教科書に書いてあることを信じないこと」と言われましたが、まさにイノベーティブを象徴的に言い得た言葉です。
子どもにイノベーティブな力を育む鍵となるのは、「遊び」です。遊びにはゴールがないために、どこまでも自由に探索する力が育ちます。さらに「高い共感性」も挙げられます。イノベーティブは、「発見」とは異なります。アイデアを社会的意義のある価値に創造することであり、「人のために役に立ちたい」という思いがイノベーションを生み出します。
ハーバード大学テクノロジー起業センターのトニー・ワグナー氏は、イノベーティブな仕事を成し遂げた起業家を研究し、共感性とイノベーションの結びつきを提唱しました。また、脳科学者の西剛志氏は、新たな発見をした際に働く脳の部位は、人の気持ちを理解する部位と一致することを突き止めています。
—イノベーティブな力を子どもたちに育むには、どのような教育が必要だとお考えですか。
榊原 学習者である子どもに影響を及ぼす人々、つまり、保護者、家族、友人、教員、さらに教育体制を担う国や自治体がどうあるべきか、どのようにかかわるべきか、何をすべきかを考えることが重要です。
最も重要なことは、先ほど述べたように、教育における多様性(ダイバーシティ)の徹底だと考えます。これまでの教育は、与えられた知識・技能を覚えて再現することに重きが置かれていました。学びが画一的であれば、それで育った人も同じようになり、イノベーションを生み出すアイデアはなかなか出てこないでしょう。
教育に多様性を生み出すためには、どうすればよいのか。まずは、教員となる人材の幅を広げることです。一般企業に勤務していた人や研究者など、様々な経験を持つ人材を義務教育の段階から学校現場で積極的に活用していくのです。教員免許を持たなくても、特別活動や課外活動などに協力してもらうことも考えられます。
次に考えたいのは、カリキュラムの多様性です。学習指導要領によって、国全体の平均学力が高まった今は、次の段階として、新しい社会を築くイノベーションを生み出す人材を育てる教育を推進することが必要だと考えます。多様なカリキュラムの中から、学習者が自身の適性や希望に合ったものを選べるようにすれば、多様な人材が育ち、それらの人同士がかかわることでイノベーションが生まれていくのではないでしょうか。
—指導が多様になるのであれば、評価も多様となる必要がありそうです。
榊原 現在の学校教育では、習得した知識・技能を試験によって測り、一人ひとりを評価します。その結果、低い評価を受けた子どもは、自己肯定感が低くなり、その後の学習にも大きく影響してしまいます。私は教育の専門家ではないから言えるのかもしれませんが、評価によって自尊感情を傷つけられてきた発達障害の子どもたちを見てきた経験から、評価を行う意味を見直していただければと思うのです。子ども個々の得意・不得意は、試験で評価しなくても指導の過程である程度把握でき、それを基にして指導を工夫できるのではないでしょうか。
私は、子どもの自己肯定感・自尊感情の研究も行っています。日本の子どもの調査結果を見ると、小学校入学後、学年が上がるごとに自尊感情が下がっています。その理由の一つに挙げられるのは、試験での評価があります。試験には平均点があり、およそ半分の子どもは平均点以下となります。それを子どもに伝えることは、学習への奮起を促し、学習への動機づけを持たせる側面も確かにありますが、特に小さい子どもにとっては負の影響の方が大きいと言えます。評価は、教員の指導のための資料にとどめることも、一案ではないかと思うのです。
—新学習指導要領においても、評価の方法については大きな課題となっています。
榊原 評価の観点は、今は知識・技能の定着が中心ですが、新学習指導要領では、それに加えて、「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」が示されました。答えが一つではない問題に答えを見いだしていく力や、新たな価値を生み出す力の育成を目指すのであれば、それらの力が身についたかどうかを評価すべきではないでしょうか。
もちろん、新しい評価規準をつくることは、大変難しいものです。それには「人のwell-beingとは何か」を考えるところから始めなければならないでしょう。経済的に豊かならよいのか、社会的な地位が高ければよいのか、好きなことができていればよいのか、それぞれのwell-beingが高まる方法は、また多様です。例えば、アメリカでは、居住区域や人種によって学力に差が出ることがありますが、平均化しようという議論は出てきません。それは、それぞれのwell-beingの規準が異なると分かっているために、横並びにする意識がないのです。そうした考え方も、評価方法を考える際のヒントになると思います。
ただ、それらの力は、最初から育成するのを目指すのではなく、何かに取り組んだ結果、身についているものだと捉えています。ほとんどの教育では、○○力を育成するためとして論理的にカリキュラムを作成しています。しかし、そのプロセス自体がクリエイティブとは言えません。自分が楽しいと思うことに取り組み、夢中になって学び、その結果、身につくのが、○○力なのです。
*well-being…肉体的にも、精神的にも、社会的にも、すべてが満たされている状態のこと(日本 WHO協会訳)