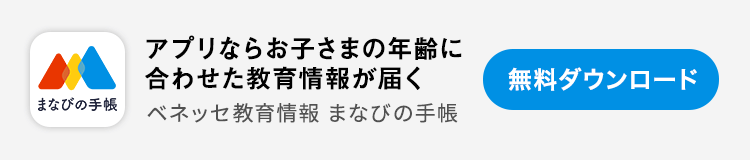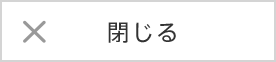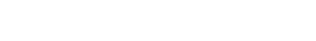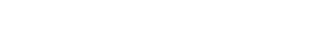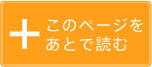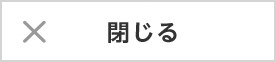係り結びとは
係り結びとは何ですか。見分け方も教えてください。
進研ゼミからの回答
文中に係助詞「ぞ・なむ・や・か・こそ」が出てきたら、文末が終止形以外の活用形になるのが係り結び!
■係り結びは、内容を強調したり疑問や反語を表したりするときに使います。
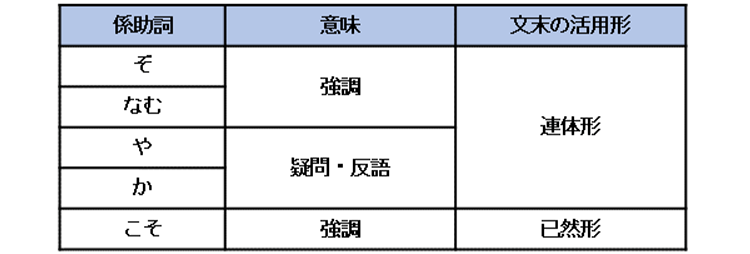
係助詞があり、文末が連体形か已然形になっていれば、係り結びだと見分けることができます。
■係り結びの例
・みやつことなむいひける。
係助詞「なむ」があるため、文末が「けり」の連体形「ける」になります。
・○○とこそ聞こえけれ。
係助詞「こそ」があるため、文末が「けり」の已然形「けれ」になります。
※「こそ」だけが已然形になることを覚えておきましょう。